アクティブ・イマジネーションのテクニックでは、眠りにつく直前のような薄明かりの意識に自分を「落とす」ことになります。 目覚めているという意識はありますが、イメージが無意識のうちに湧き上がってくる、いわば覚醒夢のような状態になります。 この状態を誘発し、維持することで、浮かび上がってきた人物との対話が始まり、彼らと関係を持ち、彼らを統合することができるのです。 ユングが夢よりも能動的な想像力を好んだのは、前者では自我がしっかりしているのに対し、後者では自我が弱く、無意識に対して不平等な立場にあるからです。 ユングの理論では、無意識の力を擬人化して関係づけることが重要です。そうすることで、これまで自我の機能や意識を膨らませたり変えたりする恐れのあった力を、ある程度コントロールできるようになるからです。 積極的な想像力は、ユングが個性化のプロセスを促進するために用いた実践と技法の一つです。これは、無意識の要素を統合して、自分の精神の無視されていた分断された部分を発展させ、より充実した意識的な人生を送るための心理的プロセスです。 赤い本』は、ユングが危機に瀕していたときの活発な想像力のセッションを記録したものであるともいえます。 そして、「赤い本」のモデルとメッセージは、確かに個性化のプロセスであり、その目的と実践、そしてそれに伴う潜在的な危険性である。
内容について
内容:『赤い本』の中でユングは、個性化のプロセスの重要性を説き続け、そのほとんどすべての例で、すぐに警告を発しています。 ユングは読者に対して、自分の真似をしないように、自分が無意識と向き合っている旅を盲目的に追わないように、と何度も繰り返している。 個性化の要点は、自分の道を進むことだと彼は強調する。
道は一つしかなく、それはあなたの道です。 道を探しているのか? 私は自分の道から遠ざかるように警告する。 それはあなたにとって間違った道かもしれません。 それぞれが自分の道を行くように。 私はあなた方の救世主でも、法の番人でも、師匠でもありません。 あなた方はもはや幼い子供ではないのだから...それぞれが自分の道を模索するように。 その道は、共同体における相互の愛につながる。 人は自分の道の類似性と共通性を見て感じるようになるでしょう。 (p. 231)
ユングは明らかに、盲目的な英雄崇拝やカルト形成の危険性を認識していました。そのため、数年後に「ユングではなくユングでよかった」と語ったのかもしれません。
ユング自身の道は、彼が「深層の精神」と呼ぶもの、すなわち無意識に取り憑かれた感覚から始まります。これは、彼が「時代の精神」と定義する、日々の目覚めた意識や日常生活とは異なるものです。 私たちは、日常生活の多くのことに大きな影響を与えている深層の衝動に気づかず、生活の表層で生きているという前提に立っています。 ユングは「赤い本」の冒頭で引用した旧約聖書の預言者との類似点を挙げていますが、同じようにビジョンの洪水に圧倒され、読者のためにこれらのビジョンとそれに対する自分の理解を記録しなければならないと感じています。 しかし、ユングは自分の道に盲目的に従わないようにと常に言い聞かせながら、自分はこのような限定された意味での預言者のような存在でしかなく、自分自身が預言者や英雄、救世主のような存在ではないことを強調しています。 実際、こうした人物の模倣は『赤い本』全体を通して疑問視され、損なわれています。
続いて、ユングの危機の先駆けとなった1913年の終末論的なビジョンが語られますが、それは実に悲惨なものでした。 聖書の「ヨハネの黙示録」に出てくるエピソードのように、ユングが見たものは、大洪水によるヨーロッパの完全な破壊、血の海、宇宙からの殺戮的な寒さなどでした。 終末論的なビジョンの後には、主人公の死を伴う2つのビジョンが続きます。 最初のビジョンでは、ユングは地下の洞窟に落下します。 地面に開いた穴から下を覗くと、そこには小川が流れている低層階が見えます。 そこには頭に血のついた傷を負った若い勇者の死体が浮かび、次に黒いコガネムシが通り過ぎます。 川底に映ったユングは今度は太陽を見ますが、すぐに大量の蛇と大量の血でかき消されてしまいます。 次のビジョンでは、ゲルマンの英雄ジークフリートが、死者の骨で作った戦車に乗って山から降りてきます。 ユングは若い「野蛮人」とともに山の麓に隠れ、ユングにジークフリートを殺害するよう説得し、待ち伏せして射殺します。 ユングはこれらのビジョンを理解しなければならないという強いプレッシャーを感じ、失敗したら自殺しようと考えていました(ナイトテーブルの引き出しに弾の入ったリボルバーを保管していました)(MDR, p.180)。
The technique of Active Imagination involves allowing oneself to “drop” into a twilight consciousness similar to that we experience just before falling asleep. We are still aware that we are awake, but images begin to bubble up from the unconscious in a sort of waking dream. Inducing and sustaining this state, one can then open a dialogue with the figures that emerge, relating to them and integrating them. Jung preferred active imagination to dreaming because the ego is on firmer footing in the former while in the latter it is on weaker, unequal footing relative to the unconscious. Personifying and relating to the forces of the unconscious is essential to Jungian theory, for in doing this one can gain some measure of control over forces that previously threatened to inflate or otherwise alter ego functioning and consciousness. Active imagination is one of the practices and techniques that Jung used to facilitate the process of individuation, a psychological process of integrating elements of the unconscious so as to develop the neglected, split-off parts of one’s psyche and thereby live out a fuller and more conscious life. The Red Book may be considered, in part, a record of many of Jung’s active imagination sessions during his crisis. And the model and message of The Red Book is certainly the process of individuation—its purpose and practice as well as the potential dangers involved.
Content:
Throughout The Red Book, Jung continually expounds on the importance of the process of individuation, and, in just about every instance, immediately follows up with a warning. He implores readers again and again not to mimic him, not to follow blindly the journey he is undergoing in his own confrontation with the unconscious. The whole point of individuation, he emphasizes, is for one to follow one’s own path:
There is only one way and that is your way. You seek the path? I warn you away from my own. It can also be the wrong path for you. May each go his own way. I will be no savior, no lawgiver, no master teacher unto you. You are no longer little children…May each seek out his own way. The way leads to mutual love in community. Men will come to see and feel the similarity and commonality of their ways. (p. 231)
Clearly, Jung was aware of the dangers of blind hero worship and cult formation—a concern that perhaps led him to say years later that he was glad to be Jung and not a Jungian!
Jung’s own path begins with a feeling of being possessed by what he calls “the spirit of the depths”—i.e., the unconscious, as distinct from “the spirit of the times,” which he defines as daily waking consciousness and routine. The assumption is that we live on the surface of our lives, unaware of the deeper impulses that have a major influence on so much in our daily lives. Drawing parallels to the Old Testament prophets, whom he quotes to open up The Red Book, Jung feels similarly overwhelmed by a flood of visions and feels similarly compelled to record these as well as his understanding of them for his readers. Still, with the continual reminders not to follow his path blindly, Jung stresses that he is only like a prophet in these limited senses and that he is not himself a prophet, hero or messiah figure. Indeed, imitation of such figures is questioned and undermined throughout The Red Book.
What follows is an account of the apocalyptic visions of 1913 that ushered in Jung’s crisis, and they are truly harrowing. Like episodes from the biblical Book of Revelation, Jung’s visions involve the complete destruction of Europe by vast floods, a sea of blood, a killing cold from outer space, and the like. The apocalyptic visions are followed by two visions involving the death of the hero. In the first, Jung drops down into a subterranean cavern. Peeking down through a hole in the ground, he catches a glimpse of a still lower level with a stream rushing past. The body of a young hero floats by with a bloody wound on his head; next, a black scarab passes. Reflected in the stream bed, Jung now sees the sun reflected, but this is soon blotted out by a glut of serpents and a surge of blood. In the next vision, the Germanic hero Siegfried rides down from the mountains on a chariot made from the bones of the dead. Jung hides at the base of the mountain along with a young ‘savage’ who persuades Jung to murder Siegfried, which they do by ambushing the young hero and shooting him. Jung felt tremendous pressure to understand these visions, so much so that he contemplated suicide if he failed (he kept a loaded revolver in the night table drawer) (MDR, p. 180).
これまでの自分の人生とキャリアを振り返って、彼はヒーローの原型(特定の形をとった普遍的な無意識の衝動や本能、この場合は、超人的な個人、つまりヒーローを作りたいという、すべての文化が抱く衝動)に溺れていたと結論づけた。 彼は野心的で、傲慢で、成功していたが、その代償は大きかった。 若き英雄の神話を生きることは、もはや彼には向いていない。その過程で自分の道を捨て、魂を失ってしまったのだから。 フロイトの後継者(フロイト派が「金髪のジークフリート」と呼んでいた)になったことで、彼は父親(北欧神話ではジークフリートの父親は「シグムンド」と呼ばれている)に食い殺されることを許してしまったのである。 彼は自分の信念や考えを犠牲にし、その過程で非人間的で無感情なものになっていたのです(ジークフリートは英雄的な旅の中で、魂の伴侶であるブリュンヒルデを忘れてしまった恐れを知らない戦士であることを付け加えておきます)。 ビジョンは、若いヒーローの原型で自我を膨らませていた彼に、これを止めなければならないと告げていたのです。つまり、自分の中の若いヒーローを殺し、それによって生きていくための新しい神話が生まれると告げていたのです(スカラベは伝統的に再生の象徴とされています)(Walker, p.68)。 ユングは、もしこれらのビジョンを理解していなかったら、文字通りに行動したくなっていたかもしれないと感じていました(ナイトテーブルの引き出しにあったリボルバー)。 このビジョンを見た直後、フェルディナント大公が暗殺され、第一次世界大戦が勃発しました。 彼の個人的な危機と、ヨーロッパを覆っている集団的な危機との間にパラレルな関係があることを、ユングは見逃しませんでした。 意味のある偶然の一致(シンクロニシティ)は、原型が活性化されたことを示唆し、ヨーロッパもまた、人格全体として若い英雄の原型で膨れ上がっており、その過程で同様に人間性と魂を失っていることを示していました(p.68)。 このインフレを理解することができず、ヨーロッパは、大公の殺害や、ナショナリズムの英雄的な理想を抱いて戦場に送り出された何百万人もの若者たちによって、大規模にそれを実行した。
ユングは、このような英雄主義の悲劇的な帰結として、魂の喪失を認識していました。 ユングにとって「魂」という言葉にはさまざまな意味がありますが、「赤い本」の文脈では、特にアニマの原型を指しているように思われます。アニマとは、男性の夢や家父長制文化の神話において、女性の姿として典型的に現れる関係性と感情の原型です(Walker, p.47)。 関係と感情の能力が成熟している場合、アニマは精神的なガイドとして夢や神話に現れます(アリアドネ、ベアトリーチェ、聖母マリア)。 その能力が未発達で未熟な場合、アニマはファム・ファタール、魔女、誘惑者などとして現れる。ローレライ、セイレーン、メデア、カリプソなど)(p.47-50)。 古代文化における英雄神話は、若い英雄が人間性や人間関係を犠牲にして自分の能力を高めすぎたことによる悲劇的な結果を捉えているようです。ジェイソンはメデアを捨て、テセウスはアリアドネを捨て、エネアスはディドを捨てます。 ユングの場合は、人生の前半を直観や思考の機能の開発に費やし、感情や感覚の機能は放置されたままでした。 この頃から結婚生活に問題が生じ、トニ・ウォルフとの不倫関係が始まったのも当然といえば当然かもしれません。 ユングは後に、人生の後半戦における男性の主な課題は、精神の無視された側面、特にアニマを統合し、発展させることであると理論化します。 それゆえ、「赤い本」のメインテーマは「魂の再発見」、あるいはユングの別の作品のタイトルにもあるように、「魂を求める現代人」となっています。もちろん、これには女性が個性化の過程で遭遇する性別に反した課題は含まれていません。
ユング自身のアニマは、サロメという人物と、単に「私の魂」と名付けられた人物の形で『赤い本』に登場します(この2つの人物は入れ替え可能なようで、ユングはサロメについて「...彼女は私自身の魂です...」と直接語っています。(p. 248). ヘロデのために踊り、彼を誘惑して洗礼者ヨハネの首をはねさせた新約聖書の人物をモデルにしたユングのサロメは、信頼に足るものではありません。 聖書の人物とは異なり、ユングのサロメは目が見えず(おそらく彼女の成長のなさのもう一つの表れでしょう)、ユングに愛されることを切望しています。 彼女は感情と感覚の体現者であり、ユングの関心と愛情を求めています。 彼女が登場する直前、ユングは次のように述べています。「考える人の情熱は悪く、したがって喜びもありません...感じることよりも考えることを好む人は、自分の感情を暗闇の中で腐らせてしまいます。 感じることよりも考えることを好む人は、自分の感情を暗闇の中で腐らせる。それは熟すことなく、型にはまって光に届かない病んだ蔓を作り出す」(p.248)。 サロメは、ユングのビジョンに登場する賢者の老人、フィレモンの娘でもあり、終始彼に依存し、彼に従属しています。
Reflecting on his life and career to this point, he concluded that he had been inflated with the hero archetype (a universal unconscious impulse or instinct that takes on a particular form—in this case, the impulse that all cultures feel to create a superhuman individual, a hero). He had been ambitious, arrogant, successful, but at a price. Living the myth of the young hero no longer suited him, for he had given away his own path in the process and had lost his soul. In becoming Freud’s heir apparent (the “blond Siegfried” as the Freudians called him), he had allowed himself to be devoured by the father (in Norse myth, Siegfried’s father is named “Sigmund”). He had sacrificed his own convictions and ideas and had become something inhuman and unfeeling in the process (we might add that Siegfried is a warrior without fear who forgets his soul mate Brunhilde in his heroic journey). The visions were telling him that his ego had been inflated with the archetype of the young hero and that this had to stop—i.e., that he must kill the young hero in himself and that this would give rise to a new myth to live by (the scarab is a traditional symbol of rebirth) (Walker, p. 68). Jung felt that if he hadn’t come to an understanding of these visions, he might have been tempted to act them out literally (the revolver in the night table drawer). Soon after he had these visions, Archduke Ferdinand was assassinated, igniting WWI. The parallel between his personal crisis and the collective crisis overtaking Europe was not lost on Jung. The meaningful coincidence (synchronicity) suggested to him that an archetype had been activated and that Europe, as a personality writ large, was also inflated with the archetype of the young hero and had similarly lost its humanity and soul in the process (p. 68). Unable to understand this inflation, it acted it out on a mass scale with the murder of the Archduke as well as millions of young men sent off to battle filled with the heroic ideals of nationalism.
The tragic consequence of such hero inflation, Jung realized, was a loss of soul. For Jung, the word “soul” has many meanings, but in the context of The Red Book, it seems to refer specifically to the archetype of the anima—the archetype of relationship and feeling that typically manifests in a man’s dreams, as well as in a patriarchal culture’s myths, as a female figure (Walker, p. 47). When the capacity for relationship and feeling is mature, the anima appears in dream and myth as a spiritual guide (Ariadne, Beatrice, the Virgin Mary). When that capacity is undeveloped and immature, the anima appears as a femme fatale, a witch, a seductress, etc. (Lorelei, Siren, Medea, Calypso, et al.) (p. 47-50). Hero myths in ancient cultures seem to capture the tragic consequences of the young hero’s over-development of his abilities at the expense of his humanity and relationships—after they begin to accumulate heroic deeds and reputation, Jason abandons Medea, Theseus abandons Ariadne, Aeneas abandons Dido. In Jung’s particular case, he had spent the first half of his life developing the functions of intuition and thinking, leaving those of feeling and sensation neglected and undeveloped. It is perhaps no surprise that he began having marital problems at this time and began his affair with Toni Wolff, perhaps an attempt to re-claim the soul he had lost in his heroic career thus far. Jung would theorize later on that a primary challenge for men in the second half of life is to integrate and develop neglected aspects of the psyche, especially the anima. Hence, the main theme of The Red Book is “the Re-Finding of the Soul” or, as the title of another work by Jung, “Modern Man in Search of a Soul.” This, of course, leaves out the contra- gendered challenges encountered by women during individuation.
Jung’s own anima appears in The Red Book in the form of the figure named Salome as well as that named simply “my soul” (the two figures appear to be interchangeable and Jung says directly of Salome, “…she is my own soul…” (p. 248). Based on the New Testament figure who danced for Herod and seduced him into beheading John the Baptist, Jung’s Salome is anything but trustworthy. Unlike the biblical character, Jung’s version is blind (perhaps another sign of her lack of development) and desperately wants Jung to love her. She is the embodiment of feeling and sensation, begging for Jung’s attention and affection. Just prior to her appearance, Jung notes that “The thinker’s passions are bad, therefore he has no pleasure…He who prefers to think than to feel, leaves his feeling to rot in darkness. It does not grow ripe, but in moldiness produces sick tendrils that do not reach the light” (p. 248). Salome is also the daughter of Philemon, the wise old man of Jung’s visions, dependent upon him and subordinate to him throughout.
先に述べたように、フィレモンは「赤い本」全体を通してユングの典型的な賢者であり、ガイドであり、以前はイライジャという名前で登場していました。 フロイトや他の年配の男性指導者がいない中で、フィレモンはユングにとって「幽霊のような指導者」の役割を果たしていました。 ダンテにとってのヴァージルのように、フィレモンは「赤の本」の地下世界を案内する役割を果たしており、ユングはフィレモンがある出会いの裏で働いていることを発見したのです。 ユングのフィレモンは、オヴィッドの「バウシスとフィレモン」という物語をベースにしています。この物語では、老夫婦が、人間に扮して村人を訪問し、ゼニア(古代ギリシャで重んじられた神聖な客と宿主の関係)の能力を試しているジュピターとマーキュリーに対して、適切な敬意ともてなしを行います。 その報酬として、二人は神々の怒りである大洪水による隣人の全滅を免れます。 神々は、二人の信心深さを称えて二人の家を神殿に変え、二人のたった一つの願いである「同時に死ぬこと」を許します。 彼らが死んだ後、神々は彼らを木に変え、枝や幹が交錯して一緒に成長するようにします。 ユングはゲーテの「ファウスト」第2部での夫婦の描写にも大きな影響を受けています。ここでは、ファウストの建設・開発プロジェクトのために老夫婦が引っ越しを拒否し、メフィストがファウストの知らないところで彼らを殺害してしまいます(この行為はファウストに多大な罪悪感を抱かせ、彼の魂の救済にも一役買っています)。
不思議なことに、ユングは幻影の中のフィレモンを翻案する際、バウシスを完全に省き、彼らの物語の特徴である夫婦の親密さ、貞節さ、愛を描かないようにしている(Schwartz-Salant, p.26)。 その代わりに、フィレモンは盲目のサロメの父親兼被後見人となり、『赤い本』の最後でユングに「信用するな」と言うことになります。 ユングは自分のアニマの未熟さに気づき、アニマを擬人化して対話し、アニマの統合に向けて大きく前進したように見えますが(アニマを愛していると告白し、アニマとの交流によってサロメの視力が回復します)、『赤い本』の最後では、アニマとの関係を深めることができなかったようです。 このように「赤い本」には、ユングが自分の魂を完全に信頼して愛することができず、それによって自分の人格の未熟な部分を完全に発展させることができなかったという、未完成の要素、さらには悲劇の要素があります。
しかし、ユングが失った魂を取り戻し、自分の未熟な感情や人間関係の能力を発展させていく過程は、『赤い本』の他のいくつかの主要なエピソードで劇的に展開されています。 赤い本」の第2部である「Liber Secundus」では、文章が明るくコミカルな新しいトーンになっています。 冒頭のエピソード「森の城」では、ユングは中世の城の中で、厳粛で真面目な塔の番人としての自分を思い描き、赤い騎士が近づいてくるのを見つけます。 赤い騎士は自分の前に現れ、ユングと言葉を交わして馬上槍試合を始めます。 キリスト教とユダヤ教の長所と短所を議論し、ユングはついに彼を悪魔と呼んでしまいます。 しかし騎士は、自分は本当は喜びの擬人化であると主張します。 騎士は、人は人生を通じて踊ることを学ぶべきだと主張しますが、ユングは、踊りは交尾や古い習慣を再現するためのものに過ぎないと言い切ります。 ユングは、ダンスとは根本的には欲望と狂気の表現でしかないと主張します。 喜びのために踊ることもあると、赤の騎士はあざ笑うような真剣な口調で反論します。 すると突然、ユングの服が葉っぱになってしまいました。
このエピソードに続く分析の中で、ユングは悪魔には内面的なリアリティと意味があることを指摘しています。 悪魔は宗教の厳粛さを批判しますが、彼と宗教について話し合うことで、ユングは悪魔と理解を深めます。すなわち、喜びは単なる狂気や欲望の症状ではなく、人生の表現であり、踊る正当な理由であるということです。 ユングは、この悪魔と踊ることで、自分の劣等感側の統合と発展を続けていることに気づきます。今回のエピソードでは、赤の騎士に代表されるように、堅苦しいユングが自分の過剰に発達した思考側を表しており、あるいは、塔の上にいるプエラエテルヌスの夢の自我に擬人化された未発達の理想主義的な感情側を表しています(Beebe, p. 50)。
Philemon, as noted earlier, is Jung’s archetypal wise old man and guide throughout The Red Book, appearing earlier under the name Elijah. In the absence of Freud or any other older male mentor, Philemon served as a “ghostly guru” to Jung. Like Virgil for Dante, Philemon serves as a guide through the underworld of The Red Book as Jung finds him to be at work behind the scenes helping him through certain encounters. Jung’s Philemon is based, in part, on Ovid’s tale “Baucis and Philemon,” in which the old couple show appropriate reverence and hospitality to Jupiter and Mercury who, disguised as mortals, are visiting and testing the villagers in their capacity for Xenia (the sacred guest-host relationship valued among the ancient Greeks). As a reward, the couple is spared the wrath of the gods in the form of a great flood that destroys all of their neighbors. The gods transform their home into a temple in honor of their piety and grant them their one wish, which is to die together at the same time. After they pass away, the gods honor them by transforming them into trees, which interlace branches and trunks as they grow together. Jung was also heavily influenced by Goethe’s rendering of the couple in his Faust, Part Two. Here, the old couple refuse to move to make way for Faust’s construction and development project, and Mephistopheles ends up murdering them without Faust’s knowledge or approval (an act that induces tremendous guilt in Faust and that plays a part in the redemption of his soul).
Curiously, in his adaptation of Philemon in his visions, Jung completely omits Baucis, and opts not to draw upon the defining characteristic of their story—i.e., their marital intimacy, fidelity and love (Schwartz-Salant, p. 26). Instead, Philemon is made the father and ward of the blind Salome, whom he ends up telling Jung not to trust toward the end of The Red Book. Though Jung seems to have made great strides in realizing the immature state of his anima, in personifying her and opening up a dialog with her, and even in making some progress toward her integration (he does confess to loving her and his interaction with her leads to the restoring of her sight), by the end of The Red Book he seems unable to have gone further with her. Hence, The Red Book has an element of incompletion, even tragedy—of Jung’s inability to completely trust and love his soul and thereby develop fully this immature part of his personality.
Nevertheless, the progress that Jung does make in reclaiming lost soul and developing his immature capacity for feeling and relationship plays out dramatically in several other of the major episodes of The Red Book. In Liber Secundus, the second part of The Red Book, the writing takes on a new tone—light and comic. In the opening episode, “The Castle in the Forest,” Jung envisions himself in a medieval castle as a solemn, serious tower guard who spies a red knight approaching. The red knight presents himself, and he and Jung begin to verbally joust. They debate the virtues and shortcomings of Christianity and Judaism and Jung eventually calls him the devil. But the knight insists that he is really, in fact, a personification of Joy. He argues that one should learn to dance through life, and Jung stuffily replies that dancing is really just for mating or to re-enact antiquated customs. At its root, Jung asserts, dancing is nothing more than an expression of lust and madness. In a mock serious tone, the red knight counters that one can also dance for joy. Suddenly, Jung’s clothes burst into leaves!
In the analysis following this episode, Jung notes that the devil has an inner reality and meaning. The devil criticizes religion for its solemnity, but by discussing religion with him, Jung reaches an understanding with the devil—namely, that Joy is not merely a symptom of madness or lust, but an expression of life and a legitimate reason for dancing. Jung realizes that in dancing with this devil, he is continuing his integration and development of his inferior feeling side—this time, represented by the Red Knight with the stuffy Jung in the episode representing his overdeveloped thinking side, or, perhaps, his undeveloped, idealistic feeling side personified in his puer-aeternus dream ego, high up in the tower (Beebe, p. 50).
最新の画像[もっと見る]
-
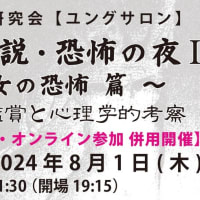 ユング心理学研究会
5ヶ月前
ユング心理学研究会
5ヶ月前
-
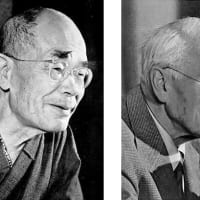 ユング心理学研究会
5ヶ月前
ユング心理学研究会
5ヶ月前
-
 ユング心理学研究会
5ヶ月前
ユング心理学研究会
5ヶ月前
-
 街録ch沖縄トークライブ!【那覇市/2024年7月28日】
6ヶ月前
街録ch沖縄トークライブ!【那覇市/2024年7月28日】
6ヶ月前
-
 「汝自身を知る」とは「ダイモンを知る」ことを意味します。
8ヶ月前
「汝自身を知る」とは「ダイモンを知る」ことを意味します。
8ヶ月前
-
 ユング心理学研究会
8ヶ月前
ユング心理学研究会
8ヶ月前
-
 バーバラ・ハンナ: 全体性を目指して努力する。
8ヶ月前
バーバラ・ハンナ: 全体性を目指して努力する。
8ヶ月前
-
 【プロが教える】たった1分でネット速度を快適にする裏技を紹介!【超便利】
8ヶ月前
【プロが教える】たった1分でネット速度を快適にする裏技を紹介!【超便利】
8ヶ月前
-
 マーク・ザッカーバーグ/AI ニュース
8ヶ月前
マーク・ザッカーバーグ/AI ニュース
8ヶ月前
-
 バーバラ・ハンナ: 全体性を目指して努力する。
8ヶ月前
バーバラ・ハンナ: 全体性を目指して努力する。
8ヶ月前









