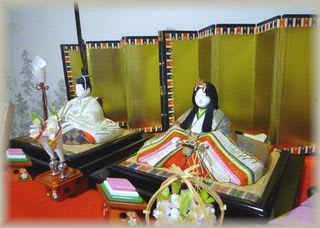ラジオで聞きました。
38才、よく頑張りました。
私を毎冬、わくわくさせてくれていました。
神戸製鋼ラグビー部の元木由記雄選手が引退だそうです。
やはりセンターとしてはピカイチだったと思います。
ラグビーの名門、大阪工大高で優勝し、明大でも大学選手権を3度の優勝。
明治の「前へ」の精神そのもので、たて突破が小気味良かったです。
神戸製鋼では、入社時より優勝し続け、7連覇を果たしました。
日本代表として歴代最多のテストマッチ通算79キャップ。
一方、神鋼ラグビー部では選手兼コーチだったスクラムハーフの苑田がヘッドコーチに昇格だそうで…。
平尾総監督自身は先月の日本選手権で敗退した後に退任を示唆していたそうですね。
平尾と元木、それぞれ「ミスターラグビー」と言われていました。
また時代が変わっていくようで、私も年をとるはずです。
38才、よく頑張りました。
私を毎冬、わくわくさせてくれていました。
神戸製鋼ラグビー部の元木由記雄選手が引退だそうです。
やはりセンターとしてはピカイチだったと思います。
ラグビーの名門、大阪工大高で優勝し、明大でも大学選手権を3度の優勝。
明治の「前へ」の精神そのもので、たて突破が小気味良かったです。
神戸製鋼では、入社時より優勝し続け、7連覇を果たしました。
日本代表として歴代最多のテストマッチ通算79キャップ。
一方、神鋼ラグビー部では選手兼コーチだったスクラムハーフの苑田がヘッドコーチに昇格だそうで…。
平尾総監督自身は先月の日本選手権で敗退した後に退任を示唆していたそうですね。
平尾と元木、それぞれ「ミスターラグビー」と言われていました。
また時代が変わっていくようで、私も年をとるはずです。