
今や音楽シーンのメイン的な場所にヒップホップはあり、ラップはその重要な要素。
ウィキによれば、日本でもラップの要素は、様々なJポップに取り入れられている。
ヒップホップのルーツは、1970年代にニューヨークのブロンクス地区で行われたブロックパーディにあると言われており、黒人文化だったらしい。
それが1980年代になり、DJ、ブレイクダンスなどを含めた要素が含まれていき、浸透していったようだ。
で、その後人気も出ていった。
今じゃ音楽シーンでは欠かせないジャンルになっている。
それは日本の音楽シーンでもそう。
ヒップホップの要素の1つにラップがあるのだとしたら、ヒップホップというジャンルがまだ日本になかったころ、ラップという音楽要素は日本ではどうだったのだろう。
まったくそれに該当したり、それに繋がる音楽はなかったのだろうか。
ざっと調べてみたところ、日本では全くなかったわけでもなさそうだ。
よく言われてるのが、吉幾三さんが1984年に発表した「俺ら東京さ行くだ」が日本語ラップの元祖という説。
でもさらに調べてみたら、ネット上には1980年にドリフターズが、1981年にはスネークマンショーやYMOが、さらに1982年にはザ・ナンバーワンバンドが。そして吉幾三さんと同じ1984年には佐野元春さんがラップ系の曲をやっている。
でもそれらは、あくまでアメリカでラップ系の曲があって、それが新鮮で、人気も出てきていたから、その影響もあったのかもしれない。
では、アメリカでまだラップという音楽がなかった時代は、日本では後のラップに繋がるような音楽要素は皆無だったのだろうか。
具体的に言うと、1960年代以前の日本の音楽シーンで。
そこで更に遡って調べてみると、後の時代にラップに繋がるような要素を持った音楽もあったように思えてきた。
例えば、これなどいかがであろうか。
川上音二郎のオッペケペー節である。
これぞ、まさに日本語ラップの源流かもしれない?
まあ、異論はあるとは思うけどね。でも、よく聴くと、それっぽくも聞こえるから不思議。
でも、これってアメリカでヒップホップジャンルが生まれるはるか以前の曲なのだ。アメリカでヒップホップ音楽が生まれる前に、すでに日本では、将来それに繋がるような要素の音楽があったのかもしれない・・・そう考えると、ちょっと痛快。ある意味、誇らしくもある??
さらにこの曲を、現代のラップサウンド調に変換した動画も見つけた。
デンボを速めてラップサウンドに乗せてみている。
なるほどなあ。これ、面白い。こうすると、確かにしっかりラップになってしまっている。
これを今の日本のヒップホップアーティストがカバーしたら、こんな感じになるのかな?
まだそんな人はいないけど。
















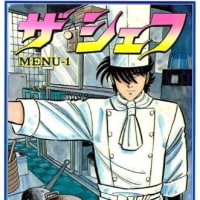











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます