
日本で漫画というものが登場したのはいつか。それには色んな見方があり、一概には決めつけられない。
ただ言えるのは、漫画(コミック)が今の隆盛を迎えるまでに、無数の作品が現れ、あまりにも多くの作品が消えてゆき、ほんの一部の名作だけが語り継がれてきている・・ということ。
ならば、消えていった・・というか、今では少なくてもあまり知られていない作品は、どれも駄作か?というと、それは違う。
今ではあまり知られていなかったり、埋もれかけている作品の中にも、名作と呼べる作品は多数ある。
中には、作品名や作者の名前は知られていても、今の世の中にあっては、案外実際にはあまり読まれていない・・・そんな作品もけっこうあるはず。
「私の漫画遺産」というシリーズタイトルで、今後そういう作品を不定期に取り上げていきたいと思う。
基本は、我が家にある作品で。
今回取りあげる「のら犬の丘」は、間違いなく名作である。
熱血系の少年漫画がお好きな方なら、一度この作品を読み始めたら最後、やめられなくなって、たとえ寝る時間が遅くなっても一気に読み干してしまい、翌日の仕事に影響がでてしまうかもしれない。なので、読み始めるなら、夜読み始めるのはお勧めしない。
この作品から受けた影響は、私にとって計りしれない。私にとって、愛してやまない作品である。
巷では、この作品は「もうひとつの、あしたのジョー」と言われているらしい。それは主人公が不良で、入った少年院でボクシングにめざめ、また少年院では永遠の友とも知りあう・・・・という点などが共通しているからであろう。
この作品を初めて読んでた頃、私は漫画家志望であった。自分なりのオリジナル漫画を、級友に頼まれて何種類も描いていた。
画風・・・という意味で、私が影響を受けた漫画家は「巨人の星」の川崎のぼる先生、「サインはV」の望月あきら先生、「ゲゲゲの鬼太郎」の水木しげる先生などその他にも色々あったが、特に自分に染み込んだ作風や画風は、SFヒーローものの「サイボーグ009」の石ノ森章太郎先生と、熱血ものの「のら犬の丘」の石井いさみ先生であった。
熱血系漫画を描く時は、「のら犬の丘」が私のバイブルであり、基準であった。
特に後半の絵柄は。この作品は、私は後半になるにつれ、その登場人物の絵柄が好きになったいったから。
そのせいか、当時描いたオリジナル熱血漫画を誰かに見せた時、「石井いさみの絵柄に似てるね」なんて言われたりした。
キャラやストーリーも好きだったが、「のら犬の丘」では、作品に出てくる自然風景の描き方も好きだった。
自然風景の絵は元々私は好きだったのだが、私が自然描写の画風が好きだった漫画家は何人もいた。
水木しげる先生やつげ義春先生の、陰影を強調したリアルな自然風景の緻密な画風。
白土三平先生の、品があって、動きも感じられて、流れるような風景描写。
それと並んで、私にとっては石井いさみ先生の「のら犬の丘」での、スッキリして分かりやすいスマートな自然風景も。
これらが特に私のお気に入りの「自然風景」だった。はっきり言って、よくマネした(笑)。
「のら犬の丘」の中で描かれる風景は、例えば水木作品やつげ作品や白土作品に比べると、少なめだし、それを「売り」にしている印象はあまりない。だが、たまに出てくる風景の描き方が私は好きだった。
キャラの魅力、自然風景の描き方、そして熱い熱血友情ストーリー。それが私にとっての「のら犬の丘」の魅力であった。
キャラはよく立っていた。
主人公・団虎太。その親友・剣持次郎。
虎太にボクシングを教えた桜庭先生。桜庭先生のライバル、羽黒先生。
のちに虎太の仲間になる大塩。
このへんのキャラは特に魅力的だった。
中でも、剣持のかっこよさは格別だった。そして、虎太との友情には、胸が熱くなるものがあった。
この作品に出てくるキャラの人気投票がもしもあったなら、剣持が人気ナンバー1かもしれない。少なくても主役の団虎太に勝るとも劣らない魅力があった。
話によると、石井先生にとっては、この作品に出てくる団虎太というキャラは、その後先生が「男」を描く時の基準になったそうだ。それほど、石井先生にとっても大きな作品になったのだろう。
石井いさみ先生の作品というと、長く連載された「750ライダー」が代表作として認識されてる場合が多いようだが、「750ライダー」は、連載開始当時はともかく、途中から絵柄も物語も大きく変化していった感がある。
なんていうか、・・私の勝手な思い込みかもしれないが、ほのぼのとした、やわらかで穏やかな作品になっていった気がする。
まあ、長く連載が続いたということは、それだけ読者の支持があった証明なのであろうが、「のら犬の丘」をこよなく愛していた私としては、「750ライダー」の途中からの作風には、どうもハマれなかった覚えがあった。絵柄も物語も。
「のら犬の丘」の熱さに比べると、どうも肩透かしをくらっているような気がしていた。
「のら犬の丘」の熱さを期待して読むと、少し物足りなかった。
まあ、石井先生としては、「750ライダー」は新境地だったのだろう。それによって新たに獲得したファンも多かったことだろう。
「のら犬の丘」にハマった私は、その後何作かの石井いさみ先生の作品を買って読んだ。
「モーレツ!巨人」「野獣の弟」その他。
この辺の作品の中には、石井先生の作品群の中では、忘れられがちな作品もあり、今では復刻もされてなかったりする作品もある。正直、ストーリー的には「のら犬の丘」には及ばないのだが、ただ、「のら犬の丘」での画風は健在であり、その絵柄を楽しめるというだけでも、私には価値があった。
「のら犬の丘」は、当時の石井先生の画風プラス、熱い物語。私にとって、その最高の要素の頂点だったと思う。
この作品には原作者がいる。
原作者は、真樹日佐夫さん。
そう、あの梶原一騎先生の弟さんだ。作風はお兄さん同様、硬派で男っぽい。
お兄さんがあまりにも有名すぎるが、どっこい真樹日佐夫先生も漫画原作者としてかなり活躍された方である。
梶原一騎先生を兄にもつ真樹日佐夫先生は、お兄さんゆずりの男っぽく熱い原作で、石井いさみ先生と組み、こんな最高の作品を生み出したのだ。
聞けば、石井先生は、梶原一騎先生が「新・巨人の星」を描く時、作画を担当してほしいというオファーがあったらしい。だが、そのオファーは断ったそうだ。
弟である真樹日佐夫先生が石井先生と組むことで生みだした「のら犬の丘」という作品の出来栄えを、編集者も梶原先生もすごく買っていたのではないだろうか。
じゃなかったら、梶原先生にとっての代表作である「巨人の星」の続編の作画というとんでもない大役を、石井先生にふるはずはないと思う。
そう、きっと「のら犬の丘」は、あの梶原先生をもうならせたのだと私には思えてならない。画風といい、内容といい、物語といい。
で、実際にそれほどの名作であったということは、この作品を読んでもらえれば、おわかりいただけると思う。
石井いさみ先生の作品には、「くたばれ!涙くん」や「750ライダー」などの名作・代表作もあるけど、私にとっては、なんといっても「のら犬の丘」なのだ。
石井いさみ先生の魅力は、これに凝縮されている・・・と言いたいぐらい。
この作品が映像化されなかったのが、私には不思議な気がする。
今も。
埋もれているのがもったいない作品。
「のら犬の丘」。珠玉の名作。団虎太と剣持次郎の友情には、きっと・・・魂をゆさぶられることだろう。
いつかまた・・この二人に、会いたいものだ。





















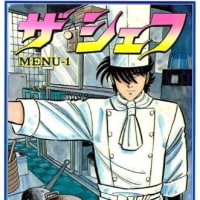






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます