紀勢本線の和歌山~新宮まで電化されたのが昭和53年10月なのですが、それ以前は気動車による運転が行われていました。

昭和49年 時刻表から
現在の様に、和歌山~御坊 御坊~田辺・・・と言った細切れではなく、気動車列車でも和歌山市発串本行きとか、周参見行きと言った普通列車が走っていました。

和歌山市発周参見行き
当時は、キハ17やキハ20、時々キハ45が連結されているとラッキーみたいな感じでした、他にもキロ26を格下げしたキハ26-400番台も運用に入っており、これが普通列車に入っていると得した気分になったものです。

昭和52年の時刻表 串本行きが新宮行きに変更されています。
まさか、キハ35で新宮まで行ったとは思いたくないのですが・・・。
さて、そんな紀勢本線もとある時期から大変なことになります。
それは、関西本線の湊町~奈良間が電化されて113系・103系による電車運転が始まると、今まで関西線の主力として活躍していたキハ35が大量に余剰となりその煽りで。和歌山機関区にはキハ35が大挙してやってくることになりました。
国鉄時代の気動車は特急形以外は基本的に自由に連結できましたので、キハ35系×4連というのが多くなりました。

まれに検査の関係などで、一部のキハ35が45に置換えられていたりすると45だけが満席になるなんてこともありました。
その後、紀勢本線が電化されると運転区間は和歌山から紀伊田辺・紀伊田辺~新宮間で運転区間が分離され、和歌山~紀伊田辺間は直通快速を基本に6連、紀伊田辺~新宮間は4連が投入されました。
その後、紀伊田辺~新宮間は165系3連、更に105系2連に変更されているのはご存じのとおりです。
余談ですが、JR西になってから天王寺発20:20が五条・田辺行だったのですが、当初は113系だったのに、阪和線内の混雑が激しいとして103系に置換えられた時期がありましたが、トイレも無い103系で紀伊田辺はいくら何でも酷いですよね。
取材・講演などお待ちしております。
国鉄があった時代のお問合せフォームからお願いいたします。
http://jnrera3.webcrow.jp/contact.html

昭和49年 時刻表から
現在の様に、和歌山~御坊 御坊~田辺・・・と言った細切れではなく、気動車列車でも和歌山市発串本行きとか、周参見行きと言った普通列車が走っていました。

和歌山市発周参見行き
当時は、キハ17やキハ20、時々キハ45が連結されているとラッキーみたいな感じでした、他にもキロ26を格下げしたキハ26-400番台も運用に入っており、これが普通列車に入っていると得した気分になったものです。

昭和52年の時刻表 串本行きが新宮行きに変更されています。
まさか、キハ35で新宮まで行ったとは思いたくないのですが・・・。
さて、そんな紀勢本線もとある時期から大変なことになります。
それは、関西本線の湊町~奈良間が電化されて113系・103系による電車運転が始まると、今まで関西線の主力として活躍していたキハ35が大量に余剰となりその煽りで。和歌山機関区にはキハ35が大挙してやってくることになりました。
国鉄時代の気動車は特急形以外は基本的に自由に連結できましたので、キハ35系×4連というのが多くなりました。

まれに検査の関係などで、一部のキハ35が45に置換えられていたりすると45だけが満席になるなんてこともありました。
その後、紀勢本線が電化されると運転区間は和歌山から紀伊田辺・紀伊田辺~新宮間で運転区間が分離され、和歌山~紀伊田辺間は直通快速を基本に6連、紀伊田辺~新宮間は4連が投入されました。
その後、紀伊田辺~新宮間は165系3連、更に105系2連に変更されているのはご存じのとおりです。
余談ですが、JR西になってから天王寺発20:20が五条・田辺行だったのですが、当初は113系だったのに、阪和線内の混雑が激しいとして103系に置換えられた時期がありましたが、トイレも無い103系で紀伊田辺はいくら何でも酷いですよね。
取材・講演などお待ちしております。
国鉄があった時代のお問合せフォームからお願いいたします。
http://jnrera3.webcrow.jp/contact.html










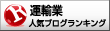
















キハ35が、紀勢本線にやって来たのは、覚えています。
それまでは、客車や早朝なんかは一部急行気動車を運用していました。それが、客車は夜行含む僅か3往復に減らされ、殆どキハ35、酷いときは昼間の和歌山発紀伊田辺行で2両編成もありました。
電化前の悲惨な時期でした。今のJR西日本と同じく特急、急行へ乗れと言われんばかりのダイヤ、運用でした。
その後、新宮電化で待望の電車が走り始め一部冷房とスピードアップで特急、急行の利用客が普通電車に流れて行きました。
その経緯もあり今の、特急へ乗れと、わざと遅く、分断した表向き合理的なダイヤを組んいるのか阪和、紀勢本線の快速、普通電車は不便です。
最後に、画像、周参見行のキハ35は確か紀伊田辺に夕方着き先頭はキハユニの2枚窓だったと思います。夕刊とか業務用書類を主要駅に下ろしていました。このスジは電化後も引き継がれ天王寺14:20発、快速紀伊田辺行のクハ111がその任を務めていました。
当時はいつ見ても、キハ35が組み込まれていて、キハ17が居なくなったかわりに、キハ26-400番台なども一緒に一掃されてしまい。ちょっと寂しい気分にされたものでした。
国鉄にしてみれば、昭和53年に電化を控えていることもあのよううな配転になったのかもしれませんね。
>周参見行のキハ35は確か紀伊田辺に夕方着き先頭はキハユニの2枚窓だったと思います。
仰る通りです、きのくにの先頭に連結されて、和歌山駅で解結・和歌山市から来た周参見行きの先頭に連結されて下っていきました。
電化前後の紀勢線の模様も家族旅行で、ちょくちょく行ったので良く覚えています。奈良電化前は湊町ー名古屋のキハ35運用もあったといいますから、とかく、天鉄管内はひどい車両が多かったですね。
昼の12時頃にキハ30の単行が熊野まで往復してました。
ゆっくりした速度で走ってる姿を見に よく熊野市行きに乗って 途中の有井で折りて、熊野市から折り返してくるキハ30を見に行きました。
あの頃に走ってたタラコのキハ30も、今は廃車・解体されたと思います。鉄道模型のキハ30首都圏色を、昔を思い出しながらよく走らせてます。
コメントありがとうございます。
キハ35が、昭和55年頃は新宮付近で走っていたのですね。
外釣りドアは隙間風も酷くて、温暖新宮付近でも冬場は寒かったのではないでしょうか。
紀勢本線について検索していまして、こちらの記事を拝見させて頂きました。
今とは列車に求めるものが大きく違ったのだろうと思いますが、キハ30形への拒否感には強いものがあったのですね。新車で投入された訳でもなく、期待感を持てるような車両ではなかったということなのでしょうか。
直流電化され、特急列車も走るようになって以降も、105系が長く活躍しているあたりは、この路線の普通列車のあり方は長年大きくは変わっていないということなのだろうと思います。
和歌山から先、車窓に映る景色の変化を楽しみに、またいつか紀勢本線の旅にも出かけたくなります。
風旅記: https://kazetabiki.blog.fc2.com