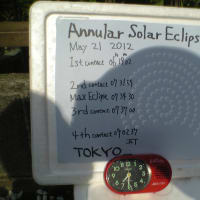はじめに
序章 資産形成を終えた人に
第1章 「資産活用」世代の実態
第2章 リタイアメント・インカムとは?
第3章 「毎月10万円の引き出し」はなぜキケンなのか?
第4章 引き出しは「率」で考える
第5章 保有する資産全体のなかで取り崩しを考える
第6章 資産活用層は新NISAをどう使う?
第7章 生活スタイルと資産活用
第8章 資産活用層の社会貢献
おわりに
山一で社員持株会で、という往復ビンタを克服した著者!
60代からの資産「使い切り」法―今ある資産の寿命を伸ばす賢い「取り崩し」の技術
担当編集が語る
私の心情(199)―資産活用アドバイス80-60代からの資産使い切り法 | 合同会社フィンウェル研究所
老後資金の取り崩し…「定額」よりも「定率」のほうが圧倒的におすすめな理由 - 記事詳細|Infoseekニュース
収益率配列のリスク
これがね、こういう説明もあるのでね。収益率配列のリスク |アムンディ・ジャパン
私の心情(202)―資産活用アドバイス82-説明が難しい収益率配列のリスク | 合同会社フィンウェル研究所
たしかに「説明が難しい」わけでね。
使っている用語が一般人になじみが薄いよね。
「(運用)成績が変動する中でどう引き出すのが良いのか」だよね。
同じようなパターンで引き出して(取り崩して)いっても、変動のパターン(成績の現れる順番)によっても結果がけっこう違ってくるというのをどう短くするか?
そういえば、最近知ったのだが、「銀行ジェロントロジスト」なる資格があるのだそうで。
金融業務3級 シニア対応銀行実務コース -銀行ジェロントロジスト認定試験- | CBT-Solutions CBT/PBT試験 受験者ポータルサイト
似た名前が乱立?
よくわからん。
年寄客対応の年寄行員?
金融ジェロントロジーとは?高齢者の資産を適切に管理・運用する学問のポイント