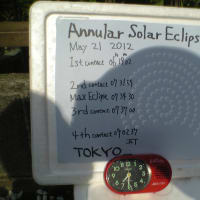『英国空軍少将の見た日本占領と朝鮮戦争―少将夫人レィディ・バウチャー編』
原書名:SPITFIRES IN JAPAN FROM FARNBOROUGH TO THE FAR EAST
(Bouchier,Sir Cecil)バウチャー,サー・セシル【著】
加藤 恭子 今井 萬亀子【訳】
社会評論社 (2008/12/25 出版)
加藤恭子のノンフィクションの書き方講座
ファーンボロは、英国の航空機開発拠点で、著者が若い頃にテストパイロットとして飛んでいた。航空ショーで有名。
wiki/Royal_Aircraft_Establishment
wiki/Cecil_Bouchier
インド空軍が19331932年(=植民地時代)にインド人パイロット5人で発足した時の指揮官でもあった。
英領インドは、その後パキスタンと別れたので、インド、パキスタン両空軍の父である由。
<1933を1932に訂正>
81周年の記事を見て気付く。1932年が正当だった。
IAF celebrates its 81st anniversary at Hindon Air Force Base
<とーころが、パキスタン空軍では>
HISTORY OF PAF
1933年云々と記載。
もっとも、基地を構えたのと、訓練を開始したのは違うとか何とかの事情があって、両方正しいのかもしれん。
Liddell Hart Centre for Military Archives:BOUCHIER, Sir Cecil Arthur (1895-1979), Air Vice Marshal
Spitfires in Japan
From Farnborough to the Far East
バトル・オブ・ブリテンの際にも飛行隊の司令官として活躍。
wiki/RAF_Hornchurch#Notable_Station_Commanders
飛行士の名前をずらずら並べていて、彼らを直接知っていて云々とあるのだが、イギリス人の間ではエース飛行士は固有名詞で知られているのか。
国の絶体絶命の危機を救った英雄たちだからな。
wiki/The_Few
ジョージ6世が勲章を授与するため基地を急に訪問した際、受勲者以外に(よく知っているベテラン飛行士は出撃中だったので)基地にいた新着の将校や予備の兵士を整列させた。
「紹介してほしい」と国王に促されたが、新しく着任したばかりの将校の名前など知らない!
そこで、出まかせに色(ホワイト、ブラウン・・・)や詩人の名前などを順に繰り出して素知らぬ顔で急場を凌いだという話が愉快。
岩国飛行場小史:1946年
オーストラリア空軍ムスタング戦闘機隊、ニュージーランド空軍コルセア戦闘機隊、インド 兵主体の英空軍スピットファイアー戦闘機隊が順に飛来 司令官はボーチャ英空軍少将
~「ボーチャ英空軍少将」というのが本書の主人公ね。
「ベストアンサー」もいい加減なもんだ:戦後進駐軍はどのように上陸して撤収していったのですか?アメリカ軍だけでなくイギリス、オランダ、オーストラリア、カナダ軍も駐留していたのですか?
ページ下部のdejyulnayaさんの回答(ベストアンサー以外の回答)が正解。
XI Squadron formed part of the occupation forces in Japan in From 1946 - 1948. Equipped with Spitfire XIV and based at Iwakuni and Miho.
バウチャー少将は、英連邦空軍の指揮官として岩国に駐留。
"アメリカ軍部隊の進駐が完了した後の1946年2月以降、英連邦軍約4万人が上陸し、中国・四国地方の占領に当たりました(ただし、米第8軍の管轄下にありました)。"
食糧不足で大変な日本なので、進駐軍は食糧は全量持ち込みのこと、という指示だったが、中国軍は現地調達の方針だったこともあり、中国軍(国民党軍ね)の日本駐留は実現しないで済んだ由。
実現していたら大変なことになっていた?
一旦退役後、朝鮮戦争勃発を受け、乞われて再度国連軍の参謀としてマッカーサー司令部に勤務。
「英軍部隊を送れ…などという運びにはならないように」と特にくぎを刺されて赴任するが、現地を視察して「(釜山から追い落とされそうで)ダンケルクになってしまう」と危機感を強め、香港の部隊を大至急派遣すべしと提言して採用される。
西側諸国は派兵決議(国連軍の編成)に賛成したものの、準備だ何だと時間が経過するうちに事態がおさまり、実際に派兵せずに済むことを期待していたわけか。
いずれ派兵するとことになる筈なので、米が最も困っている時点でいの一番に助けるべしと主張した著者は、解任されるかもしれないと覚悟を決めて報告電を発信。
英国大使がなかなかマッカーサーに会えないのに対して、著者は2日に一度ほどの頻度でしばしば総司令官に面会。
自分(大使)も会えるように何とかしてほしいとの大使の依頼をつなぐが、英大使に会うと他国の大使にも会わなければならないので、例外は作れないと言われた由。
帰国後、チャーチルが朝鮮戦争中の著者の報告電を気に入っていたことが判明。
「バウチャーの書きっぷりが気に入ったね」は、チャーチルの言。
週末の昼食に招かれ、慰労される。
「ヤールー川」は、(カッコ)付きでもいいから鴨緑江と書いた方がよいと思う。
編者のドロシー夫人はご健在で、葉山の有名人?
逗子の文化をつなぎ、広め、深める会
日本人以上の日本人ともいえるドロシーさんが語る 「大正から昭和前期の葉山・逗子の人と風物」
(講師:ドロシー・ブリトン(レディ・バウチャー)氏) ←リンク切れ!
代替としてこれでも貼っておくね。
叔母のドロシーと2歳になる前のドロシー・ブリトン 1923年撮影
ある書評:尻切れ頭切れのダイジェスト版みたいな感じがした~新世界読書放浪
原書名:SPITFIRES IN JAPAN FROM FARNBOROUGH TO THE FAR EAST
(Bouchier,Sir Cecil)バウチャー,サー・セシル【著】
加藤 恭子 今井 萬亀子【訳】
社会評論社 (2008/12/25 出版)
加藤恭子のノンフィクションの書き方講座
ファーンボロは、英国の航空機開発拠点で、著者が若い頃にテストパイロットとして飛んでいた。航空ショーで有名。
wiki/Royal_Aircraft_Establishment
wiki/Cecil_Bouchier
インド空軍が
英領インドは、その後パキスタンと別れたので、インド、パキスタン両空軍の父である由。
<1933を1932に訂正>
81周年の記事を見て気付く。1932年が正当だった。
IAF celebrates its 81st anniversary at Hindon Air Force Base
<とーころが、パキスタン空軍では>
HISTORY OF PAF
1933年云々と記載。
もっとも、基地を構えたのと、訓練を開始したのは違うとか何とかの事情があって、両方正しいのかもしれん。
Liddell Hart Centre for Military Archives:BOUCHIER, Sir Cecil Arthur (1895-1979), Air Vice Marshal
Spitfires in Japan
From Farnborough to the Far East
バトル・オブ・ブリテンの際にも飛行隊の司令官として活躍。
wiki/RAF_Hornchurch#Notable_Station_Commanders
飛行士の名前をずらずら並べていて、彼らを直接知っていて云々とあるのだが、イギリス人の間ではエース飛行士は固有名詞で知られているのか。
国の絶体絶命の危機を救った英雄たちだからな。
wiki/The_Few
ジョージ6世が勲章を授与するため基地を急に訪問した際、受勲者以外に(よく知っているベテラン飛行士は出撃中だったので)基地にいた新着の将校や予備の兵士を整列させた。
「紹介してほしい」と国王に促されたが、新しく着任したばかりの将校の名前など知らない!
そこで、出まかせに色(ホワイト、ブラウン・・・)や詩人の名前などを順に繰り出して素知らぬ顔で急場を凌いだという話が愉快。
岩国飛行場小史:1946年
オーストラリア空軍ムスタング戦闘機隊、ニュージーランド空軍コルセア戦闘機隊、インド 兵主体の英空軍スピットファイアー戦闘機隊が順に飛来 司令官はボーチャ英空軍少将
~「ボーチャ英空軍少将」というのが本書の主人公ね。
「ベストアンサー」もいい加減なもんだ:戦後進駐軍はどのように上陸して撤収していったのですか?アメリカ軍だけでなくイギリス、オランダ、オーストラリア、カナダ軍も駐留していたのですか?
ページ下部のdejyulnayaさんの回答(ベストアンサー以外の回答)が正解。
XI Squadron formed part of the occupation forces in Japan in From 1946 - 1948. Equipped with Spitfire XIV and based at Iwakuni and Miho.
バウチャー少将は、英連邦空軍の指揮官として岩国に駐留。
"アメリカ軍部隊の進駐が完了した後の1946年2月以降、英連邦軍約4万人が上陸し、中国・四国地方の占領に当たりました(ただし、米第8軍の管轄下にありました)。"
食糧不足で大変な日本なので、進駐軍は食糧は全量持ち込みのこと、という指示だったが、中国軍は現地調達の方針だったこともあり、中国軍(国民党軍ね)の日本駐留は実現しないで済んだ由。
実現していたら大変なことになっていた?
一旦退役後、朝鮮戦争勃発を受け、乞われて再度国連軍の参謀としてマッカーサー司令部に勤務。
「英軍部隊を送れ…などという運びにはならないように」と特にくぎを刺されて赴任するが、現地を視察して「(釜山から追い落とされそうで)ダンケルクになってしまう」と危機感を強め、香港の部隊を大至急派遣すべしと提言して採用される。
西側諸国は派兵決議(国連軍の編成)に賛成したものの、準備だ何だと時間が経過するうちに事態がおさまり、実際に派兵せずに済むことを期待していたわけか。
いずれ派兵するとことになる筈なので、米が最も困っている時点でいの一番に助けるべしと主張した著者は、解任されるかもしれないと覚悟を決めて報告電を発信。
英国大使がなかなかマッカーサーに会えないのに対して、著者は2日に一度ほどの頻度でしばしば総司令官に面会。
自分(大使)も会えるように何とかしてほしいとの大使の依頼をつなぐが、英大使に会うと他国の大使にも会わなければならないので、例外は作れないと言われた由。
帰国後、チャーチルが朝鮮戦争中の著者の報告電を気に入っていたことが判明。
「バウチャーの書きっぷりが気に入ったね」は、チャーチルの言。
週末の昼食に招かれ、慰労される。
「ヤールー川」は、(カッコ)付きでもいいから鴨緑江と書いた方がよいと思う。
編者のドロシー夫人はご健在で、葉山の有名人?
逗子の文化をつなぎ、広め、深める会
日本人以上の日本人ともいえるドロシーさんが語る 「大正から昭和前期の葉山・逗子の人と風物」
(講師:ドロシー・ブリトン(レディ・バウチャー)氏) ←リンク切れ!
代替としてこれでも貼っておくね。
叔母のドロシーと2歳になる前のドロシー・ブリトン 1923年撮影
ある書評:尻切れ頭切れのダイジェスト版みたいな感じがした~新世界読書放浪