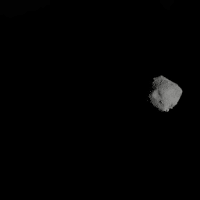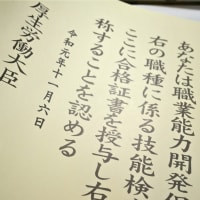説経節「をぐり」のはじめのはじめ、小栗出生について語りはじめる段は、一種の呪術めいた空気に満たされているようにも読めます。それは仏教的というよりは、仏教以前の山岳信仰のような、古い起源に由来する日本の土着的な思考風土に根ざしているように思われて仕方ありません。
「土着的」な「思考風土」とはいっても、それを傍証してくれるような確実な資料が手もとにあるわけではないのですが、これは「をぐり」に限った印象というわけでもない。
説経節のいくつかを読んでみると、はたと首を傾げてしまうことがあります。
もし、時衆の念仏聖と呼ばれる人々が純粋に仏法を説いて廻ることを目的としていたのだったら、それにふさわしいお話は他に山ほど、いくらでもあっただろうに、と思うからです。つまりは、当時すでにありふれていた「基礎教養」とも呼ぶべき仏法仏説を説いて民衆の支持を得たわけではない。このことはあきらかで、人々にそれまでとは違った「別の意識」をダイナミックに示す、という要請が生み出した「語り」が遊行の中心にあったはずです。説経節の役割も深くそこに関わりがあったはずだ、と。
「別の意識」を喚起することが、革命的思想や社会改革などのような「方法論」ではなかった、というのが注目すべき点なのだろうと思います。
「古い心」、「古い地層」に回帰していくようなラインを複雑に織り込んでいるような「物語」によって、人々の心の中にリアルにつながる古い「風景」を甦らせること。ここに力点が置かれているようにも読めてくるのです。レトロスペクティブに「世界」を再構築していく、と言えるような意図を感じる。。。それまでに語られてきた「仏教」から少し離れたところ、ほんの少しズラした視点から新しい「物語」が語りだされる必然性があったと見るべきだろうと思うのです。
もっとも、僕らが手に取って普通に読める「をぐり」は江戸時代にまとめられた浄瑠璃や歌舞伎の「脚本」のようなものを底本にしているので、そこには本居宣長の時代から芽吹きはじめていた「古神道」への「回帰」を想像させるような「新しい」流れが背景にあることもカウントしておかなきゃいけないのだけど。説経節を読む上では、「新しさ」は二重に重ねられている。「新しい」時衆ムーブメントが庶民文化の萌芽にあるとすれば、それが庶民文化爛熟期の江戸時代の説経節ムーブメントと重なっていくことも、必然的な共感だったと言い切りたいのです。「新しい」とは「庶民の」と言い換えても差し支えはまったくないのではないだろうか、と。
その「新しい」物語に求められる「新しい」意匠とは何だったのか?
「古い心」への回帰を実現するために要請されていたドラマツルギー・・・でも、当時にあって「仏教以前」の世界はすでにファンタジーです。手がかりさえすでに失われつつあったような道の再生、再構築に等しい。。。そのために、すでに広く知られている仏教的なテクニカルタームを駆使して「道」を語ることで、その「道」を現実に支える。。。そういう空気が背景にあったのではないか?街道伝いに広まっていった時衆ムーブメントにふさわしい在り方は、辻と辻が交わるような場にあったのだから。それ故に、説経節の主人公たちは、例外なく旅に出るのです。街道に沿って。
「をぐり」にはその出だしから古神道的「自然」を感じさせるのに十分な舞台が設えられています。
仮名は兼家の仮名、母は常陸の源氏の流れ、氏と位は高けれど、男子にても、女子にても、
末の世継が、御ざなうて、鞍馬の毘沙門にお詣りあつて、申子をなされける。
満ずる夜の御夢想に、三つなりのありの実を、給はるなり。あらめでたの御ことやと、
山海の珍物に、国土の菓子を調へて、御喜びかぎりなし。
鞍馬の毘沙門天と言えば、誰しも牛若丸がパッと思い浮かぶはずですが、鞍馬山の名がつぶやかれるだけで、なにがしかの空気を醸し出しているように感じられます。鞍馬天狗とか、ね。
当時の人々が「鞍馬山」で連想させられたことって具体的にはどういう風景だったのだろうか?究極的な答えはほとんど永遠に得られないだろうと思いつつも、ある種の傾向はいろいろ調べられそうではあります。
霊山鞍馬山に何をしにお詣りするのかというと「申子(もうしご)」をするために行く、と語られます。「子ども授かるように祈る」というのが「申子」なのですが、その実態にはちょっと驚くべきことがあって、むしろその方が「申子」の意を尽くしているらしい。これについては、別の場所で少し詳しくやろうかと思います。
後段、照手姫もまた日光山にて「申子」した後に与えられた女子であることが相模の商人「後藤左衛門」の口から説明されることになるのですが、これは意図的な一致とみてよいと思います。出会うべき相手は、お互いに「山の神様」への「申子」によって与えられていたというのは、自然なバランスです。
ここで「満ずる夜の御夢想に」と夢の中にあらわれた「しるし」について語られます。その「しるし」が「三つ成りのありの実」。梨の実のことを「ありの実」と呼び代えているのですが、それがどうして「めでたいこと」なのかについては、説明らしきこともありません。
ここは少し読み込んでみてもよいかも。というのも、「三つ」の「なしの実=ありの実」が「成る」ことから、即座に仏教でいうところの「三界」を思い起こさせるからです。
目の前には「ない」ように見える「三界」を「三有」、つまり「ある」ものとして現実に引き出してみせる。この御託宣が「鞍馬の毘沙門天」から夢によって下されることになるわけです。ご託宣はまずは小栗誕生で証しされることになります。「申子」によって、「なし」だった子が「ある」ようになるからです。
「ある」ようになったその子が「三つ」の「ある」=「三界」をくぐり抜ける、という予感(というより、もはや予定)は小栗出生から用意されている。こう考えると説経節「をぐり」においては構成的に意味を配置していると見なせるシーンが特定できそうです。
御台所は、をしへけむちくあらたかに、七月のわづらひ、九月の苦しみ、当たる十月と申すには、御産の紐を、お解きある。女房たちは参り、介錯申し、抱き取り、男子か、女子かと、お問ひある。玉を磨き、瑠璃をのべたるごとくなる、御若君にておはします。あらめでたの御ことや、須達、福分におなり候へと、産湯を取りて参らする。肩の上の鳳凰に、手の中のあいしの玉、桑の木の弓に、蓬の矢、天地和合と、射払ひ申す。屋形に、齢久しき翁の太夫は、参りて、この若君に、御名をつけてまゐらせん、げにまこと、毘沙門の御夢想に、三つなりのありの実を、給はるなれば、ありの実にことよせて、すなはち御名をば、有若殿と、奉る。
「毘沙門の御夢想」にあらわれた「三つなりのありの実」。これにちなんで小栗判官の幼名は「有若」とつけられることになります。これから語られる物語が、すべて現実に「存在する」「三界」を巡るだろうということを「申子」の「御夢想」と「有若」という幼名で示しているとも言えるのです。
「土着的」な「思考風土」とはいっても、それを傍証してくれるような確実な資料が手もとにあるわけではないのですが、これは「をぐり」に限った印象というわけでもない。
説経節のいくつかを読んでみると、はたと首を傾げてしまうことがあります。
もし、時衆の念仏聖と呼ばれる人々が純粋に仏法を説いて廻ることを目的としていたのだったら、それにふさわしいお話は他に山ほど、いくらでもあっただろうに、と思うからです。つまりは、当時すでにありふれていた「基礎教養」とも呼ぶべき仏法仏説を説いて民衆の支持を得たわけではない。このことはあきらかで、人々にそれまでとは違った「別の意識」をダイナミックに示す、という要請が生み出した「語り」が遊行の中心にあったはずです。説経節の役割も深くそこに関わりがあったはずだ、と。
「別の意識」を喚起することが、革命的思想や社会改革などのような「方法論」ではなかった、というのが注目すべき点なのだろうと思います。
「古い心」、「古い地層」に回帰していくようなラインを複雑に織り込んでいるような「物語」によって、人々の心の中にリアルにつながる古い「風景」を甦らせること。ここに力点が置かれているようにも読めてくるのです。レトロスペクティブに「世界」を再構築していく、と言えるような意図を感じる。。。それまでに語られてきた「仏教」から少し離れたところ、ほんの少しズラした視点から新しい「物語」が語りだされる必然性があったと見るべきだろうと思うのです。
もっとも、僕らが手に取って普通に読める「をぐり」は江戸時代にまとめられた浄瑠璃や歌舞伎の「脚本」のようなものを底本にしているので、そこには本居宣長の時代から芽吹きはじめていた「古神道」への「回帰」を想像させるような「新しい」流れが背景にあることもカウントしておかなきゃいけないのだけど。説経節を読む上では、「新しさ」は二重に重ねられている。「新しい」時衆ムーブメントが庶民文化の萌芽にあるとすれば、それが庶民文化爛熟期の江戸時代の説経節ムーブメントと重なっていくことも、必然的な共感だったと言い切りたいのです。「新しい」とは「庶民の」と言い換えても差し支えはまったくないのではないだろうか、と。
その「新しい」物語に求められる「新しい」意匠とは何だったのか?
「古い心」への回帰を実現するために要請されていたドラマツルギー・・・でも、当時にあって「仏教以前」の世界はすでにファンタジーです。手がかりさえすでに失われつつあったような道の再生、再構築に等しい。。。そのために、すでに広く知られている仏教的なテクニカルタームを駆使して「道」を語ることで、その「道」を現実に支える。。。そういう空気が背景にあったのではないか?街道伝いに広まっていった時衆ムーブメントにふさわしい在り方は、辻と辻が交わるような場にあったのだから。それ故に、説経節の主人公たちは、例外なく旅に出るのです。街道に沿って。
*
「をぐり」にはその出だしから古神道的「自然」を感じさせるのに十分な舞台が設えられています。
仮名は兼家の仮名、母は常陸の源氏の流れ、氏と位は高けれど、男子にても、女子にても、
末の世継が、御ざなうて、鞍馬の毘沙門にお詣りあつて、申子をなされける。
満ずる夜の御夢想に、三つなりのありの実を、給はるなり。あらめでたの御ことやと、
山海の珍物に、国土の菓子を調へて、御喜びかぎりなし。
鞍馬の毘沙門天と言えば、誰しも牛若丸がパッと思い浮かぶはずですが、鞍馬山の名がつぶやかれるだけで、なにがしかの空気を醸し出しているように感じられます。鞍馬天狗とか、ね。
当時の人々が「鞍馬山」で連想させられたことって具体的にはどういう風景だったのだろうか?究極的な答えはほとんど永遠に得られないだろうと思いつつも、ある種の傾向はいろいろ調べられそうではあります。
霊山鞍馬山に何をしにお詣りするのかというと「申子(もうしご)」をするために行く、と語られます。「子ども授かるように祈る」というのが「申子」なのですが、その実態にはちょっと驚くべきことがあって、むしろその方が「申子」の意を尽くしているらしい。これについては、別の場所で少し詳しくやろうかと思います。
後段、照手姫もまた日光山にて「申子」した後に与えられた女子であることが相模の商人「後藤左衛門」の口から説明されることになるのですが、これは意図的な一致とみてよいと思います。出会うべき相手は、お互いに「山の神様」への「申子」によって与えられていたというのは、自然なバランスです。
ここで「満ずる夜の御夢想に」と夢の中にあらわれた「しるし」について語られます。その「しるし」が「三つ成りのありの実」。梨の実のことを「ありの実」と呼び代えているのですが、それがどうして「めでたいこと」なのかについては、説明らしきこともありません。
ここは少し読み込んでみてもよいかも。というのも、「三つ」の「なしの実=ありの実」が「成る」ことから、即座に仏教でいうところの「三界」を思い起こさせるからです。
目の前には「ない」ように見える「三界」を「三有」、つまり「ある」ものとして現実に引き出してみせる。この御託宣が「鞍馬の毘沙門天」から夢によって下されることになるわけです。ご託宣はまずは小栗誕生で証しされることになります。「申子」によって、「なし」だった子が「ある」ようになるからです。
「ある」ようになったその子が「三つ」の「ある」=「三界」をくぐり抜ける、という予感(というより、もはや予定)は小栗出生から用意されている。こう考えると説経節「をぐり」においては構成的に意味を配置していると見なせるシーンが特定できそうです。
御台所は、をしへけむちくあらたかに、七月のわづらひ、九月の苦しみ、当たる十月と申すには、御産の紐を、お解きある。女房たちは参り、介錯申し、抱き取り、男子か、女子かと、お問ひある。玉を磨き、瑠璃をのべたるごとくなる、御若君にておはします。あらめでたの御ことや、須達、福分におなり候へと、産湯を取りて参らする。肩の上の鳳凰に、手の中のあいしの玉、桑の木の弓に、蓬の矢、天地和合と、射払ひ申す。屋形に、齢久しき翁の太夫は、参りて、この若君に、御名をつけてまゐらせん、げにまこと、毘沙門の御夢想に、三つなりのありの実を、給はるなれば、ありの実にことよせて、すなはち御名をば、有若殿と、奉る。
「毘沙門の御夢想」にあらわれた「三つなりのありの実」。これにちなんで小栗判官の幼名は「有若」とつけられることになります。これから語られる物語が、すべて現実に「存在する」「三界」を巡るだろうということを「申子」の「御夢想」と「有若」という幼名で示しているとも言えるのです。