今日は、休日だったので、先日の移動運用で断線したコーリニアアンテナの修理と製作を行うことにした。
使用しているコーリニアアンテナは、同軸ケーブルを半田付けして、移動運用の度に丸めたり伸ばしたりしているので、半田付け部分が何度も曲げられて、いつか断線する。
もう10回以上は、新たに作ったり修理したりを繰り返している。断線までの期間を伸ばすノウハウは持っているが、防ぐことは出来ていない。
出来るとするならば、半田付けした上をエポキシボンドで固着する方法か?と思うが、それではメンテナンスが出来なくなる。
断線が無くなれば、それでも良いと思っている。一度、それをチャレンジしてみるか?
【同軸】
コーリニアの同軸は、3D2Vを使用する。理由は簡単、山岳移動なので少しでも軽量にしたいからだ。
それを5m以内の5D2Vケーブルでリグまで引っ張ってきている。
ついでに書くなら、関東UHFでは430MHzで5DFBを15mで使い、2012年の全市全郡では、50MHzで3D2V15mで給電していた。
山岳移動は、標高とロケを稼ぐので、荷物を軽くする為、ケーブルには、さほどこだわらなくても良いか?
【同軸ストリッパー(写真)】
これまでは、カッターとワイアーストリッパーで同軸の皮剥きを行ってきた。これが効率が悪い。
そこで前回から同軸ストリッパーを使っている。
ジェフコムのCCS-600というストリッパーだ。少し練習をしないと上手く出来ないけど、かなり効率がアップした。

【同軸をカット】
3D2Vも同軸の短縮率は、0.67なので、(300000km/433MHz/2)*0.67=0.232mが半波長だ。
つまり、中心周波数432MHzの7段コーリニアを作るならば、1/2λの0.232m同軸(以降の長さというのは、網線の先端間で表している)が7本必要となる。また、その両サイドに1/4λの同軸を付ける。
写真は、7段コーリニア用にカットしたエレメントだ。中心の1/2λの同軸を増やしていけば段数が上がるというわけだ。
30段にしたいのならば、1/2λエレメントを30本用意すれば良い。(←これを山岳移動で使用すると打ち上げ角が狭すぎる)
[何度か製作して最終的に採用している長さ](2014.8.30追記)
| 中心周波数 | 145MHz | 433MHz | 1295MHz | |
| 同軸短縮率 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 3D2V等 |
| 物理1/4λ | 519 | 173 | 58 | |
| 同軸1/4λ | 348 | 116 | 39 | 短縮率込み(下図のK含む) |
| 同軸1/2λ | 696 | 232 | 78 | 短縮率込み(下図のK含む) |
| スタブ | 173 | 58 | 19 | スタブ(長めに用意しカット) |

【同軸を半田付け】
1/2λの同軸を半田付けしていく。芯線を相手同軸の網線に、網線は相手同軸の芯線に半田付けする。
(重要!)半田付けする度に、エレメントがショートしてないかをテスター等で確認する。この段階では、交互に接続しているだけなので、一番外側の芯線と網線には全く導通がない。
これをショートさせてしまうと、後からではどこが原因か分からなくなる。

【1/4λエレメント取付け】
1/2λのエレメントの半田付けが終了したら、両サイドに1/4λの同軸を半田付けする。
この段階でも導通はない。

【補強材の取付け】
同軸のみだとネジれや折れがひどくなるので、捻れないように割箸(または竹串等)とテープで補強をする。
調整してから、最後に防水の為にVINI-TAPE(ビニテープ)を巻く。←ワイヤーハーネス締結用のテープがあればベスト。

【マッチング部取付け】
最後に1/4λのエレメントの片側へマッチング、ラジアル部を取り付ける。それが、下記の写真1、2、3だ。
MPコネクタまでの長さを1m以上の任意長とする。片方にMPコネクタを取り付ける。反対の端は、スタブを平行に取り付ける。
1は、173mm、2(1の長さのうち末端10mm)で、幅10mm程度で網線が出るように、同軸の外皮を剥がす。その部分へ同軸の網線を長さ220mmにカットしたもの同軸に被せて(被せると短くなるので173mmに調整する)、2の場所で半田付けする。

マッチング、ラジアル部へスタブを取付け。スタブは、網線同士を半田付け。
マッチング、ラジアル部は、芯線を相手同軸の網線に、網線は相手同軸の芯線に半田付けする。

【調整】
半田付けが確実であれば、ほとんど問題は起こらない。あとは、マッチング用のスタブの調整を行う。
調整中に、東海コンテスト参加中の13:26 7M3OER/2を見つけてコールをしてみる。(その時は、家と家の間の隙間から送信)
この場所ならば59+++だった。

【コーリニア完成】
仮調整を行って動作を確認し飛びを確認したら、同軸の接続部へテープを巻いて防水処理を行う。
出来上がったコーリニアを大山の見える位置(地面から50cm)に設置し、ワッチしてみた。
それでも、大都市コンテスト参加の栃木局や2エリア局とも交信が出来た。十分に性能が発揮出来ているようだ。











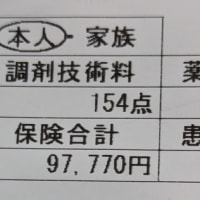








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます