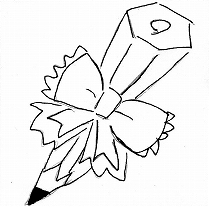今日は二十四節気のひとつ『白露』です。
草花に朝露がつき、朝日の当たると白く輝いて見える頃という意味なのだそうです。
現在の法律では、「太陽黄経が165度のとき」と定められています。
日中はまだまだ暑い日が続いていますが、朝晩は涼しくなってきて、今日なんかエアコンがいらないぐらいです。
単純に嬉しい☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
夜中に大気が冷えて、空気中の水蒸気が凝固して水滴となって付着したものを露と呼びます。
ちなみに霜は、字も似ていますが、空気中の水蒸気が昇華して地面や地物に付着した氷の結晶のことを言います。
この時期は、まだそこまで冷たくないということですね。
七草粥にして無病息災を祈る「春の七草」はよく知られていますが、実は秋にも「秋の七草」があります。
春とは違い、その美しさを鑑賞するためのものだそうで、万葉集の時代から言い伝えられています。
萩(はぎ)、尾花(おばな)=ススキ、葛(くず)、撫子(なでしこ)、女郎花(おみなえし)、藤袴(ふじばかま)、朝貌(あさがお)=キキョウの七つです。
アサガオといえば小学生の時の夏の観察日記を思い出しますが、このアサガオが日本に来たのは万葉集の時代よりも後のことだそうで、ここでいう朝貌は桔梗の花のことだろうというのが通説だそうです。
そういえば昔、「萬葉集」が読めなくて、「くずのはしゅう」だと思ってて、どれだけ図書館探しても見当たらないから職員さんに聞いて持ってきてもらったときに「まんようしゅう」って言われてひっくり返るぐらい驚いたなあ...。