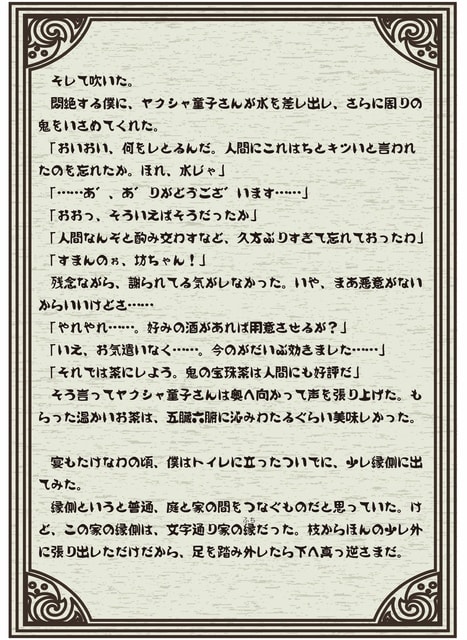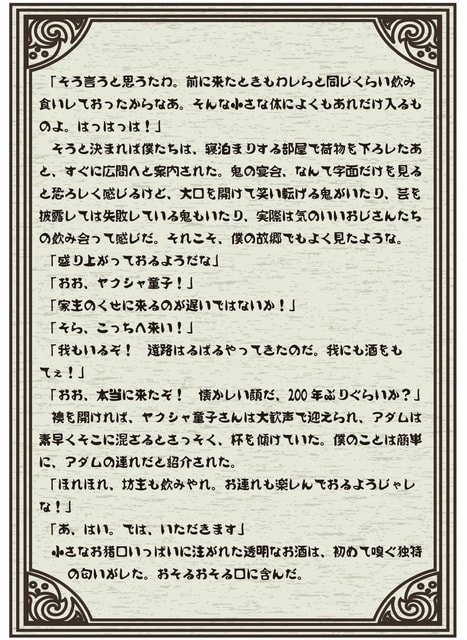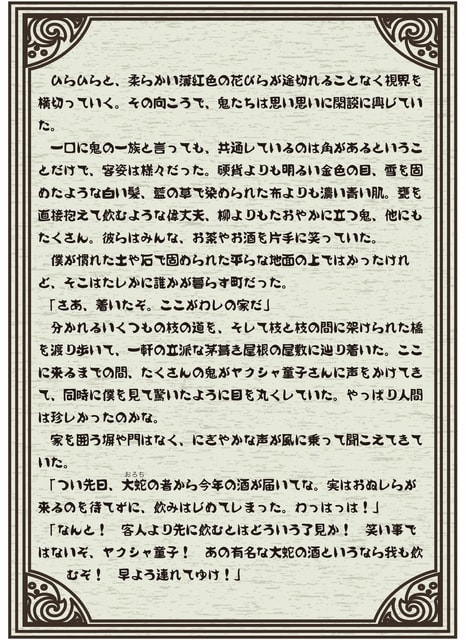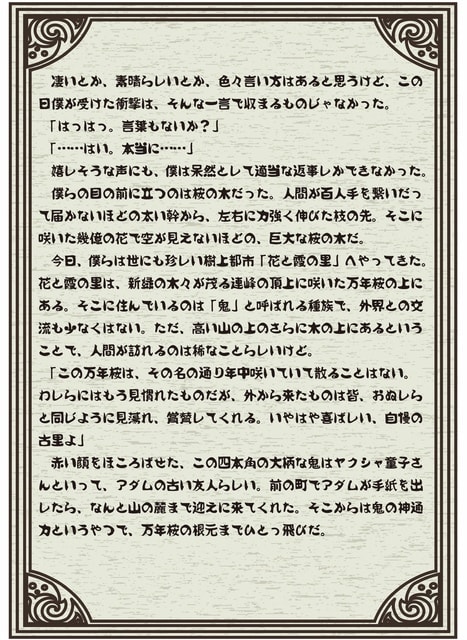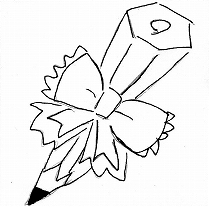1日1枚画像を作成して投稿するつもりのブログ、改め、一日一つの雑学を報告するつもりのブログ。
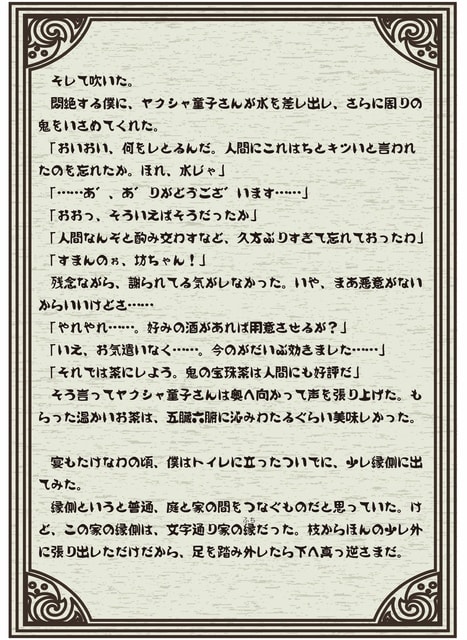
本文詳細↓
そして吹いた。
悶絶する僕に、ヤクシャ童子さんが水を差し出し、さらに周りの鬼をいさめてくれた。
「おいおい、何をしとるんだ。人間にこれはちとキツいと言われたのを忘れたか。ほれ、水じゃ」
「……あ゛、あ゛りがどゔござ゛います……」
「おおっ、そういえばそうだったか」
「人間なんぞと酌み交わすなど、久方ぶりすぎて忘れておったわ」
「すまんのぉ、坊ちゃん!」
残念ながら、謝られてる気がしなかった。いや、まあ悪意がないからいいけどさ……
「やれやれ……。好みの酒があれば用意させるが?」
「いえ、お気遣いなく……。今のがだいぶ効きました……」
「それでは茶にしよう。鬼の宝珠茶は人間にも好評だ」
そう言ってヤクシャ童子さんは奥へ向かって声を張り上げた。もらった温かいお茶は、五臓六腑に沁みわたるぐらい美味しかった。
宴もたけなわの頃、僕はトイレに立ったついでに、少し縁側に出てみた。
縁側というと普通、庭と家の間をつなぐものだと思っていた。けど、この家の縁側は、文字通り家の縁(ふち)だった。枝からほんの少し外に張り出しただけだから、足を踏み外したら下へ真っ逆さまだ。
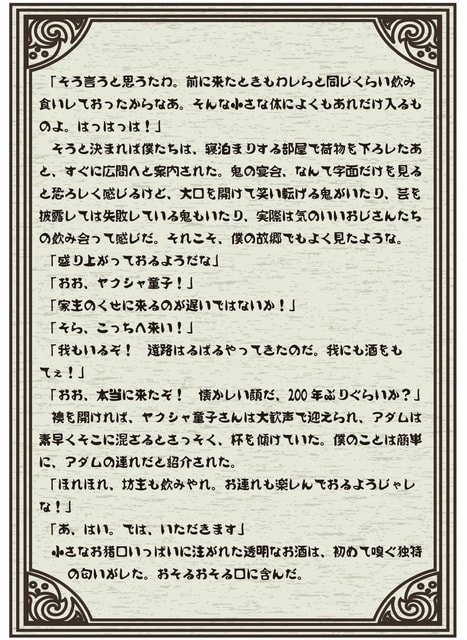
本文詳細↓
「そう言うと思うたわ。前に来たときもわしらと同じくらい飲み食いしておったからなあ。そんな小さな体によくもあれだけ入るものよ。はっはっは!」
そうと決まれば僕たちは、寝泊まりする部屋で荷物を下ろしたあと、すぐに広間へと案内された。鬼の宴会、なんて字面だけを見ると恐ろしく感じるけど、大口を開けて笑い転げる鬼がいたり、芸を披露しては失敗している鬼もいたり、実際は気のいいおじさんたちの飲み会って感じだ。それこそ、僕の故郷でもよく見たような。
「盛り上がっておるようだな」
「おお、ヤクシャ童子!」
「家主のくせに来るのが遅いではないか!」
「そら、こっちへ来い!」
「我もいるぞ! 遠路はるばるやってきたのだ。我にも酒をもてぇ!」
「おお、本当に来たぞ! 懐かしい顔だ、200年ぶりぐらいか?」
襖を開ければ、ヤクシャ童子さんは大歓声で迎えられ、アダムは素早くそこに混ざるとさっそく、杯を傾けていた。僕のことは簡単に、アダムの連れだと紹介された。
「ほれほれ、坊主も飲みやれ。お連れも楽しんでおるようじゃしな!」
「あ、はい。では、いただきます」
小さなお猪口いっぱいに注がれた透明なお酒は、初めて嗅ぐ独特の匂いがした。おそるおそる口に含んだ。
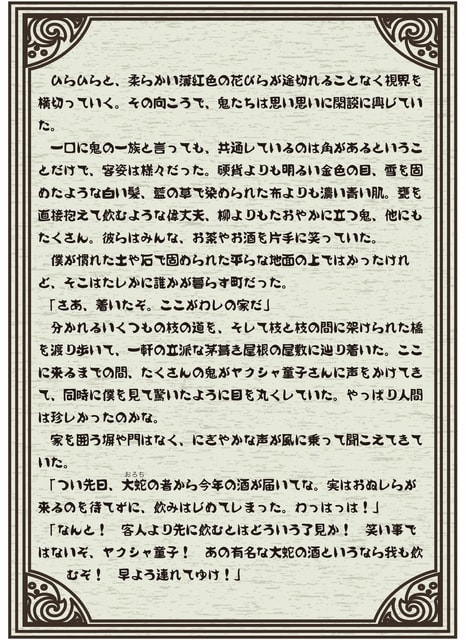
本文詳細↓
ひらひらと、柔らかい薄紅色の花びらが途切れることなく視界を横切っていく。その向こうで、鬼たちは思い思いに閑談に興じていた。
一口に鬼の一族と言っても、共通しているのは角があるということだけで、容姿は様々だった。硬貨よりも明るい金色の目、雪を固めたような白い髪、藍の草で染められた布よりも濃い青い肌。甕を直接抱えて飲むような偉丈夫、柳よりもたおやかに立つ鬼、他にもたくさん。彼らはみんな、お茶やお酒を片手に笑っていた。
僕が慣れた土や石で固められた平らな地面の上ではかったけれど、そこはたしかに誰かが暮らす町だった。
「さあ、着いたぞ。ここがわしの家だ」
分かれるいくつもの枝の道を、そして枝と枝の間に架けられた橋を渡り歩いて、一軒の立派な茅葺き屋根の屋敷に辿り着いた。ここに来るまでの間、たくさんの鬼がヤクシャ童子さんに声をかけてきて、同時に僕を見て驚いたように目を丸くしていた。やっぱり人間は珍しかったのかな。
家を囲う塀や門はなく、にぎやかな声が風に乗って聞こえてきていた。
「つい先日、大蛇(おろち)の者から今年の酒が届いてな。実はおぬしらが来るのを待てずに、飲みはじめてしまった。わっはっは!」
「なんと! 客人より先に飲むとはどういう了見か! 笑い事ではないぞ、ヤクシャ童子! あの有名な大蛇の酒というなら我も飲むぞ! 早よう連れてゆけ!」

本文詳細↓
「一気に里へ飛んでもよかったのだが、やはり外からも万年桜を見てほしかったのだ。これほどの桜は、この大地には他にあるまい。よくよく目に焼き付けておけ」
「うむ、明るい中の桜というのも好(よ)いな。より華やかだ。前に見た時は夕方だったからなあ。入った時はイノシシの腹の中で揺られながらであったし」
「そういえばそうだったか。懐かしい話だ。おぬしがくると言ったら、会いたいという奴が二、三おったぞ」
「おおっ、どの女性(にょしょう)だ? 菖蒲(あやめ)の君か、若葛(わかかずら)の君か、それとも……」
「いや、ちょっと待って。普通に話を進めるな。なんだイノシシの腹の中って。そして何人いるんだよ」
思わず割り込んだが、アダムはきょとんとヤクシャ童子さんを仰いぐだけだった。
「いやあ、あの時のことは忘れもせんよ。わしがかっ捌いたイノシシの腹の中からこやつがころっと出てきおってなあ。さすがのわしも仰天したわ。はっはっは! まったく、よくぞ生きておったものよ。あと、おぬしに会いたいと言っていたのは酒呑み仲間のほうだ」
僕といいヤクシャ童子さんといい、こいつは普通に誰かと出会うということができないのだろうか……。頭が痛くなる話だったけど、自分を待っていたのが女性じゃないと分かって凹むアダムに溜飲が下がったので良しとする。
「さて、なにはともあれ歓迎しよう。ようこそ、我が里へ」
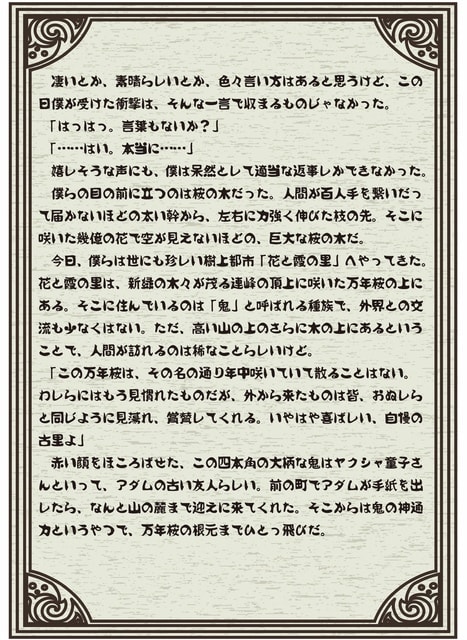
本文詳細↓
凄いとか、素晴らしいとか、色々言い方はあると思うけど、この日僕が受けた衝撃は、そんな一言で収まるものじゃなかった。
「はっはっ。言葉もないか?」
「……はい。本当に……」
嬉しそうな声にも、僕は呆然として適当な返事しかできなかった。
僕らの目の前に立つのは桜の木だった。人間が百人手を繋いだって届かないほどの太い幹から、左右に力強く伸びた枝の先。そこに咲いた幾億の花で空が見えないほどの、巨大な桜の木だ。
今日、僕らは世にも珍しい樹上都市「花と霞の里」へやってきた。花と霞の里は、新緑の木々が茂る連峰の頂上に咲いた万年桜の上にある。そこに住んでいるのは「鬼」と呼ばれる種族で、外界との交流も少なくはない。ただ、高い山の上のさらに木の上にあるということで、人間が訪れるのは稀なことらしいけど。
「この万年桜は、その名の通り年中咲いていて散ることはない。わしらにはもう見慣れたものだが、外から来たものは皆、おぬしらと同じように見蕩れ、賞賛してくれる。いやはや喜ばしい、自慢の古里よ」
赤い顔をほころばせた、この四本角の大柄な鬼はヤクシャ童子さんといって、アダムの古い友人らしい。前の町でアダムが手紙を出したら、なんと山の麓まで迎えに来てくれた。そこからは鬼の神通力というやつで、万年桜の根元までひとっ飛びだ。