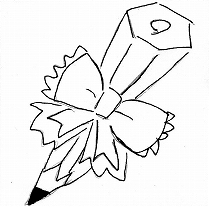今日は『苗字の日』です。
ちなみに2月13日にも「苗字制定記念日」なるものがあります。
1870(明治3)年に戸籍整理のため一般人も苗字を持つことを許可するおふれが出たのですが、それまで苗字は貴族や武士など一部の特権階級しか持つことができず、一般にはほとんど浸透していない概念でした。
なので、そんなおふれが出てもほとんどの人が苗字を名乗らずにいた結果、1875(明治8)年に改めて全員苗字を持つことを義務付けるおふれが出されました。
この1870年「平民苗字許可令」が出た日を『苗字の日』に制定し、1875年の「平民苗字必称義務令」が出た日を「苗字制定記念日」としたのです。
ところで、今日の『苗字の日』ですが、「名字」とも書きますよね。
どちらが正しいかと言えば、「どちらも正しい」ようなので、ほんっと日本人適当か! って思いました。
ではなぜ二通りの書き方があるのかというと、調べた限りでは「江戸時代は『苗字』が一般的だったが、戦後当用漢字表(日常使用される漢字の範囲を示したもの)に苗(みょう)という読み方が加えられなかったため、さらに古くからあった『名字』に回帰した」らしいです。
「名字」という言葉は平安時代中期以降にできたと言われています。
その頃台頭してきていた武士が所有していた土地を名田(みょうでん)と呼びました。
「この名田を支配している我の字(あざな。名前という意味がある漢字)」を、本来自分が持っていた名前とは別に名乗りだしたので、名字という言葉と概念が生まれたそうです。
一方の「苗字」は、江戸時代に生まれた言葉です。
地名に由来していた「名字」ですが、江戸時代にまでなると家や一族を示す側面が強くなってきました。
そこで、遠い子孫や末裔という意味がある「苗」という漢字を使った「苗字」が一般的になったそうです。
現代の日本人は明治の人たちのように自分で名字や名前を決めることができませんが、ペンネームや芸名という手段があるのでいいですよね。
べつに悪魔君とかでも構わないわけですし、心機一転で全く新しい名前にすることもできるわけですし。
ちなみに私のペンネームの「霧ヶ原」は、通学中のバスで見たバス停の名前が気に入ったからそれにした...と思っていたんですが、後々見てみるとどこにも「霧ヶ原」なんてバス停なかったんですよねー。
何と見間違えたんだよ自分ε-(´∀`; )