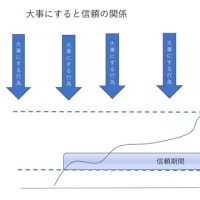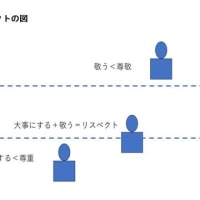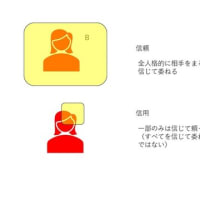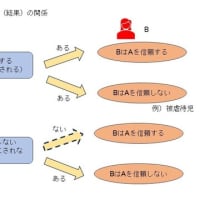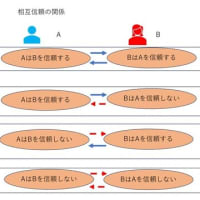対話のセミナーをやっていると次の段階があることを知ります。
1.お互い、どんな人なんだろうという
相互探索モード
2.お互いに傾聴しあって、深まる
相互傾聴モード
3.違いを認めた上で違和感が繰り出される
カオスモード
4.違和感が出ている場でおきていることを全員で共有し探求する
探求モード
5.場の一致点が浮き上がり、各自がすべきことがみえる
アクションモード
〇〇モードというのは今、勝手につけている仮名称です。
さて、ワールドカフェなどカフェ的雰囲気で1~2のステップはうまくいきます。
問題は3以降の部分。 ファシリテーターが表面上、
「さぁ違和感を遠慮なく吐き出してください」と促したところで、うまくはいきません。参加者が、傾聴し仲良くなった相手に、”相手を傷つけないように” ”嫌われたくない” というメンタルモデルが発動してしまうからです。特に普段、発言・発信力の機会のない人には難しい部分。
私がファシリテーターだと仮定すると、参加者が勇気を持って発言してもらうのを待つのか、匿名の意見として書いてもらって回収するなどの方法を取るか(この場合、誰が発言したかはわからないけど、場にそういう意見があることは皆で共有できる)正直、迷います。
個人の成長が目的ならば、勇気ある発言・挑戦を奨励すべきだし、場のカオスを引き起こすのが目的なら、誰が発言者かということは関係ないから、後者の投票方式というのもありえると思ったりします。
もちろん、3のステップでダイナミックなカオスを引き起こすのは、本人が体験などにもとづいたストーリーを自分の口で話し、表明することだと思っています。
1.お互い、どんな人なんだろうという
相互探索モード
2.お互いに傾聴しあって、深まる
相互傾聴モード
3.違いを認めた上で違和感が繰り出される
カオスモード
4.違和感が出ている場でおきていることを全員で共有し探求する
探求モード
5.場の一致点が浮き上がり、各自がすべきことがみえる
アクションモード
〇〇モードというのは今、勝手につけている仮名称です。
さて、ワールドカフェなどカフェ的雰囲気で1~2のステップはうまくいきます。
問題は3以降の部分。 ファシリテーターが表面上、
「さぁ違和感を遠慮なく吐き出してください」と促したところで、うまくはいきません。参加者が、傾聴し仲良くなった相手に、”相手を傷つけないように” ”嫌われたくない” というメンタルモデルが発動してしまうからです。特に普段、発言・発信力の機会のない人には難しい部分。
私がファシリテーターだと仮定すると、参加者が勇気を持って発言してもらうのを待つのか、匿名の意見として書いてもらって回収するなどの方法を取るか(この場合、誰が発言したかはわからないけど、場にそういう意見があることは皆で共有できる)正直、迷います。
個人の成長が目的ならば、勇気ある発言・挑戦を奨励すべきだし、場のカオスを引き起こすのが目的なら、誰が発言者かということは関係ないから、後者の投票方式というのもありえると思ったりします。
もちろん、3のステップでダイナミックなカオスを引き起こすのは、本人が体験などにもとづいたストーリーを自分の口で話し、表明することだと思っています。