
光瀬龍 『百億の昼と千億の夜』 ←アマゾンへリンク これは新装版
問答無用で心に入ってしまう中学時代に心酔してしまった。
だから、あまり客観的にあれこれ書けない。
(いや、普段からあんまり客観的ではないけど。)
光瀬龍氏の作品は、SF、時代小説、等多岐に渡るのだが、
歴史や地理、社会が苦手なわたしは、光瀬氏のSFを狙って読んでいた。
短編の連作 (宇宙年代記) も多いけれど、
この 『百億の昼と千億の夜』 はこれひとつでしっかりまとまって、独立した話で、
それだけに別格という様だったのだ。
あとがきに
「私にとって最も大事な作品であると同時に、また、二度と手に取りたくない、目をそむけたくなる作品でもある」
とあるのが、なんとなく分かるような気がする。
それだけ、作者にとっても別格なのだろうか?
かつてはハヤカワ文庫に光瀬氏の本が何冊も収められていたが、
いまはこの 『百億の昼と千億の夜』 のみ、というのが寂しい。
(代わりにといってはなんだが、ハルキ文庫でいっぱい復刊されている。)
1973年に出た本なので、やはり古いところは所々ある。
でも、それに目をつぶって読ませる力が強い。
少しネタバレになってしまうが、
プラトンとシッタルダとイエスと阿修羅王が出てくる話だ。
ははあ、宗教にひと言申したいのかしら? (モハメッドは出てこない。)
その扱い方に、中学に入るまで親に連れられてプロテスタントの教会に行っていたわたしは
なんともびっくりしたのだ。
萩尾望都がマンガ化したのも有名だ。
多少変えてある部分もあり、どちらもよい。
萩尾氏の 『百億の昼と千億の夜』 の解釈もとても深い、と思う。
心にぽっかりと浮かぶ黒い穴、
わたしにとって、この話はそういう存在だ。
大事な穴だ。
ひゅうぅ、ひゅうぅ、と風が吹いて、砂漠の砂が飛んでいくような、
それとも寄せてはかえす波、その波打ち際、
そんなイメージ。
↑写真は昨年12月20日の月。 皆既月食の前日。
ちょっとイメージが違うなぁ。




















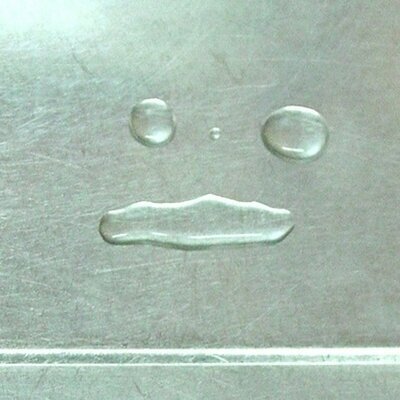





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます