
原著は2010年に書かれ、2012年に日本語訳が出版されて、2022年に文庫化されたされた。
わたしが読んだのは↑文庫版。
「言語は思考に影響を及ぼすか」というテーマは古典だと思う。
○○語が母語だと論理的な思考をする、みたいな雑談のネタなら聞いたことはあると思う。だが、学術的にそれなりに信頼のおける話なのか?というと急に難しくなる。
虹は何色あるのか?っていうのもトリビアだな。国/言語によって差があるのは有名だ。
言語による色の範囲の違いに注目して「言語は思考に影響を及ぼすか」を解いていこう、という本だ。
著者は頭のいい人なんだなあ、と思った。引き合いに出される事柄が幅広くてわたしには難しいと思えるから。
この分野に不案内なわたしにとって結論は予想されるものではなく、一体どこに行きたいのやら、と読みながら訝しく思ったよ。
「視覚、色覚」に対する興味というのはずっとある。でも日常生活を送っているときに表色系をもちいて厳密に示したりすることなどないから、わたしが青と言ったときにわたしが心に描いた色と 言われた相手が思い起こした色が同じだとはとても思えない。
網膜で受けた刺激が脳で何段階も処理されて「見える」けれど、脳の複雑なことを考えるとその処理に個人差がないとはとても思えない。
そもそも網膜上の錐体細胞のタイプに個人差があるしね。
その何段階もある脳での処理に 言語は影響するのだろうか? それはそもそも検証できるものなのか?
検証方法には感心した。そういう手段を用いれば影響の有無を知ることが出来るんだなあ、と。
「色」からのアプローチ以外に、名詞の「男/女/中性」の有無や言語による違いや、ある位置を伝えるときに前後左右を用いず東西南北で示す言語との比較も出てくる。
葡萄酒色の海に溺れ知的好奇心の迷宮に入り込んで迷うだけかと思いきや、出口へ向かう糸口を見出すのはさすがだ。
そして最後の段落には唸った。研究者の矜持を感じた。




















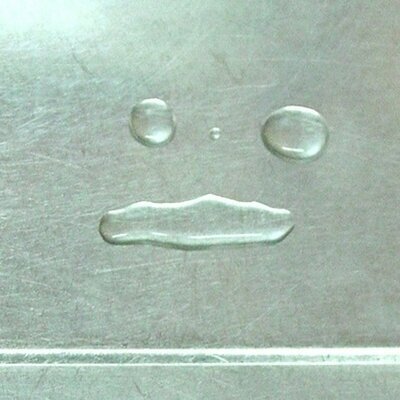





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます