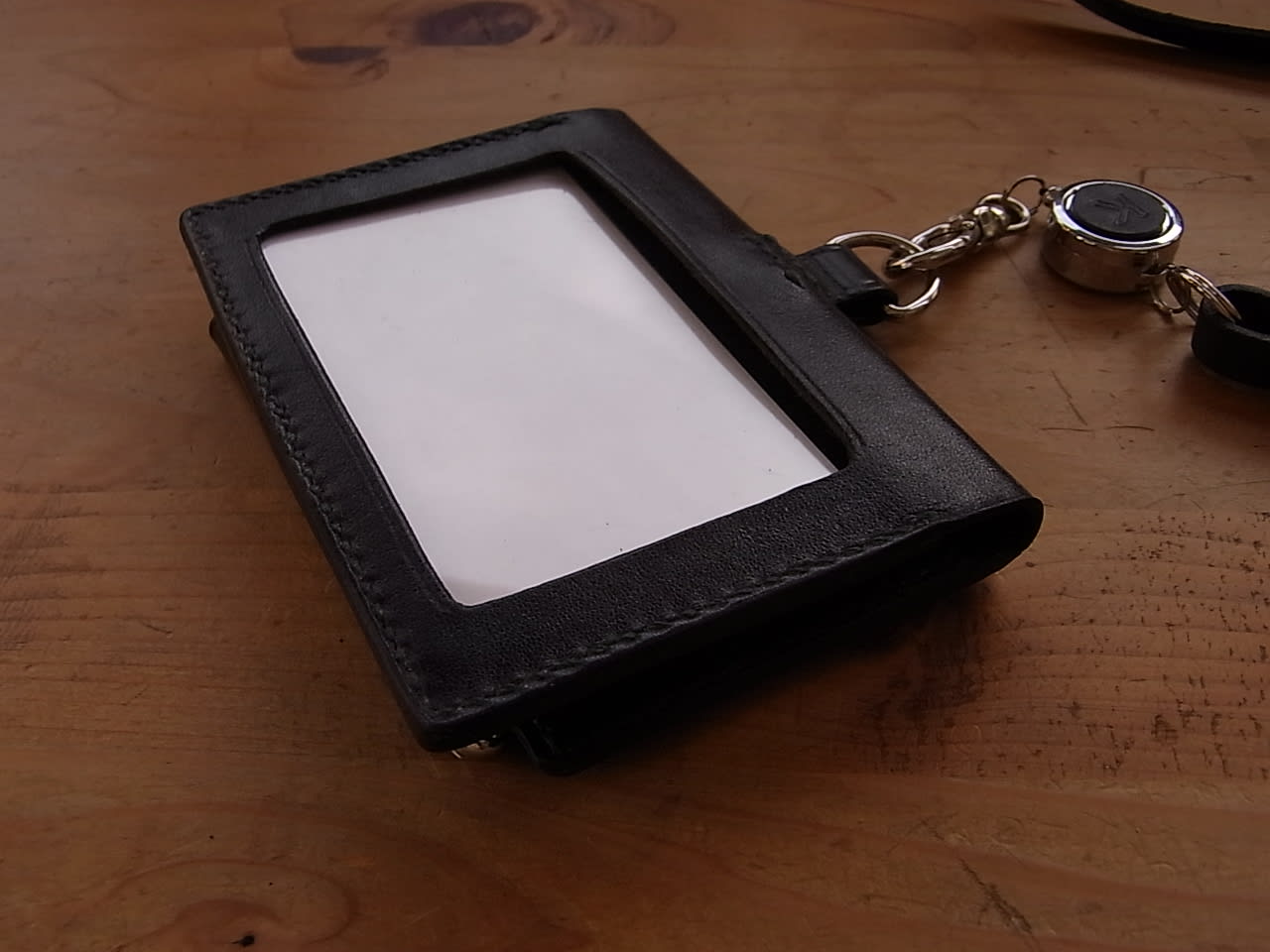日本橋本石町にある日本銀行本店の脇の通り(通称:日銀通り)はちょくちょく行き来するが、最近、気になることがある。
日銀の建物の窓を補修するために目張りしている真っ青な養生シートが目障りなのだ。
日本銀行本店は明治の建築界の重鎮である辰野金吾が設計、明治29年(1896年)竣工の重要文化財である(※)。
風格のある建物で、たまにファッション雑誌が海外の街角に見立ててモデルの背景として撮影に利用しているくらい。そういう建物に、なんでまたこんな下世話な色の養生シートを張らねばならないのだろう。
かつて我が家の水まき用のホースの選択にあたって、ホームセンターでのホースの色揃えの悪さについて問題提起したことがあるが(関連エントリ→
LINK)、その時のコメント欄でもm-louisさんからホースのほかに養生シート(ブルーシート)も色揃えが悪いとの指摘があった。
こうして重要文化財にあわせて見てみれば、色のセンスの悪さが一目瞭然である。
みんな不思議に思っていても一向に改善されないものが世の中にはいくつもあるが、この養生シートの色もそんな部類に属する。
養生シートが多色になれば、一般人のレジャーシートにも使えるはず。
花見の時など、場所取りで真っ青な養生シートが全面に広がって自分の仲間の場所がわかりにくいなんてことがあるが、5色ほどもバリエーションがあればずいぶんわかりやすくなるだろう。
運動会などの学校行事でも、クラスごとにシートの色を変えたりすればクラス対抗っぽさが強調できるし、なにより華やかになっていい。
ベーシックなものを多色展開するのが得意なユニクロのような発想をする建築資材メーカーが出てきてもよさそうなものだと思う。
(※)ちなみにGoogle Mapの航空写真で見ると日銀の建物は「円」の字になっているというのは有名なトリビアだが、竣工当時の¥の漢字は「圓」であり「円」を意識したものではないらしい。