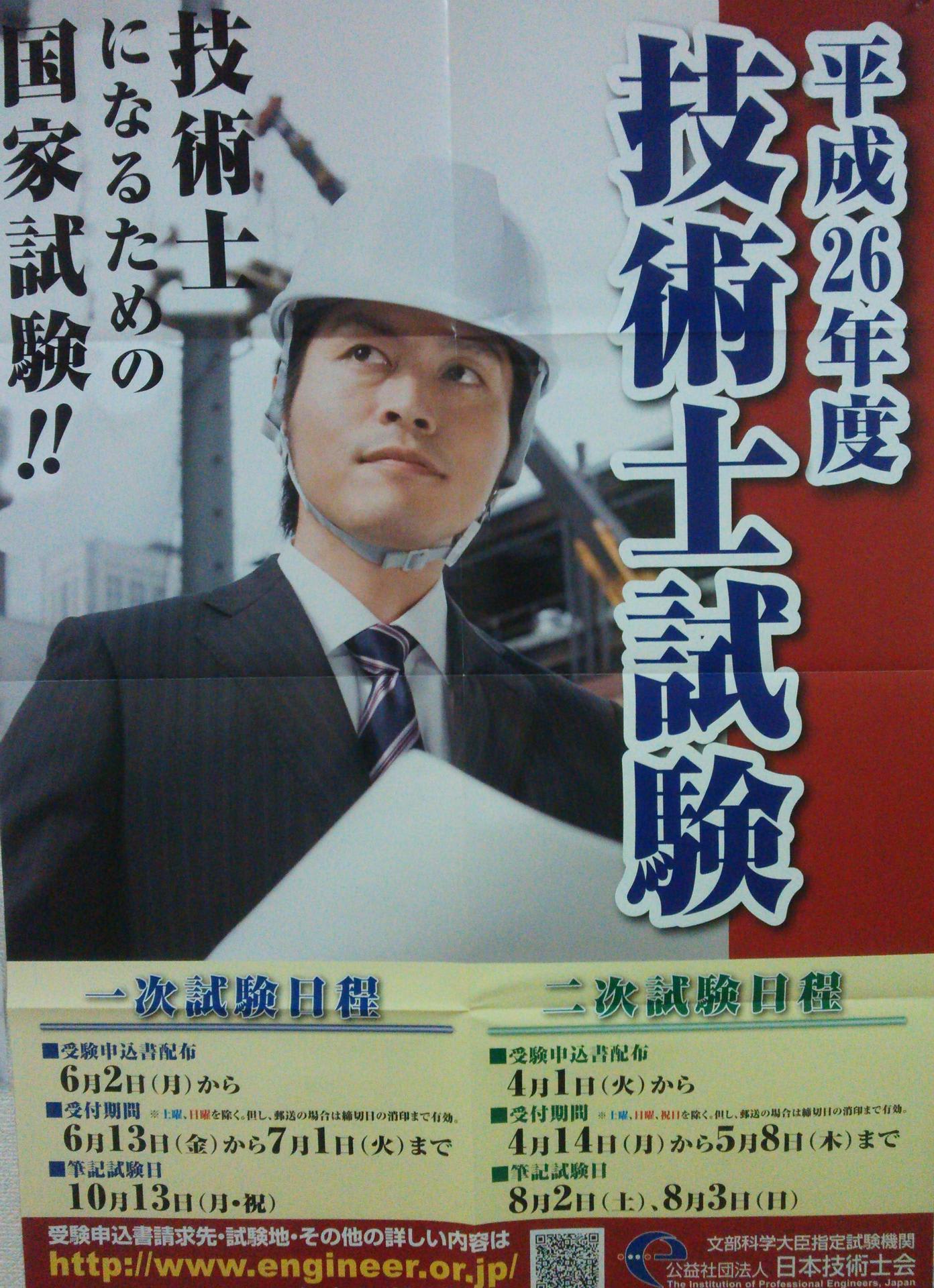国土交通省の社会資本整備審議会というところが道路構造物の老朽化への対策が不十分であり、本格的に対策を行う最後のタイミングであるとの提言を発表した。
以下はその提言のリンク(国土交通省サイト)である。
http://www.mlit.go.jp/road/road_fr4_000029.html
内容的には特に目新しいところは無く、自分のような構造物の技術者であれば数年前から明確に憂慮し、議論してきた内容とほぼ一緒といえる。
要約すると、
社会資本ストックの老朽化は加速し、今すぐに大規模な予算をもって補修・更新の整備に取り掛からないと大災害が発生する恐れがある。
しかし、特に小規模な地方自治体の技術者不足、認識不足、予算不足は深刻であり、危険なまま放置されている。
予算を増やし、メンテナンスのシステム化を推進していかなければならない。
といった内容だ。
私の所属する会社はメンテナンス業務の割合が大幅に増え続けている。しかし、実際に業務をこなしている人材は知識・技術力が乏しく、しかもただ仕事としてこなしてるだけなのだ。
国や町の安全なんて漠然すぎて頭に無く、ただ金を稼げればいいといった意識・資質の低さが目立っている。
過去の設計例にならって莫大な費用のかかる部材の交換を提案したり、メンテナンスのための仮設備の設置が損傷を生むような構造にしたりと、技術者が成熟していないのが現状だ。
地方自治体のみならず建設業界全体の技術者不足は深刻なのである。
現状を変えていくのは大変であり、いま莫大な予算が付いたとしても適切ではない補修設計や施工が増え、投資が無駄になったり最悪の場合損傷が悪化し危険性が増す恐れがある。
予算と技術者のバランスをとりつつ、官と民の双方の人材の育成が再優先課題だと考える。
以下はその提言のリンク(国土交通省サイト)である。
http://www.mlit.go.jp/road/road_fr4_000029.html
内容的には特に目新しいところは無く、自分のような構造物の技術者であれば数年前から明確に憂慮し、議論してきた内容とほぼ一緒といえる。
要約すると、
社会資本ストックの老朽化は加速し、今すぐに大規模な予算をもって補修・更新の整備に取り掛からないと大災害が発生する恐れがある。
しかし、特に小規模な地方自治体の技術者不足、認識不足、予算不足は深刻であり、危険なまま放置されている。
予算を増やし、メンテナンスのシステム化を推進していかなければならない。
といった内容だ。
私の所属する会社はメンテナンス業務の割合が大幅に増え続けている。しかし、実際に業務をこなしている人材は知識・技術力が乏しく、しかもただ仕事としてこなしてるだけなのだ。
国や町の安全なんて漠然すぎて頭に無く、ただ金を稼げればいいといった意識・資質の低さが目立っている。
過去の設計例にならって莫大な費用のかかる部材の交換を提案したり、メンテナンスのための仮設備の設置が損傷を生むような構造にしたりと、技術者が成熟していないのが現状だ。
地方自治体のみならず建設業界全体の技術者不足は深刻なのである。
現状を変えていくのは大変であり、いま莫大な予算が付いたとしても適切ではない補修設計や施工が増え、投資が無駄になったり最悪の場合損傷が悪化し危険性が増す恐れがある。
予算と技術者のバランスをとりつつ、官と民の双方の人材の育成が再優先課題だと考える。