いわゆる「ごみ屋敷」と呼ばれる家に暮らす高齢者について、10年間の追跡調査を東京都健康長寿医療センター研究所の井藤佳恵かえ医師が論文にまとめた。メディアなどの影響で、ごみ屋敷の住人は「迷惑な人」「変わった人」のレッテルが貼られてきた。
しかし、井藤氏は「私たち誰もが、ごみ屋敷の住人になり得る」とし、理解と適切な支援を訴える。(沢田千秋)
◆「ディオゲネス症候群」…認知症がより進行
身だしなみに気を使わず、掃除や片付けをせず、自宅に物を大量にため込んだりする行動を、精神医学の世界では「ディオゲネス症候群(DS)」という。
「ごみ屋敷」症候群とも呼ばれる。
井藤氏は、高齢者の精神疾患の専門家として、行政が「支援困難」と判断した人々と接する中で、適切な支援方法を求め、DSの研究に着手。
井藤氏は、高齢者の精神疾患の専門家として、行政が「支援困難」と判断した人々と接する中で、適切な支援方法を求め、DSの研究に着手。
国際的な判断基準を用い、これまで対応した270人のうち61人をDSと診断し、残りの209人との間で心身の状態や生活環境を比較した。
結果、DSの人々はそうでないグループより平均年齢は若いが、認知症がより進行していた。1年以内の死亡率も倍近く多かった。
不衛生で窮屈な暮らし、栄養状態などが影響している可能性がある。
◆身体機能の低下と関係か
認知症がDSを発症させるのか、DSとなって認知症が進むのか。
井藤氏は「その家がごみ屋敷になっていく過程を観察しないと分からない。
倫理的に許されず、どちらが先かは分からない」と話す。
ただ、身体機能の低下はDSと関係がありそうだ。
DSの人々には、トイレや歩行、入浴などに助けが必要な人が多かった。
ごみ出しや片付けができなくなり、次第に家が散らかっていくという。
「生活に助けが必要になった時、どこに言えばいいか分からない、助けてほしいと言えない、面倒な人付き合いをしたくないと思っていると、DSになるかもしれない。
誰にでも十分あり得る」と、
井藤氏は強調する。
元来、きれい好きだった人の家がごみ屋敷になっている様も見てきた。
元来、きれい好きだった人の家がごみ屋敷になっている様も見てきた。
「怠け者ではなく、人に迷惑をかけまいと頑張ってDSになる場合もある。
自分たちと同じ人間。
今は体力と生活のめりはりがあっても、老後の単調な毎日で、片付けのタイミングを逸しているうちに手に負えなくなることもある」(井藤氏)
◆「一緒に生きていく隣人としての目を向けて」
ごみ屋敷を前に、支援する側は「こうあるべきだ」と一方的な正義を押しつけ、住人が心を閉ざすケースは少なくない。
井藤氏が「最近いい例があった」と教えてくれた。
冷蔵庫を開けると大量のウジが出てくる一軒家に、若い男性ケアマネジャーが通い始めた。
冷蔵庫を開けると大量のウジが出てくる一軒家に、若い男性ケアマネジャーが通い始めた。
床の穴に板を貼ってふさぎ、少しずつ片付けを手伝った。
ドタドタ走るネズミを「唯一の家族」と言っていた70代の住人男性は、
曲がった腰が立ち、半年後にはごみ出しができるまでに回復した。
現状の介護制度で、男性ケアマネジャーの行為は無報酬のボランティア行為だったが、確実に住人男性を支援した。
現状の介護制度で、男性ケアマネジャーの行為は無報酬のボランティア行為だったが、確実に住人男性を支援した。
井藤氏は「住人が捨てられないものをごみと決め付けると、それは支援ではなく支配になる」と指摘。
「ごみ屋敷の住人は排除の対象ではなく、一緒に生きていく隣人としての目を向けてほしい。本人の思いに立った真の支援を」
と呼び掛けた。











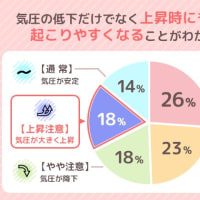







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます