<三権分立議会制自由民主主義議員内閣政府日本の大学や研究機関から軍民両用技術が共産党一党独裁政府国軍事研究大学機関に流出か>
::::::
9/25(金) 6:01配信
「中国軍関係者も「留学」できる日本の大学の大問題」
[筆者プロフィール] 平井 宏治(Hirai Koji) 1958(昭和33)年、神奈川県生れ。62歳。1982年、キヤノン株式会社入社。UBS証券会社、株式会社レコフ、UFJつばさ証券、PWCアドバイザリー株式会社で勤務後、2016年、株式会社アシスト代表取締役社長。1991年から、一貫してM&A助言ならびに事業再生支援業務を手掛け、成約実績は100件を超える。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。日本の尊厳と国益を護る会、セイコーエプソン、キリンビール、日本生命他などで講演多数。月刊誌「正論」「WILL」や専門誌フジサンケイビジネスアイ他に寄稿の他、ブルームバーグなどでもコメント多数。
:::::
(平井 宏治:日本戦略研究フォーラム政策提言委員・株式会社アシスト代表取締役)
中国では、大学が兵器の研究開発で重要な役割を担う。中国共産党人民解放軍(以下、中国軍)と直接、軍事技術開発契約を締結して、機密度の高い兵器などの開発や製造の一端を担うのが、北京航空航天大学、ハルビン工業大学、北京理工大学、ハルビン工程大学、南京航空航天大学、南京理工大学、西北工業大学だ。これら7校は国防七校と呼ばれ、国務院に属する工業・情報化部の国防科技工業局により直接管理されている。 国防七校の学生が、米国や日本の大学に留学をしている。また、中国軍の軍関係者も留学生になりすまして米国や日本の大学で研究をしている。彼らが、米国由来や日本由来の軍民両用技術を帰国後に軍事転用している疑惑が明らかになり、米国は本格的に取締に乗り出している。
日本学術会議は2017年3月、「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」とする昭和42年の同会議の方針を踏襲する「軍事的安全保障研究に関する声明」を決定した。日本の大学と研究機関は、自国の防衛技術の向上に協力しない。ところが、人民解放軍と関係の深い国防七大学から留学生を受け入れ、その上、もしかしたら日本由来の軍民両用技術を習得し、中国の軍備近代化に間接的に加担しているかもしれないという懸念に対して無防備だ。誰の目から見てもおかしい。 例えば、日本に対する外国によるミサイル攻撃を防ぐための防衛ミサイル開発に協力しない日本の大学と研究機関が、日本を標的にする中国のミサイル開発に研究開発を通じて間接的に加担する。こんなことは許されない。仮に、留学生になりすました中国軍関係者を受け入れていれば、反国家行為であり、厳しく処罰されるべきだ。
学術界は、外為法に定められた安全保障貿易管理を軽視し、大学と研究機関に適切な管理を徹底することを躊躇し、大学と研究機関にいる中国人留学生が、日本由来の軍民両用技術を外国で軍事転用することを見て見ぬふりをしてきたとの指摘に対し反論できるか。 日中大学間の軍民両用技術研究が中国で軍事転用されるリスクを認識し、十分な管理を行ってきたとは思えない。 国防七校出身や中国軍の軍人の留学を拒否できなければ、軍民両用技術が盗まれ留学生が帰国した後に軍事転用される可能性は常に存在する。 留学制度を見直す際に、2018年に成立した中国の国家情報法も考慮すべきだ。同法七条は「国民と組織は、法に基づいて国の情報活動に協力し、国の情報活動の秘密を守らなければならず、国は、そのような国民及び組織を保護する」とし、情報活動への協力を義務付けている。 文部科学省が、国家安全保障局経済班や財務省国際局、経済産業省、警察庁と都道府県警察の公安部門と連携し、留学生の身元確認を調査し、留学生として入国を許可・拒否できる仕組みを作ることが、自由民主主義陣営の一員として求められている。 しかし、論文発表、学会発表、特許公開等で公知化された技術は規制対象外となる。近年の軍事活動は、智能化戦争に変わっているが、そこでの優位性に結びつく先端的研究成果が制限なく公知化されることにより不特定多数に共有される。 基礎科学分野の研究活動も規制対象外だ。海外の大学や研究機関等との共同研究、留学生・研究者の受け入れ、研究資金の供与等を通じて、輸出管理対象となる以前に、懸念国やその企業等の関与下に(場合によっては独占的管理下に)置かれてしまうことがある。 兵器の研究開発で重要な役割を担う国防七校との共同研究では、厳格な技術管理と軍事転用防止策が必要だ。 大学・研究機関等から軍民両用技術の流出防止の方策は、輸出管理法である外為法では対応が難しい。輸出管理(技術移転)規制での立件が難しい中で、政府は新法を国会で成立させ、外為法で取り締まることが難しい穴を塞ぐことが必要だ。 大学や研究機関から軍民両用技術が懸念国に流出していることは、西側諸国の安全保障だけでなく、日本国の安全保障にも悪影響を及ぼす問題だ。日本由来の軍民両用技術の流失防止策を早急に作り上げ実施することは喫緊の課題だ。














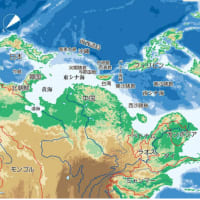


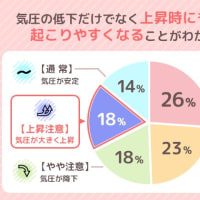
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます