
参議院選挙を振り返って
(候補者名は敬称略とさせていただきました。)
写真は本日朝の宿の近くの湯島聖堂で出会った孔子さま。東京ど真ん中のパワースポットでした。
緑茶会最初の取組みとなった第23回参議院選挙が終わった。結果は予想された通りの自民党大勝。投票率は52.61%強で、前回選挙(57.92%)を5.31%下回った。当日の有権者数は1億415万2589人で、棄権者数は前回選挙よりも553万人ほど棄権が増え、総数にすると4935万人強が棄権したことになる。自民党の比例得票数1846万票の2.67倍。もしこの人たちが投票に行き、前回並み投票率を上回っていたら自民党大勝はなかったかもしれない。
マスコミは投票日になっても「投票に行こう」との報道はほとんどやらず、自民党大勝予測ばかり。もはや投票しても無駄と言わんばかりの報道に終始していた。一方でネット選挙は確かに新しい層を投票行動や選挙活動に引き出した。山本太郎の当選や、当選はできなかったものの緑の党の三宅洋平の17万票は、ネット選挙の賜物だろう。しかし、大部分の有権者はネットの外にいた。昔ながらのドブイタ選挙がまだ強い。自民党、公明党の支持者は、いまでも政策ではなく地縁、共同体の意識で投票している。ネット選挙は、まだこれをくつがえせなかった。
選挙協力ほとんど皆無の代償
緑茶会が推薦した候補36名のうち当選したのは6名。選挙区選挙では16名を推薦し、埼玉の行田くに子と沖縄の糸数慶子の2人が当選。ほかは山形の舟山康江(みどりの風)のような接戦での敗北もあるが、ほとんどは大差の負けだった。その背景には、脱原発候補の複数乱立がある。緑茶会が呼びかけた「大合流」が実現できなかった結果だ。
たとえば新潟では、推薦の森ゆう子(生活の党)と渡辺英明(社民党)が票を争い、結果的に渡辺が森の当選を阻んだ。神奈川では露木順一(みどりの風)を推薦したが、結果的には畑野君枝(共産党)の当選を邪魔した。露木と畑野だけでなく、畑野と木村栄子(社民党)でも2人の得票をあわせれば4位に滑り込んでおり、この乱立はみすみす脱原発の一議席を失わせたことになる。社民党が脱原発候補の足を引っ張ることは予測されたが、緑茶会自身も神奈川では露木立候補を歓迎した経緯もあり、社民党だけを非難することはできない。
東京では、推薦した大河原雅子(無所属)が20万票と伸び悩んだが、脱原発票の大半を山本太郎や共産党の吉良に取られた結果だろう。生活者ネット出身の大河原は、公示直前に民主党公認を取り消され無所属での立候補となった。しかし無所属のメリットを生かせず、民主党票は鈴木寛(民主党)に奪われた結果となった。菅直人さんなど民主党現職議員の応援がプラスだったのかマイナスだったのか悩ましい。山本と吉良の勝利は、脱原発にとって大きな成果ではあるが、脱原発に実績ある現職を失ったマイナスを考えると、そう大きなプラスともいえない。
山形の舟山にしても、共産党が協力して3万票が加算されていたら当選したし、北海道の浅野(新党大地)も共産党、もしくはみんなの党との協力ができていたら2位に滑り込んだはずだ。
選挙区推薦の判断は再検討必要
愛知では緑茶会が推薦しなかった大塚耕平(民主党)が善戦し議席を守った。おそらくトヨタ労組の力だ。推薦した宇田幸正(減税日本)に脱原発の平山誠(みどりの風)、伊藤善規(社民党)などをあわせても、次点落選の共産党の得票数にも及ばず、推薦の判断が正しかったのかが問われる結果だった。
同じく長野の神津ゆかり(無所属)や兵庫の松本なみほ(緑の党)でもほとんど得票できておらず、推薦の判断もしくは支える体制の再検討が必要だろう。このほか西日本では、当選した沖縄の糸数慶子(無所属)と落選した熊本の松野(民主党)と大分の後藤(社民党)以外には、ほとんど脱原発候補者といえる候補が存在しなかった。これは西日本の脱原発運動の力が政治へのアプローチが弱いことの現れではないのだろうか。
「支持」だった宮城の岡崎トミ子(民主党)は5000票の僅差でみんなの党に破れた。岡崎の選対では原子力ムラ系の労組色が強く、脱原発を強く打ち出せず結果的に票を他党候補に奪われた。福島の金子恵美(民主党)も、自民党の森雅子が脱原発や再稼働を平然と主張しているのに、自身は「選対のしばり」で脱原発を鮮明にできず、結果はダブルスコアの大敗となった。民主党は大阪、岐阜など、このパターンの敗北と思われるものが多い。今後は、選対のしばりで政策協定を結べなかったり、脱原発の主張ができないような候補者に推薦や支持を出すか要検討である。
比例区の推薦の出し方も再検討
比例区候補者については20人を推薦したが、当選は4人だった。有権者はそもそも1人しか選べない。議員個人の情報は少なく、個人を選び、個人名で投票しようという緑茶会提案がどこまで実現できたのかは見えない。比例区候補の情報は選挙区以上に充実させる必要がある。
推薦候補を上げた政党は7つだが、党事情により「支持」となった共産党も含めると8つ。結局はまず政党で選ぶ人が多かったかもしれない。民主党候補については異論の声もあったが、相原久美子、神本美恵子、大島九州男の3氏は当選した。しかし緑茶会が「特推薦」としたツルネンマルテイは落選した。ツルネンを「特推薦」としたのは、民主党比例区は原子力ムラ候補と脱原発候補が入り交じっているからである。当選者を6~7名程度と想定し、当落線上にいるのがツルネンとすれば、ツルネンが当選すれば別の原子力ムラ候補の落選が決まると考えた。
原子力ムラ候補とは電力総連の浜野喜史(関西電力労組)と電機連合の石上俊雄(東芝労組)。ツルネンに票を集めれば、一人は落とせると踏んだのだが、残念ながら東芝労組を7番目で当選させてしまった。緑茶会の意図はまだ十分に理解されていない。
社民党やみどりの風、緑の党でも特推薦を示したが、いずれも戦略的なものだ。しかし三党とも得票が伸びず、社民党は1人、他の2党は議席獲得がならなかった。複数を推薦して特推薦をつけるよりも、絞り込んだ特推薦を推薦候補としてリスト化をはかる方がわかりやすかったかもしれない。
候補者を絞り込むことの困難さと重要性
東京選挙区では大河原雅子ではなく山本太郎が勝った。緑茶会の絞り込み方に問題があるのではないかという批判もおそらくあるだろう。もとより緑茶会の絞り込みが常に正しいとは限らない。一人に絞り込むことは悩ましく、絞り込まれなかった候補者や支持者との軋轢も生む。しかし、当選可能性を高めることを目的にしている以上、絞り込みは必要である。
しかし一人に絞り込んだからと言って、他候補が劣るとか問題ありと言う非難は避けて来た。すでに大河原を現職として推薦していたこともあり、山本太郎には東京選挙区への立候補を行わないようお願いをしたが、彼の方にも事情があり、最終的に東京選挙区立候補となったため推薦はできなかっただけである。大河原がいなければ当然推薦をしていただろう。彼もその事情はよくわかっており、彼からも緑茶会への非難やうらみごとは一切なかったと思う。
立候補の決断とそれを支援する側の思惑は、いろいろな場面や時間差や人間関係などの事情で交錯する。それが原因で永遠の決別や、犬猿の仲になったという事例も過去に見て来た。選挙によって、いろいろな市民運動の現場に亀裂と対立が持ちこまれてしまうことは本意ではなく、極力避けなければならない。
山本太郎だけではなく、共産党候補や緑の党の候補についても同じようなご指摘がある。たとえば三宅洋平は、彼の方から推薦辞退をしたものだ。山本太郎との連携や、彼なりの新しい選挙手法にとって緑茶会推薦はない方がやりやすいという判断があったのだと思っている。共産党候補も推薦に該当したが、党本部から「市民の団体との政策協定は一切結ばないという原則」との公式文書をいただき、弱い推薦である「支持」とした。生活の党と緑の党の候補者数名も、候補者判断での推薦辞退である。
自民党の圧倒的多数時代をどう乗り切るのか
さて最後のまとめ。選挙結果は最悪である。共産党の躍進、山本太郎の当選はあるが、これまで脱原発市民の活動をサポートしていた現職議員は、川田龍平以外ほぼ全員を失った。他議員は、気軽に議員会館の部屋取りを依頼し、勉強会に顔出してと頼める議員ではない。すでに昨年の総選挙でもたくさんの議員を失っており、今後の市民による国会活動は新たな拠点づくりから取組まねばならない。
まったく議席を取れなかった生活の党、みどりの風は存続が危ぶまれる。生活の党はまだ衆議院7名非改選2名で政党要件があるが、みどりの風は衆議院2名だけで政党要件も失う。社民党は1議席を確保したが、衆議院と非改選あわせて政党要件ギリギリの5名。全員を合わせれば16名だし、政策がほとんど似通っているのだから、一本化をいまから模索したほうが良いだろう。
それに比べれば民主党はまだ115名の議員がいるし、党内のロードマップの会や超党派の原発ゼロの会もある。みんなの党も重要だし、これからは公明党や自民党内の脱原発議員も重要なカギになるだろう。
まず原発再稼働の動きがやってくる。新規立地の上関原発や大間原発の建設の動きも復活し激しくなるだろう。山口県はあらためて田ノ浦の海の埋め立て許可を出してくるに違いない。中途半端でいろいろ批判のある原子力規制委員会は、それでも原子力ムラからは邪魔な存在だ。今後は委員の懐柔、差替えなど露骨な動きが出てくるのではないだろうか。原発輸出の動きはさらに強引になるだろうし、東電の延命と原発被害者の切り捨ても、3.11がなかったかのごとく進められるだろう。
しかし市民の側では、原発をきちんと終わらせるための原子力市民委員会が動き出しているし、電力自由化をめざす電力システム改革は国民の8割が支持している。国の政策に頼るのではなく、みずから道をつくろうという「市民電力」の動きも各地で活発化している。永田町だけは自民党に乗っ取られているが、日本全体ではまだ大きな転換点としての実践が着々と進み、政府の政策とぶつかりあっている。
今後の活路も、そこにある。次は3年後、衆参同日選と言われている。3年はあっという間である。緑茶会は今回の選挙では1億円の寄付も、10万人の有権者名簿も達成できていない。支部もまだ数えるほどしかない。それらの目標はいまも無意味化はしていない。3年の間には議会や首長などの自治体選挙もある。あくまで各地の人を主体としつつ、緑茶会として地方から人づくりをしながら、3年の間に目標を達成したい。
(候補者名は敬称略とさせていただきました。)
写真は本日朝の宿の近くの湯島聖堂で出会った孔子さま。東京ど真ん中のパワースポットでした。
緑茶会最初の取組みとなった第23回参議院選挙が終わった。結果は予想された通りの自民党大勝。投票率は52.61%強で、前回選挙(57.92%)を5.31%下回った。当日の有権者数は1億415万2589人で、棄権者数は前回選挙よりも553万人ほど棄権が増え、総数にすると4935万人強が棄権したことになる。自民党の比例得票数1846万票の2.67倍。もしこの人たちが投票に行き、前回並み投票率を上回っていたら自民党大勝はなかったかもしれない。
マスコミは投票日になっても「投票に行こう」との報道はほとんどやらず、自民党大勝予測ばかり。もはや投票しても無駄と言わんばかりの報道に終始していた。一方でネット選挙は確かに新しい層を投票行動や選挙活動に引き出した。山本太郎の当選や、当選はできなかったものの緑の党の三宅洋平の17万票は、ネット選挙の賜物だろう。しかし、大部分の有権者はネットの外にいた。昔ながらのドブイタ選挙がまだ強い。自民党、公明党の支持者は、いまでも政策ではなく地縁、共同体の意識で投票している。ネット選挙は、まだこれをくつがえせなかった。
選挙協力ほとんど皆無の代償
緑茶会が推薦した候補36名のうち当選したのは6名。選挙区選挙では16名を推薦し、埼玉の行田くに子と沖縄の糸数慶子の2人が当選。ほかは山形の舟山康江(みどりの風)のような接戦での敗北もあるが、ほとんどは大差の負けだった。その背景には、脱原発候補の複数乱立がある。緑茶会が呼びかけた「大合流」が実現できなかった結果だ。
たとえば新潟では、推薦の森ゆう子(生活の党)と渡辺英明(社民党)が票を争い、結果的に渡辺が森の当選を阻んだ。神奈川では露木順一(みどりの風)を推薦したが、結果的には畑野君枝(共産党)の当選を邪魔した。露木と畑野だけでなく、畑野と木村栄子(社民党)でも2人の得票をあわせれば4位に滑り込んでおり、この乱立はみすみす脱原発の一議席を失わせたことになる。社民党が脱原発候補の足を引っ張ることは予測されたが、緑茶会自身も神奈川では露木立候補を歓迎した経緯もあり、社民党だけを非難することはできない。
東京では、推薦した大河原雅子(無所属)が20万票と伸び悩んだが、脱原発票の大半を山本太郎や共産党の吉良に取られた結果だろう。生活者ネット出身の大河原は、公示直前に民主党公認を取り消され無所属での立候補となった。しかし無所属のメリットを生かせず、民主党票は鈴木寛(民主党)に奪われた結果となった。菅直人さんなど民主党現職議員の応援がプラスだったのかマイナスだったのか悩ましい。山本と吉良の勝利は、脱原発にとって大きな成果ではあるが、脱原発に実績ある現職を失ったマイナスを考えると、そう大きなプラスともいえない。
山形の舟山にしても、共産党が協力して3万票が加算されていたら当選したし、北海道の浅野(新党大地)も共産党、もしくはみんなの党との協力ができていたら2位に滑り込んだはずだ。
選挙区推薦の判断は再検討必要
愛知では緑茶会が推薦しなかった大塚耕平(民主党)が善戦し議席を守った。おそらくトヨタ労組の力だ。推薦した宇田幸正(減税日本)に脱原発の平山誠(みどりの風)、伊藤善規(社民党)などをあわせても、次点落選の共産党の得票数にも及ばず、推薦の判断が正しかったのかが問われる結果だった。
同じく長野の神津ゆかり(無所属)や兵庫の松本なみほ(緑の党)でもほとんど得票できておらず、推薦の判断もしくは支える体制の再検討が必要だろう。このほか西日本では、当選した沖縄の糸数慶子(無所属)と落選した熊本の松野(民主党)と大分の後藤(社民党)以外には、ほとんど脱原発候補者といえる候補が存在しなかった。これは西日本の脱原発運動の力が政治へのアプローチが弱いことの現れではないのだろうか。
「支持」だった宮城の岡崎トミ子(民主党)は5000票の僅差でみんなの党に破れた。岡崎の選対では原子力ムラ系の労組色が強く、脱原発を強く打ち出せず結果的に票を他党候補に奪われた。福島の金子恵美(民主党)も、自民党の森雅子が脱原発や再稼働を平然と主張しているのに、自身は「選対のしばり」で脱原発を鮮明にできず、結果はダブルスコアの大敗となった。民主党は大阪、岐阜など、このパターンの敗北と思われるものが多い。今後は、選対のしばりで政策協定を結べなかったり、脱原発の主張ができないような候補者に推薦や支持を出すか要検討である。
比例区の推薦の出し方も再検討
比例区候補者については20人を推薦したが、当選は4人だった。有権者はそもそも1人しか選べない。議員個人の情報は少なく、個人を選び、個人名で投票しようという緑茶会提案がどこまで実現できたのかは見えない。比例区候補の情報は選挙区以上に充実させる必要がある。
推薦候補を上げた政党は7つだが、党事情により「支持」となった共産党も含めると8つ。結局はまず政党で選ぶ人が多かったかもしれない。民主党候補については異論の声もあったが、相原久美子、神本美恵子、大島九州男の3氏は当選した。しかし緑茶会が「特推薦」としたツルネンマルテイは落選した。ツルネンを「特推薦」としたのは、民主党比例区は原子力ムラ候補と脱原発候補が入り交じっているからである。当選者を6~7名程度と想定し、当落線上にいるのがツルネンとすれば、ツルネンが当選すれば別の原子力ムラ候補の落選が決まると考えた。
原子力ムラ候補とは電力総連の浜野喜史(関西電力労組)と電機連合の石上俊雄(東芝労組)。ツルネンに票を集めれば、一人は落とせると踏んだのだが、残念ながら東芝労組を7番目で当選させてしまった。緑茶会の意図はまだ十分に理解されていない。
社民党やみどりの風、緑の党でも特推薦を示したが、いずれも戦略的なものだ。しかし三党とも得票が伸びず、社民党は1人、他の2党は議席獲得がならなかった。複数を推薦して特推薦をつけるよりも、絞り込んだ特推薦を推薦候補としてリスト化をはかる方がわかりやすかったかもしれない。
候補者を絞り込むことの困難さと重要性
東京選挙区では大河原雅子ではなく山本太郎が勝った。緑茶会の絞り込み方に問題があるのではないかという批判もおそらくあるだろう。もとより緑茶会の絞り込みが常に正しいとは限らない。一人に絞り込むことは悩ましく、絞り込まれなかった候補者や支持者との軋轢も生む。しかし、当選可能性を高めることを目的にしている以上、絞り込みは必要である。
しかし一人に絞り込んだからと言って、他候補が劣るとか問題ありと言う非難は避けて来た。すでに大河原を現職として推薦していたこともあり、山本太郎には東京選挙区への立候補を行わないようお願いをしたが、彼の方にも事情があり、最終的に東京選挙区立候補となったため推薦はできなかっただけである。大河原がいなければ当然推薦をしていただろう。彼もその事情はよくわかっており、彼からも緑茶会への非難やうらみごとは一切なかったと思う。
立候補の決断とそれを支援する側の思惑は、いろいろな場面や時間差や人間関係などの事情で交錯する。それが原因で永遠の決別や、犬猿の仲になったという事例も過去に見て来た。選挙によって、いろいろな市民運動の現場に亀裂と対立が持ちこまれてしまうことは本意ではなく、極力避けなければならない。
山本太郎だけではなく、共産党候補や緑の党の候補についても同じようなご指摘がある。たとえば三宅洋平は、彼の方から推薦辞退をしたものだ。山本太郎との連携や、彼なりの新しい選挙手法にとって緑茶会推薦はない方がやりやすいという判断があったのだと思っている。共産党候補も推薦に該当したが、党本部から「市民の団体との政策協定は一切結ばないという原則」との公式文書をいただき、弱い推薦である「支持」とした。生活の党と緑の党の候補者数名も、候補者判断での推薦辞退である。
自民党の圧倒的多数時代をどう乗り切るのか
さて最後のまとめ。選挙結果は最悪である。共産党の躍進、山本太郎の当選はあるが、これまで脱原発市民の活動をサポートしていた現職議員は、川田龍平以外ほぼ全員を失った。他議員は、気軽に議員会館の部屋取りを依頼し、勉強会に顔出してと頼める議員ではない。すでに昨年の総選挙でもたくさんの議員を失っており、今後の市民による国会活動は新たな拠点づくりから取組まねばならない。
まったく議席を取れなかった生活の党、みどりの風は存続が危ぶまれる。生活の党はまだ衆議院7名非改選2名で政党要件があるが、みどりの風は衆議院2名だけで政党要件も失う。社民党は1議席を確保したが、衆議院と非改選あわせて政党要件ギリギリの5名。全員を合わせれば16名だし、政策がほとんど似通っているのだから、一本化をいまから模索したほうが良いだろう。
それに比べれば民主党はまだ115名の議員がいるし、党内のロードマップの会や超党派の原発ゼロの会もある。みんなの党も重要だし、これからは公明党や自民党内の脱原発議員も重要なカギになるだろう。
まず原発再稼働の動きがやってくる。新規立地の上関原発や大間原発の建設の動きも復活し激しくなるだろう。山口県はあらためて田ノ浦の海の埋め立て許可を出してくるに違いない。中途半端でいろいろ批判のある原子力規制委員会は、それでも原子力ムラからは邪魔な存在だ。今後は委員の懐柔、差替えなど露骨な動きが出てくるのではないだろうか。原発輸出の動きはさらに強引になるだろうし、東電の延命と原発被害者の切り捨ても、3.11がなかったかのごとく進められるだろう。
しかし市民の側では、原発をきちんと終わらせるための原子力市民委員会が動き出しているし、電力自由化をめざす電力システム改革は国民の8割が支持している。国の政策に頼るのではなく、みずから道をつくろうという「市民電力」の動きも各地で活発化している。永田町だけは自民党に乗っ取られているが、日本全体ではまだ大きな転換点としての実践が着々と進み、政府の政策とぶつかりあっている。
今後の活路も、そこにある。次は3年後、衆参同日選と言われている。3年はあっという間である。緑茶会は今回の選挙では1億円の寄付も、10万人の有権者名簿も達成できていない。支部もまだ数えるほどしかない。それらの目標はいまも無意味化はしていない。3年の間には議会や首長などの自治体選挙もある。あくまで各地の人を主体としつつ、緑茶会として地方から人づくりをしながら、3年の間に目標を達成したい。










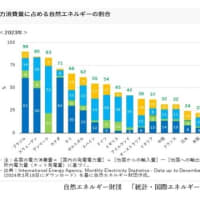


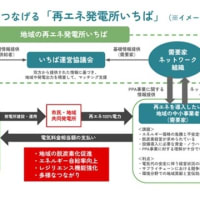






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます