先日の6月9日・10日 京都を旅行しました
しばらく旅行記が続きますが、どうぞお付き合いくださいませ
東京駅を出発する時は、雨でした

動き出したら、朝ごはんタイム
今日は「とんかつまい泉」のお弁当

まい泉のとんかつは、どうしてこんなに柔らかいのかしら
おいなりさんとのりまきも食べられて 幸せ
なんて言ってたら、あっという間に京都に着いちゃいました
まず最初に向かったのは、
真言宗 泉涌寺派 別格本山 雲龍院

南北朝時代は北朝の後光厳天皇の勅願により、竹巌聖皐を開山として応安5年(1372年)に創建されました
中庭がきれいです

後小松天皇、称光天皇など皇室の帰依を受けて発展したとされ、
北朝歴代の後尊牌が霊明殿に奉安されています

この石灯籠は、徳川慶喜が寄進したそうです

大石内蔵助が書いた「龍淵」

大石内蔵助の本心を表した書、と言われています
本堂「龍華殿」は、重要文化財です

現存最古の写経道場で、この日も写経が行われていました

テレビで有名になった「しき紙の景色」
障子を閉めると、左から「椿・灯籠・楓・松」が
まるで額に入れた絵のように見えます

悟りの窓

向こうに見えるのは、紅白の梅の木です
美しい景色が、季節を通して変化して見えるそうです
この龍の目が 追いかけてくるように見えるのだとか…

さて、この掛け軸は なぞなぞです
とあるお寺に落書きされた このひらがなだらけの文章の意味は何でしょう?

答えは「ちごのさけ いつも のみたや」
当時、お寺の修復などに携わる職人に、ちご(お寺の小僧さんみたいな身分かな?)が酒をふるまうことがあったらしいのですが、
「たまにじゃなくて 毎日飲みたいな~ 」
」
なんて思いながら、仕事をしていたのでしょうね
で、こちらの漢字は、なんと読むでしょう?

答えは、ずばり「禁酒」です
漢字の意味を追って、漢字の偏(へん)や旁(つくり)を組み合わせると
この2文字になりますよ
どの時代も、考えることは同じなんですね
この観音様に、とっても親近感が湧きました

体型が、です~(罰当たりですみません )
)
ね、醍醐もでしょ

おなかぽよぽよでも 気にしない~

で、もう おなかが空いてきちゃいました
明日は「大梵鐘とお昼ごはん」です
珊瑚と醍醐に ポチっとお願いします

にほんブログ村

しばらく旅行記が続きますが、どうぞお付き合いくださいませ
東京駅を出発する時は、雨でした


動き出したら、朝ごはんタイム
今日は「とんかつまい泉」のお弁当

まい泉のとんかつは、どうしてこんなに柔らかいのかしら

おいなりさんとのりまきも食べられて 幸せ

なんて言ってたら、あっという間に京都に着いちゃいました
まず最初に向かったのは、
真言宗 泉涌寺派 別格本山 雲龍院

南北朝時代は北朝の後光厳天皇の勅願により、竹巌聖皐を開山として応安5年(1372年)に創建されました
中庭がきれいです

後小松天皇、称光天皇など皇室の帰依を受けて発展したとされ、
北朝歴代の後尊牌が霊明殿に奉安されています

この石灯籠は、徳川慶喜が寄進したそうです

大石内蔵助が書いた「龍淵」

大石内蔵助の本心を表した書、と言われています
本堂「龍華殿」は、重要文化財です

現存最古の写経道場で、この日も写経が行われていました

テレビで有名になった「しき紙の景色」
障子を閉めると、左から「椿・灯籠・楓・松」が
まるで額に入れた絵のように見えます

悟りの窓

向こうに見えるのは、紅白の梅の木です
美しい景色が、季節を通して変化して見えるそうです
この龍の目が 追いかけてくるように見えるのだとか…

さて、この掛け軸は なぞなぞです

とあるお寺に落書きされた このひらがなだらけの文章の意味は何でしょう?

答えは「ちごのさけ いつも のみたや」
当時、お寺の修復などに携わる職人に、ちご(お寺の小僧さんみたいな身分かな?)が酒をふるまうことがあったらしいのですが、
「たまにじゃなくて 毎日飲みたいな~
 」
」なんて思いながら、仕事をしていたのでしょうね
で、こちらの漢字は、なんと読むでしょう?

答えは、ずばり「禁酒」です
漢字の意味を追って、漢字の偏(へん)や旁(つくり)を組み合わせると
この2文字になりますよ
どの時代も、考えることは同じなんですね

この観音様に、とっても親近感が湧きました

体型が、です~(罰当たりですみません
 )
)ね、醍醐もでしょ

おなかぽよぽよでも 気にしない~

で、もう おなかが空いてきちゃいました

明日は「大梵鐘とお昼ごはん」です

珊瑚と醍醐に ポチっとお願いします


にほんブログ村











 誕生日:2008年4月15日
うちに来た日:2008年6月5日
好きな食べ物:ヨーグルト・にぼし
嫌いな物:掃除機・コーヒー
眠い時は未だに指チューしま~す(人間の薬指限定です)
誕生日:2008年4月15日
うちに来た日:2008年6月5日
好きな食べ物:ヨーグルト・にぼし
嫌いな物:掃除機・コーヒー
眠い時は未だに指チューしま~す(人間の薬指限定です)
 うちに来た日 2009年6月2日
(たぶん珊瑚より年上だけど、弟です)
好きな物:牛乳
嫌いな物:何にも無いです!(納豆もOK)
超マイペースで食いしん坊で甘えん坊です
うちに来た日 2009年6月2日
(たぶん珊瑚より年上だけど、弟です)
好きな物:牛乳
嫌いな物:何にも無いです!(納豆もOK)
超マイペースで食いしん坊で甘えん坊です
 うちに来た日:2014年6月23日
食欲女王ですが超ビビりの女の子です
うちに来た日:2014年6月23日
食欲女王ですが超ビビりの女の子です
 うちの子になった日:2015年6月29日
ウィンクがチャームポイントの女の子です☆
うちの子になった日:2015年6月29日
ウィンクがチャームポイントの女の子です☆
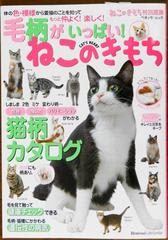
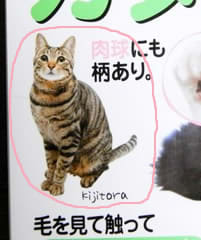
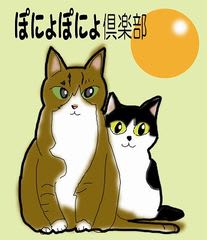 珊瑚・醍醐も入会しました☆
珊瑚・醍醐も入会しました☆




