「体験博物館 千葉県立房総のむら」内の「風土記の丘資料館」の第3展示室では、
トピックス展『千葉の行商―小さなからだと大きなカゴと―』が開催されていました

東京に隣接した千葉県では、 恵まれた自然を生かし、
農業 ・ 水産業などの豊かな生産物を食材として都市部へ提供してきました

千葉の行商のはじまりは大正期といわれています
第一次世界大戦後、東京都市部では人口増加により食糧難が生じ、
関東大震災後は青果物などの配給が途絶えたことから、
現金収入を得るために鉄道を利用して、行商へ出かけて行きました

また、1929年の世界恐慌の翌年の1930年に昭和恐慌が起こり、
農産物の価格が暴落し、農村は著しく困窮
自力で生計が立てられる行商は推奨されるようになりました

初めは男性も行商に出ていましたが、
効率良く田畑を耕す=男性、行商=女性となったようです

Nさんは朝5時前には家を出て、
2番列車で東京に行き、昼頃には帰宅していました
これを証明するのが当時の時刻表です

Nさんは1963年から1996年まで行商を行っていたそうです
今も成田線や京成線の駅には、行商台が残っています

地面から高さ60~75センチの台は「荷物の一時置き場」
女性のお尻の高さに合わせた寸法なのだそうです
行商のスタイル「手ぬぐいシャッポ」

手ぬぐいを帽子型に縫製したものです
手ぬぐいと違い、結び直す手間が省け、風に飛ばされにくかったそうです
かごは風呂敷で包まれ、多くが茶色・黒・濃紺色でした
ピーク時には約9000人を数え、夜明け前から大きな荷物を背負い、
駅のホームを一群となって移動することから「カラス部隊」などと呼ばれたこともありました

行商かごを作る「竹かご職人」も当時は大勢いたそうです

現在でも行商を続ける女性が2人いらっしゃいます
季節ごとの野菜は、お得意様に大変喜ばれているそうです

(本日の文章はトピックス展『千葉の行商―小さなからだと大きなカゴと―』のパンフレットより引用させていただきました)
行商かごを背負う体験が出来るそうですが
「おかあさん きっと ひっくりかえるでしょうね」(苺)

野菜や米などで、かごの重さは40キロ以上になることもあったとか
ダイビングの器材も重いけど、かごの方が2倍も3倍も重いなんて

苺もかごを背負って、行商に行ってみる?
きっといっぱい売れると思うんだけどなぁ

「房総のむら」のお話はこれでおしまいです
長期間に渡りお付き合いいただき、ありがとうございました
苺にポチッとお願いします

にほんブログ村
こちらにもポチッとお願いします

人気ブログランキング
トピックス展『千葉の行商―小さなからだと大きなカゴと―』が開催されていました

東京に隣接した千葉県では、 恵まれた自然を生かし、
農業 ・ 水産業などの豊かな生産物を食材として都市部へ提供してきました

千葉の行商のはじまりは大正期といわれています
第一次世界大戦後、東京都市部では人口増加により食糧難が生じ、
関東大震災後は青果物などの配給が途絶えたことから、
現金収入を得るために鉄道を利用して、行商へ出かけて行きました

また、1929年の世界恐慌の翌年の1930年に昭和恐慌が起こり、
農産物の価格が暴落し、農村は著しく困窮
自力で生計が立てられる行商は推奨されるようになりました

初めは男性も行商に出ていましたが、
効率良く田畑を耕す=男性、行商=女性となったようです

Nさんは朝5時前には家を出て、
2番列車で東京に行き、昼頃には帰宅していました
これを証明するのが当時の時刻表です

Nさんは1963年から1996年まで行商を行っていたそうです
今も成田線や京成線の駅には、行商台が残っています

地面から高さ60~75センチの台は「荷物の一時置き場」
女性のお尻の高さに合わせた寸法なのだそうです
行商のスタイル「手ぬぐいシャッポ」

手ぬぐいを帽子型に縫製したものです
手ぬぐいと違い、結び直す手間が省け、風に飛ばされにくかったそうです
かごは風呂敷で包まれ、多くが茶色・黒・濃紺色でした
ピーク時には約9000人を数え、夜明け前から大きな荷物を背負い、
駅のホームを一群となって移動することから「カラス部隊」などと呼ばれたこともありました

行商かごを作る「竹かご職人」も当時は大勢いたそうです

現在でも行商を続ける女性が2人いらっしゃいます
季節ごとの野菜は、お得意様に大変喜ばれているそうです

(本日の文章はトピックス展『千葉の行商―小さなからだと大きなカゴと―』のパンフレットより引用させていただきました)
行商かごを背負う体験が出来るそうですが
「おかあさん きっと ひっくりかえるでしょうね」(苺)

野菜や米などで、かごの重さは40キロ以上になることもあったとか
ダイビングの器材も重いけど、かごの方が2倍も3倍も重いなんて

苺もかごを背負って、行商に行ってみる?
きっといっぱい売れると思うんだけどなぁ


「房総のむら」のお話はこれでおしまいです
長期間に渡りお付き合いいただき、ありがとうございました

苺にポチッとお願いします
にほんブログ村
こちらにもポチッとお願いします
人気ブログランキング











 誕生日:2008年4月15日
うちに来た日:2008年6月5日
好きな食べ物:ヨーグルト・にぼし
嫌いな物:掃除機・コーヒー
眠い時は未だに指チューしま~す(人間の薬指限定です)
誕生日:2008年4月15日
うちに来た日:2008年6月5日
好きな食べ物:ヨーグルト・にぼし
嫌いな物:掃除機・コーヒー
眠い時は未だに指チューしま~す(人間の薬指限定です)
 うちに来た日 2009年6月2日
(たぶん珊瑚より年上だけど、弟です)
好きな物:牛乳
嫌いな物:何にも無いです!(納豆もOK)
超マイペースで食いしん坊で甘えん坊です
うちに来た日 2009年6月2日
(たぶん珊瑚より年上だけど、弟です)
好きな物:牛乳
嫌いな物:何にも無いです!(納豆もOK)
超マイペースで食いしん坊で甘えん坊です
 うちに来た日:2014年6月23日
食欲女王ですが超ビビりの女の子です
うちに来た日:2014年6月23日
食欲女王ですが超ビビりの女の子です
 うちの子になった日:2015年6月29日
ウィンクがチャームポイントの女の子です☆
うちの子になった日:2015年6月29日
ウィンクがチャームポイントの女の子です☆
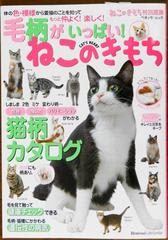
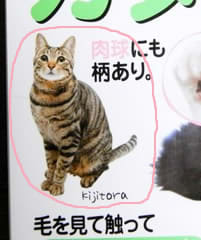
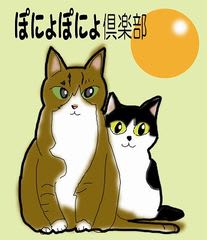 珊瑚・醍醐も入会しました☆
珊瑚・醍醐も入会しました☆




