こういう努力には、頭が下がります。
**********
貴重な二ホンミツバチの養蜂、きっかけは農家の愚痴挑戦10年超「後味すっきり上品な甘さ」
希少な在来種ニホンミツバチの養蜂に10年以上にわたって挑んできた兵庫県太子町の佐々木巧さん(71)から「今年は過去一番の量が採れた」と知らせが届いた。集まるハチミツの量はセイヨウミツバチの10分の1とされるが今年は150キロを収穫。野生の群れが減少する中、ノウハウを蓄積してきた佐々木さんに養蜂の現場を見せてもらった。
9月末、田園に囲まれた佐々木さん宅に近い空き地で胸ほどの高さの巣箱が並んでいた。箱の上を覆う板をめくると、地層のように重なる蜂の巣が光る。
「虫はいないし色も上出来。後味がすっきりした上品な甘さ」と佐々木さんが胸を張る。巣箱一つから採れるハチミツは約10キロ。1群当たり1万匹ともいわれるハチが半年かけて地道にためた自然の恵みだ。
「最近ハチがいない。イチゴの形が悪くなってきた」。2006年、近所の農家が愚痴をこぼすのを聞いて、佐々木さんはニホンミツバチの飼育を思い立った。手作りの巣箱を置いてみたが、最初の3年は巣に群れが入ることはなかった。
国内の養蜂業はセイヨウミツバチが中心。一方、減少が著しいニホンミツバチを増やそうと趣味で養蜂に取り組む人が各地に現れ、静かなブームともいわれている。佐々木さんも地域にいる養蜂の“先輩”からアドバイスを受け、ようやく10キロほどのハチミツが採れるようになった。夏の間は日に何度も巣箱を観察し、スズメバチなどの天敵を駆除して保護してきた。
10月からは蜂の巣を削り取って蜜を採取。遠心分離機は使わず時間をかけて蜜を落とす「垂れ蜜」という方法だ。セイヨウミツバチは特定の花に集中する性質があり強い甘みが特徴。ニホンミツバチは幅広い花の蜜を集めるため味わい深く「百花蜜」と呼ばれる。絞りかすも栄養豊富なため家庭で食用に活用しているといい、のどの乾燥予防や美容にも使うという。
飼育を軌道に乗せた佐々木さんは「1匹が一生に集められる蜜はスプーン1杯程度とされる。集団の中で役割を果たすハチの姿を見つめていると感謝の気持ちが湧いてくる。地域の農業にも貢献できればうれしい」と話していた。
希望者には500グラム3千円(税込み)で販売する。(小林良多)
9月末、田園に囲まれた佐々木さん宅に近い空き地で胸ほどの高さの巣箱が並んでいた。箱の上を覆う板をめくると、地層のように重なる蜂の巣が光る。
「虫はいないし色も上出来。後味がすっきりした上品な甘さ」と佐々木さんが胸を張る。巣箱一つから採れるハチミツは約10キロ。1群当たり1万匹ともいわれるハチが半年かけて地道にためた自然の恵みだ。
「最近ハチがいない。イチゴの形が悪くなってきた」。2006年、近所の農家が愚痴をこぼすのを聞いて、佐々木さんはニホンミツバチの飼育を思い立った。手作りの巣箱を置いてみたが、最初の3年は巣に群れが入ることはなかった。
国内の養蜂業はセイヨウミツバチが中心。一方、減少が著しいニホンミツバチを増やそうと趣味で養蜂に取り組む人が各地に現れ、静かなブームともいわれている。佐々木さんも地域にいる養蜂の“先輩”からアドバイスを受け、ようやく10キロほどのハチミツが採れるようになった。夏の間は日に何度も巣箱を観察し、スズメバチなどの天敵を駆除して保護してきた。
10月からは蜂の巣を削り取って蜜を採取。遠心分離機は使わず時間をかけて蜜を落とす「垂れ蜜」という方法だ。セイヨウミツバチは特定の花に集中する性質があり強い甘みが特徴。ニホンミツバチは幅広い花の蜜を集めるため味わい深く「百花蜜」と呼ばれる。絞りかすも栄養豊富なため家庭で食用に活用しているといい、のどの乾燥予防や美容にも使うという。
飼育を軌道に乗せた佐々木さんは「1匹が一生に集められる蜜はスプーン1杯程度とされる。集団の中で役割を果たすハチの姿を見つめていると感謝の気持ちが湧いてくる。地域の農業にも貢献できればうれしい」と話していた。
希望者には500グラム3千円(税込み)で販売する。(小林良多)
**********
ニホンミツバチ、大切にしなくてはいけません。佐々木さんの努力に感謝です。










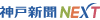




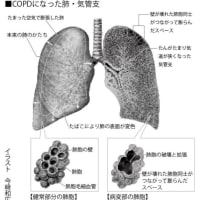
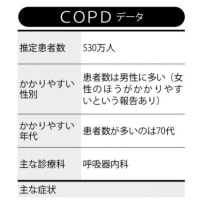




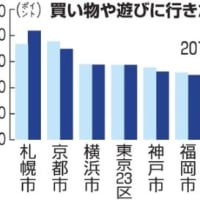





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます