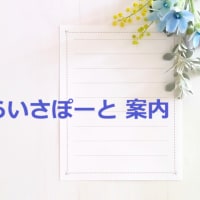先日ある支援スタッフの方に、支援についての相談をしました。
喫緊の課題として支援を考えるのか。
必ず訪れるであろう将来を見通して支援を考えるのか。
第三者に相談して意見を求めるということはとても大事なことです。
近い距離間で長く当事者と接していると、
その人の混乱する場を軽減するための手段を講じることに目を向けがちになってしまいます。
しかし本当にその対応が本人にとって将来プラスになるものなのか。
不調を何時間も引きずるものでない限り、当事者がその場で混乱をしたとしても、
そこからのスタートでプラスの経験値に近づけていく支援をする。
その場しのぎではない、将来の現実に安心して身を置けるよう、
関わるものとして、前向きの思考に切り替えることに気づかせていただきました。
どういうかたちで子どもの人生を未来に繋げていくのか。
はじめから正解があればいいのですが、
人は生き物、自然ですから、マニュアル通りにはいきません。
1+1が2にはならない。
だから自然を相手にする生活から遠ざかっている都市社会の中での現代人は、
子育てにおいても心労が絶えない不都合な社会なのかもしれません。
でも、1+1が2にならないので、面白いと思えれば良いのです。
正解ありきでなく、まずやってみて、次どうしたらいいのか。
これはやはり一人で抱え込まずに、
信頼できる人と共有しながら進めるのが、
何よりの前向きな道なのかなあと思います。