『赤軍PFLP・世界戦争宣言』(1971)
監督:若松孝二、足立正生
【作品概要】
内容(「キネマ旬報社」データベースより)
鬼才・若松孝二、足立正生監督らがレバノンの赤軍派、PFLPと共同し、パレスチナ解放のために闘うアラブゲリラの日常を描いたドキュメンタリー。未だ話題の人物である元赤軍リーダーの重信房子のインタビューなど貴重な映像を満載した1枚。
内容(「Oricon」データベースより)
若松孝二・足立正生がカンヌ映画祭の帰り道でレバノンのベイルートに向い、現地の赤軍派、PFLPと共同し、パレスチナ解放のために闘うアラブゲリラの日常に迫った伝説的ドキュメンタリー。世界革命のためのニュースフィルムであることを目指すため、既存の劇場公開を拒否し、全国各地の大学や工場などで独自の上映運動が行われた話題作。元赤軍リーダー、重信房子のインタビューなども収録した貴重な映像資料としても価値あり。

【感想レビュー】
うーん、これまたとにかく早口… 。
。
内容は、世界革命を目論む赤軍のプロパガンダ映画だ。とはいえ、私は何か特定の思想や概念に傾倒しているわけではなくて、足立正生という人物に興味を持って、資料として観ました。
ところどころ、赤軍メンバーの声だけのインタビューや重信房子の映像付きのインタビューも出てくるのだけど、これがもう何かあまりのお粗末さに、虚しさを覚える…。重信房子のインタビューは、とにかく早口で、内容は堂々巡っている感が否めない。
よく言われる事だけど、結局は物事の本質が見えなくなり、自己正当化の為の理論武装のように聞こえて仕方なかった。
また、本篇の中で全くの無音になる時間が幾つかあって、それは当時のベイルートの人々の生活や、パレスチナ解放のために闘うアラブゲリラの日常を訓練も含めて映し出していて、そこが無音なことと、現地の赤軍メンバーのスピーチが雄弁であるにも関わらず空虚なことが、何とも皮肉に思えて仕方なかった。
無音の編集であることに、どんな意図があるのか分からない以上、それは単に私の勝手な観方ではあるのだけど…。
本篇の最後に、パレスチナの歴史説明がある。古代カナン語で“勇敢なる兵士”を意味する。2000年前の侵略者ヘブライ人と闘い、ローマ帝政十字軍と闘い、近代シオニズムと闘い、4000年前から闘う人民だ、という説明。
そんな土地柄にちょっとお邪魔して一体何が出来るというのか…。
日本ではない何処かを目指し、自国を飛び出したが、結局、日本ではない何処かはあり得なかったわけだ。
社会学者の宮台真司氏は、『映画芸術』の記事の中で、足立映画のモチーフが、『「ここではないどこか」がありえないという不全感に満ちた世界を、②性と暴力で切り裂こうとするが、③結局は「ここ」に戻ってしまう、という循環形式にあることが分かり、私はハマった。』と言っている。
この “循環形式”を嫌というほど理解しているはずの足立正生監督が、何故この時、被写体と同化してしまったのか…その謎はまだ分からない。
『映画/革命』(著者:足立正生、聞き手:平沢剛)という河出書房新社から出ている書籍も読んでいるので、まだ読破出来ていないけど、何か新しい事が分かりますように…。
監督:若松孝二、足立正生
【作品概要】
内容(「キネマ旬報社」データベースより)
鬼才・若松孝二、足立正生監督らがレバノンの赤軍派、PFLPと共同し、パレスチナ解放のために闘うアラブゲリラの日常を描いたドキュメンタリー。未だ話題の人物である元赤軍リーダーの重信房子のインタビューなど貴重な映像を満載した1枚。
内容(「Oricon」データベースより)
若松孝二・足立正生がカンヌ映画祭の帰り道でレバノンのベイルートに向い、現地の赤軍派、PFLPと共同し、パレスチナ解放のために闘うアラブゲリラの日常に迫った伝説的ドキュメンタリー。世界革命のためのニュースフィルムであることを目指すため、既存の劇場公開を拒否し、全国各地の大学や工場などで独自の上映運動が行われた話題作。元赤軍リーダー、重信房子のインタビューなども収録した貴重な映像資料としても価値あり。

【感想レビュー】
うーん、これまたとにかく早口…
 。
。内容は、世界革命を目論む赤軍のプロパガンダ映画だ。とはいえ、私は何か特定の思想や概念に傾倒しているわけではなくて、足立正生という人物に興味を持って、資料として観ました。
ところどころ、赤軍メンバーの声だけのインタビューや重信房子の映像付きのインタビューも出てくるのだけど、これがもう何かあまりのお粗末さに、虚しさを覚える…。重信房子のインタビューは、とにかく早口で、内容は堂々巡っている感が否めない。
よく言われる事だけど、結局は物事の本質が見えなくなり、自己正当化の為の理論武装のように聞こえて仕方なかった。
また、本篇の中で全くの無音になる時間が幾つかあって、それは当時のベイルートの人々の生活や、パレスチナ解放のために闘うアラブゲリラの日常を訓練も含めて映し出していて、そこが無音なことと、現地の赤軍メンバーのスピーチが雄弁であるにも関わらず空虚なことが、何とも皮肉に思えて仕方なかった。
無音の編集であることに、どんな意図があるのか分からない以上、それは単に私の勝手な観方ではあるのだけど…。
本篇の最後に、パレスチナの歴史説明がある。古代カナン語で“勇敢なる兵士”を意味する。2000年前の侵略者ヘブライ人と闘い、ローマ帝政十字軍と闘い、近代シオニズムと闘い、4000年前から闘う人民だ、という説明。
そんな土地柄にちょっとお邪魔して一体何が出来るというのか…。
日本ではない何処かを目指し、自国を飛び出したが、結局、日本ではない何処かはあり得なかったわけだ。
社会学者の宮台真司氏は、『映画芸術』の記事の中で、足立映画のモチーフが、『「ここではないどこか」がありえないという不全感に満ちた世界を、②性と暴力で切り裂こうとするが、③結局は「ここ」に戻ってしまう、という循環形式にあることが分かり、私はハマった。』と言っている。
この “循環形式”を嫌というほど理解しているはずの足立正生監督が、何故この時、被写体と同化してしまったのか…その謎はまだ分からない。
『映画/革命』(著者:足立正生、聞き手:平沢剛)という河出書房新社から出ている書籍も読んでいるので、まだ読破出来ていないけど、何か新しい事が分かりますように…。


















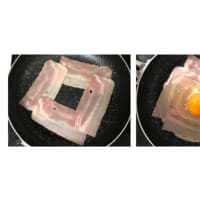

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます