『吉田喜重が語る小津安二郎の映画世界』(1993)
【作品概要】
吉田喜重監督が小津安二郎の映画の魅力を語る作品。1993年12月にNHK教育テレビで4夜連続で放映された映像を収録。
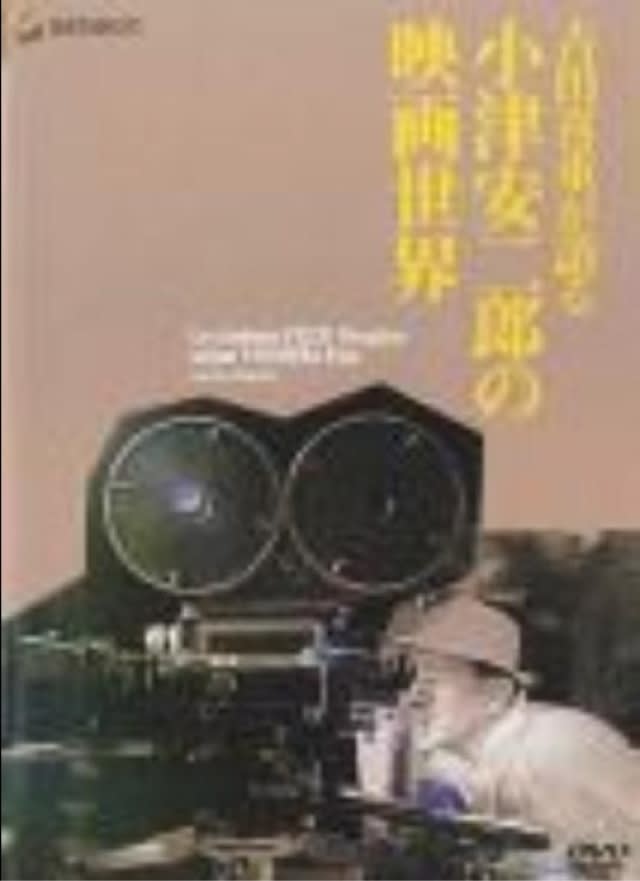
【感想レビュー】
すごい夢中になって観ました!
吉田喜重さんが小津作品について分析していて、作品の様々な場面を例に出して語るというスタイル。
実に哲学的なので、一瞬も気が抜けないのですが…

そこはDVDなので、何度も何度も見返したりして…
小津映画の観賞の旅も、レンタル出来るものはしたし、あとはネット配信やらになってしまい、どうも手続きがなぁ…ものぐさな私にはなぁ…などと思って、主な小津作品の初見はしたので、そろそろ吉田喜重さんの分析を知って、また観たら面白いかと思いこちらをレンタルしました。
よく云われる反復、モノローグのような会話、相似、色んな謎が実に解りやすく、面白くて、感激しながら観ました

なぜ小津作品に惹かれるのか、その理由の一端に触れた気がします。
【メモ・吉田喜重氏の言葉から】
 …事物の側から人間を眺める事であった。
…事物の側から人間を眺める事であった。
 小津さんはサイレント映画に拘った。
小津さんはサイレント映画に拘った。
映像が捉えるこの現実、この世界は
何の脈絡もない断片に過ぎないと考える小津さんには、トーキーによる筋道だったドラマはまやかしに思えたのである。
 小津さんは、映画を創りながらその映画をまやかしとして嫌った人であった。それにしても小津さんは、なぜこの現実、この世界を、なんの脈絡もない、無秩序なものと考えたのであろうか?
小津さんは、映画を創りながらその映画をまやかしとして嫌った人であった。それにしても小津さんは、なぜこの現実、この世界を、なんの脈絡もない、無秩序なものと考えたのであろうか?
おそらくカメラが捉える映像には、なんの筋道もなくストーリーがないことを知ったからであった。
それがいつしか、ありのままの現実、我々を包み込むこの世界もまた無秩序な存在でしかないことに気付いたのであった。小津的作品とは、こうした世界の無秩序さに耐えようとして自らの映画の中に何がしかの秩序を作り出そうとする試みであった。
 おそらく小津さんは、家族が家族として意識されない状態が正常であると考えた。
おそらく小津さんは、家族が家族として意識されない状態が正常であると考えた。
父が父であり、夫が夫であり、子が子であるうちは家庭は平穏無事であり、描く対象とはなり得なかった。
従って、家族とは何であるかを意識し、それを描くことは、とりもなおさず、家族の崩壊を描く事であった。こうした表現の矛盾は、小津さんにとって、映画を作る事の矛盾と深く重なり合っていた。この現実、この世界を映像に捉えたばかりに、そのあるがままの姿を乱してしまう。家族もまた、描く為に崩壊する。それが、小津さんが好んで家族、あるいは家族の崩壊をテーマにした理由であった。
 風の中の雌鶏
風の中の雌鶏
 『晩春』⇒『秋刀魚の味』
『晩春』⇒『秋刀魚の味』
軍艦マーチのシーンについて
それにしても軍艦マーチに合わせて敬礼し合う場面を我々はどのように理解すれば良いのだろうか。
戦争へのノスタルジーとは思えない。
むしろ、戯れに敬礼し合えるほど、あの時代が、はるか遠い過去の出来事となっている。
戦争が現実であった時には、人々はそれが何であったのかを知らず、戯れに語る事も出来なかった。このように人間とは、今生きている現実、この現在をついに知り得ない。
そして、過去は思い返す事はできても、それを我々は二度と生きる事は出来ない。このようにして、過去、現在から断ち切られ、ましてや未来を見通す事も出来ずに、それでも生きていけるのが人間であった。
 俗なる場面の後には、必ず聖なる場面を小津さんは用意する。
俗なる場面の後には、必ず聖なる場面を小津さんは用意する。
 反復しながらズラし、省略していく。
反復しながらズラし、省略していく。
それが、小津さん自身が望む人生の過ごし方であった。
反復しながら気付かぬうちにズレを起こし、やがて穏やかな死に至る。
 墓石の『無』は無常の『無』
墓石の『無』は無常の『無』
同時に『無秩序』の『無』
 小津さんが亡くなる前、病院で私に語った言葉が思い出される。
小津さんが亡くなる前、病院で私に語った言葉が思い出される。
『映画はドラマ。アクシデントではない。』
映画のドラマをまやかしとして考え、淡々とした出来事をアクシデントのように作品を創り続けたと思われる小津さんが、何故、そのように語ったのだろう。
おそらく、ドラマは映画の中にあったのではなかった。小津さんと映画の間にドラマがあった。カメラが映し出す映像を通して知ったこの世界、あるいは人間のその無秩序さに耐えようとして、小津さんは映画を創り続けた。
そのことが、小津さんのドラマであり、映画の喜びであった。
今の私にはそのように思われる。
【作品概要】
吉田喜重監督が小津安二郎の映画の魅力を語る作品。1993年12月にNHK教育テレビで4夜連続で放映された映像を収録。
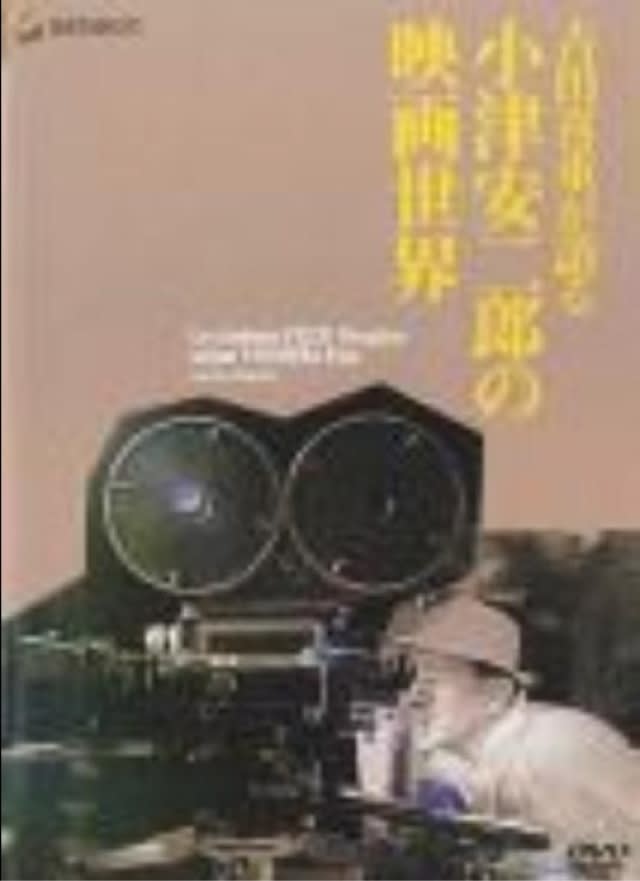
【感想レビュー】
すごい夢中になって観ました!

吉田喜重さんが小津作品について分析していて、作品の様々な場面を例に出して語るというスタイル。
実に哲学的なので、一瞬も気が抜けないのですが…


そこはDVDなので、何度も何度も見返したりして…

小津映画の観賞の旅も、レンタル出来るものはしたし、あとはネット配信やらになってしまい、どうも手続きがなぁ…ものぐさな私にはなぁ…などと思って、主な小津作品の初見はしたので、そろそろ吉田喜重さんの分析を知って、また観たら面白いかと思いこちらをレンタルしました。
よく云われる反復、モノローグのような会話、相似、色んな謎が実に解りやすく、面白くて、感激しながら観ました


なぜ小津作品に惹かれるのか、その理由の一端に触れた気がします。
【メモ・吉田喜重氏の言葉から】
 …事物の側から人間を眺める事であった。
…事物の側から人間を眺める事であった。 小津さんはサイレント映画に拘った。
小津さんはサイレント映画に拘った。映像が捉えるこの現実、この世界は
何の脈絡もない断片に過ぎないと考える小津さんには、トーキーによる筋道だったドラマはまやかしに思えたのである。
 小津さんは、映画を創りながらその映画をまやかしとして嫌った人であった。それにしても小津さんは、なぜこの現実、この世界を、なんの脈絡もない、無秩序なものと考えたのであろうか?
小津さんは、映画を創りながらその映画をまやかしとして嫌った人であった。それにしても小津さんは、なぜこの現実、この世界を、なんの脈絡もない、無秩序なものと考えたのであろうか?おそらくカメラが捉える映像には、なんの筋道もなくストーリーがないことを知ったからであった。
それがいつしか、ありのままの現実、我々を包み込むこの世界もまた無秩序な存在でしかないことに気付いたのであった。小津的作品とは、こうした世界の無秩序さに耐えようとして自らの映画の中に何がしかの秩序を作り出そうとする試みであった。
 おそらく小津さんは、家族が家族として意識されない状態が正常であると考えた。
おそらく小津さんは、家族が家族として意識されない状態が正常であると考えた。父が父であり、夫が夫であり、子が子であるうちは家庭は平穏無事であり、描く対象とはなり得なかった。
従って、家族とは何であるかを意識し、それを描くことは、とりもなおさず、家族の崩壊を描く事であった。こうした表現の矛盾は、小津さんにとって、映画を作る事の矛盾と深く重なり合っていた。この現実、この世界を映像に捉えたばかりに、そのあるがままの姿を乱してしまう。家族もまた、描く為に崩壊する。それが、小津さんが好んで家族、あるいは家族の崩壊をテーマにした理由であった。
 風の中の雌鶏
風の中の雌鶏 『晩春』⇒『秋刀魚の味』
『晩春』⇒『秋刀魚の味』軍艦マーチのシーンについて
それにしても軍艦マーチに合わせて敬礼し合う場面を我々はどのように理解すれば良いのだろうか。
戦争へのノスタルジーとは思えない。
むしろ、戯れに敬礼し合えるほど、あの時代が、はるか遠い過去の出来事となっている。
戦争が現実であった時には、人々はそれが何であったのかを知らず、戯れに語る事も出来なかった。このように人間とは、今生きている現実、この現在をついに知り得ない。
そして、過去は思い返す事はできても、それを我々は二度と生きる事は出来ない。このようにして、過去、現在から断ち切られ、ましてや未来を見通す事も出来ずに、それでも生きていけるのが人間であった。
 俗なる場面の後には、必ず聖なる場面を小津さんは用意する。
俗なる場面の後には、必ず聖なる場面を小津さんは用意する。 反復しながらズラし、省略していく。
反復しながらズラし、省略していく。それが、小津さん自身が望む人生の過ごし方であった。
反復しながら気付かぬうちにズレを起こし、やがて穏やかな死に至る。
 墓石の『無』は無常の『無』
墓石の『無』は無常の『無』同時に『無秩序』の『無』
 小津さんが亡くなる前、病院で私に語った言葉が思い出される。
小津さんが亡くなる前、病院で私に語った言葉が思い出される。『映画はドラマ。アクシデントではない。』
映画のドラマをまやかしとして考え、淡々とした出来事をアクシデントのように作品を創り続けたと思われる小津さんが、何故、そのように語ったのだろう。
おそらく、ドラマは映画の中にあったのではなかった。小津さんと映画の間にドラマがあった。カメラが映し出す映像を通して知ったこの世界、あるいは人間のその無秩序さに耐えようとして、小津さんは映画を創り続けた。
そのことが、小津さんのドラマであり、映画の喜びであった。
今の私にはそのように思われる。


















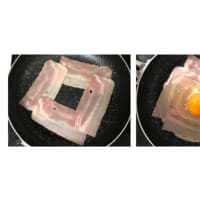

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます