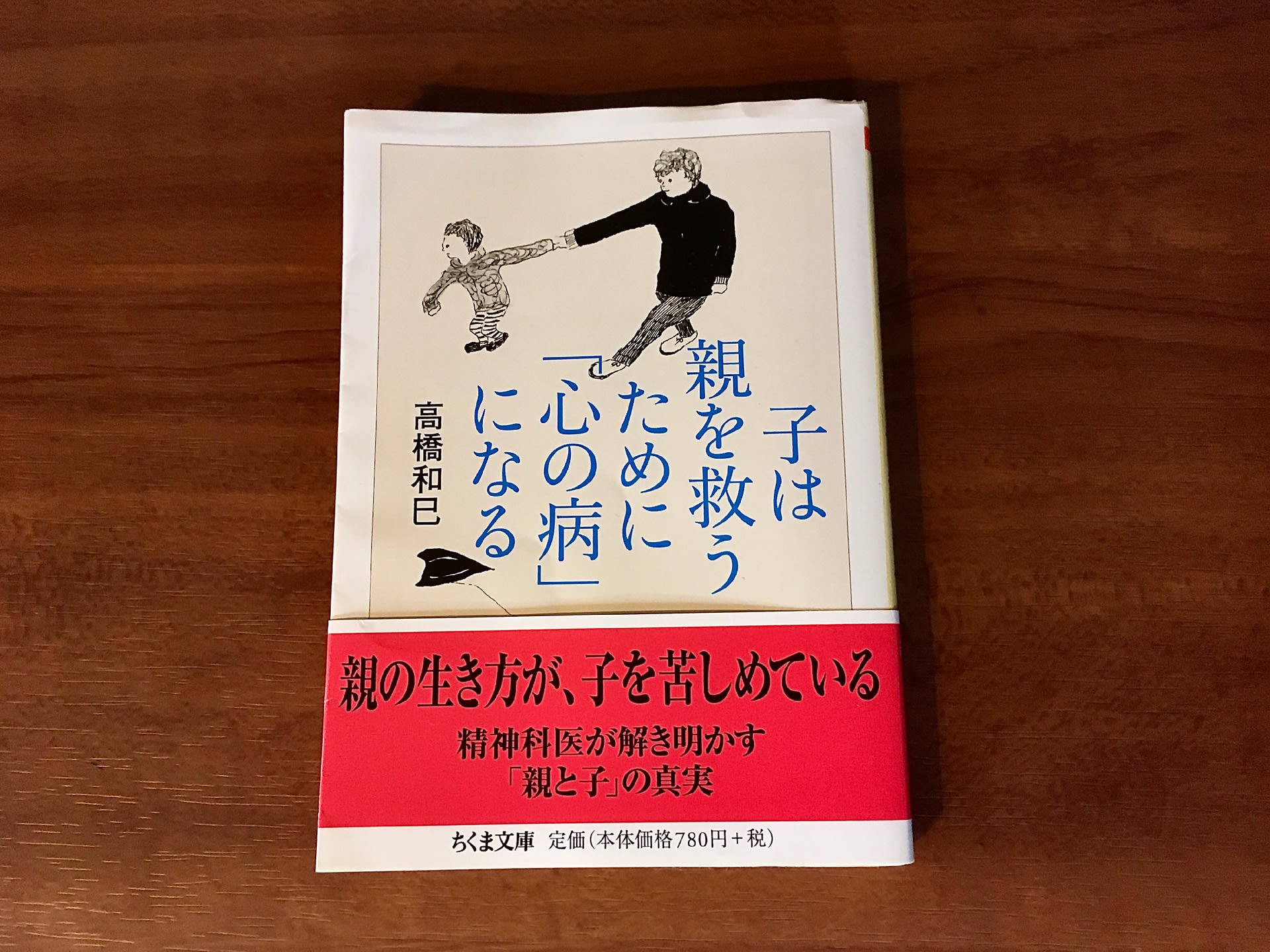
先週に引き続き、高橋和巳先生の本。
今回は、聴く技術ではなく、親子関係に焦点が当てられている。
刺さった。本当に、この本は、私の抱えている主題とかぶる。書きたいものがここにある、という感じでしょうか。
だから大事に、ゆっくり読んだ。もう一回読んだ方がいいだろうとも思う。
不登校、引きこもり、摂食障害、虐待、そして親に障害があり、実質的に親を持てなかった子の場合、それぞれのケースが紹介されています。
子は親の「心理システム」を丸ごとコピーして育つ。
生まれた時から備わっている体の保持機能は「生命システム」で、社会に適応するために学んでいく心の機能を「心理システム」とこの本では呼んでいます。
思春期になり、親の心理システムの矛盾を指摘する形で、子は親に反抗する。親の矛盾が大きいほどに反抗、そして病も大きくなる。
子の反抗としての病は、だから親が子のメッセージを受け取り、理解し、変わることで治る。
腑に落ちるのは、この「心理システム」には悪がないということ。
むしろ、親の「心理システム」に従わないことが悪。
最高の良いことは、どんな親の元でも生き延びること。
だから親から虐待を受けてきた子は、善悪が逆転してしまう。
親は悪くなくて、自分が悪いと思ってしまう。
コピーしてきたことが最高の良いこと、だった。なのに、今の自分はそうじゃない、そうできない状態がくる。
思春期に限らず遅れても必ずくる反抗や心の病は、親から自立するために通らなければならない葛藤の道。
言葉は不完全だから、心を表現し切ることができず、心の病や暴力というより強力な形でメッセージを全身で発している。
そこまでしないと分かってもらえないから。
そこまでして、分かってもらいたいから。演技ばかりさせられてきた偽りの自分ではなく、本当の自分を知って欲しい。
不満も怒りも悲しみも、そこに根がある。
私もそうだった。大人しくて、手のかからない子で、良い子。
それは、敏感に大人の空気を感じ取り、その価値観に合わせ、自分を変形までさせてしまうことができたから。
だから、本当の自分など育っていなかった。か弱く、ビクビクしたままで。
大学卒業後の進路を、恐怖のために決められなかったのもそのため。
本当は、自分を、もっと出したかった。出してもいいと、認められる場が欲しかった。
「書くこと」が、ずっと好きだったのも、そこでだけは自分を出せたから。それは今でもそうかもしれません。
自分の欲するままに、まずカウンセリングの場で、自分を出せるようになり、落ち着いていった。
認めてくれる、分かってくれる人たちと十分に出会い、十分に語り合った。それは、私の宝物。
一方で、発達障害の親を持つ場合、分かってもらう体験をあきらめなければならない。
そういう人たちを見てきた著者は、心の発達の最後の段階として「宇宙期」を提案する。
自分が、大多数の人が持つ「普通の心理システム」を持てなかったことを受け入れ、それでも自分はここに自分としてあると感じられるようになる段階。
常に存在感や実在感の希薄さに悩んできた人だからこそ辿り着ける世界なのかもしれません。
書店の棚には「精神世界」というジャンルがあり、一定のお客さんがいますが、もしかしたらそこのコアなお客さんたちに多いのかもしれません。
私の母は長女で、下に三人の妹と一人の弟がいました。母の母からよく言われたそうです。「あんたお姉さんなんだから、下の子の面倒を見なさい」と。当たり前のように。今でもこぼすくらいだから、よっぽど我慢していたのでしょう。十分に親に甘えることができず、たまに行く祖母のところが一番ほっとできたと。
そんな母の反抗期は結婚で表れたのかもしれない。何度もお見合いさせられたようですが、合わない人たちに「ノー」を差し出し続けた。なかなかうなずかない母に、母の父もカリカリしていたようですが、結局母は、「イエス」できる人(私の父)と出会って、その人を頼って家を継がず、東京に出た。孫(私の姉と私)ができて、両親はころっと変わったと言う。こんなにマメで優しい人たちだったっけ、と。母もまた、全身で両親を変える闘いをしたのかもしれません。
と書きながら私がうつになったのは、どこかでそんな我慢強く、自分を主張しない両親(とくに母)のコピーをぶち破る闘いにおいて、だったと思える。
あるいは両親のコピーの矛盾を突き、補完し、さらに進化するために。
「心の病」「不登校」「引きこもり」「摂食障害」「虐待」「発達障害」あるいは「うつ」と言葉にしてひとくくりにして、分かったつもりになってはいけない。
何も分かってはいない。一人一人は異なり、一つ一つに意味があり、分かろうと努力することで、こんがらがった糸をときほぐしていくことができるかもしれない。
そんな根気強い心の力仕事。人と人とが向き合い、存在を確認し合うこと。ていねいに心のかけらを拾い集め、今の自分にぴったりな新しい言葉という船をともに作っていくこと。
それがカウンセリングと文学の仕事だと僕は思う。カウンセリングと文学は、僕の心の奥ではつながっています。つながるようになった、と言ってもいいのかもしれない。
最後に、この本のエピローグからの引用です。
カウンセリングとは、その人の生き方とか、悩みを聞くのではなく、「存在」感を聞く、「存在」を確認するものである。その結果として、生き方を変えたり、そのまま安心したりする。しかし、それは単なる結果である。
存在は、この世界に生まれてから、社会的な存在感を身につけて生きるようになっても、それをもてないまま生きていても、あるいは、そこを抜け出してからでも、変わらずにずっと「ある」。人と人とが向かい合って、この「存在」を確認しあう作業、それがカウンセリングの本質である、そう、私は患者さん(クライアント)から教えてもらった。 273ページ10行~274ページ3行
高橋和巳 著/ちくま文庫/2014
今回は、聴く技術ではなく、親子関係に焦点が当てられている。
刺さった。本当に、この本は、私の抱えている主題とかぶる。書きたいものがここにある、という感じでしょうか。
だから大事に、ゆっくり読んだ。もう一回読んだ方がいいだろうとも思う。
不登校、引きこもり、摂食障害、虐待、そして親に障害があり、実質的に親を持てなかった子の場合、それぞれのケースが紹介されています。
子は親の「心理システム」を丸ごとコピーして育つ。
生まれた時から備わっている体の保持機能は「生命システム」で、社会に適応するために学んでいく心の機能を「心理システム」とこの本では呼んでいます。
思春期になり、親の心理システムの矛盾を指摘する形で、子は親に反抗する。親の矛盾が大きいほどに反抗、そして病も大きくなる。
子の反抗としての病は、だから親が子のメッセージを受け取り、理解し、変わることで治る。
腑に落ちるのは、この「心理システム」には悪がないということ。
むしろ、親の「心理システム」に従わないことが悪。
最高の良いことは、どんな親の元でも生き延びること。
だから親から虐待を受けてきた子は、善悪が逆転してしまう。
親は悪くなくて、自分が悪いと思ってしまう。
コピーしてきたことが最高の良いこと、だった。なのに、今の自分はそうじゃない、そうできない状態がくる。
思春期に限らず遅れても必ずくる反抗や心の病は、親から自立するために通らなければならない葛藤の道。
言葉は不完全だから、心を表現し切ることができず、心の病や暴力というより強力な形でメッセージを全身で発している。
そこまでしないと分かってもらえないから。
そこまでして、分かってもらいたいから。演技ばかりさせられてきた偽りの自分ではなく、本当の自分を知って欲しい。
不満も怒りも悲しみも、そこに根がある。
私もそうだった。大人しくて、手のかからない子で、良い子。
それは、敏感に大人の空気を感じ取り、その価値観に合わせ、自分を変形までさせてしまうことができたから。
だから、本当の自分など育っていなかった。か弱く、ビクビクしたままで。
大学卒業後の進路を、恐怖のために決められなかったのもそのため。
本当は、自分を、もっと出したかった。出してもいいと、認められる場が欲しかった。
「書くこと」が、ずっと好きだったのも、そこでだけは自分を出せたから。それは今でもそうかもしれません。
自分の欲するままに、まずカウンセリングの場で、自分を出せるようになり、落ち着いていった。
認めてくれる、分かってくれる人たちと十分に出会い、十分に語り合った。それは、私の宝物。
一方で、発達障害の親を持つ場合、分かってもらう体験をあきらめなければならない。
そういう人たちを見てきた著者は、心の発達の最後の段階として「宇宙期」を提案する。
自分が、大多数の人が持つ「普通の心理システム」を持てなかったことを受け入れ、それでも自分はここに自分としてあると感じられるようになる段階。
常に存在感や実在感の希薄さに悩んできた人だからこそ辿り着ける世界なのかもしれません。
書店の棚には「精神世界」というジャンルがあり、一定のお客さんがいますが、もしかしたらそこのコアなお客さんたちに多いのかもしれません。
私の母は長女で、下に三人の妹と一人の弟がいました。母の母からよく言われたそうです。「あんたお姉さんなんだから、下の子の面倒を見なさい」と。当たり前のように。今でもこぼすくらいだから、よっぽど我慢していたのでしょう。十分に親に甘えることができず、たまに行く祖母のところが一番ほっとできたと。
そんな母の反抗期は結婚で表れたのかもしれない。何度もお見合いさせられたようですが、合わない人たちに「ノー」を差し出し続けた。なかなかうなずかない母に、母の父もカリカリしていたようですが、結局母は、「イエス」できる人(私の父)と出会って、その人を頼って家を継がず、東京に出た。孫(私の姉と私)ができて、両親はころっと変わったと言う。こんなにマメで優しい人たちだったっけ、と。母もまた、全身で両親を変える闘いをしたのかもしれません。
と書きながら私がうつになったのは、どこかでそんな我慢強く、自分を主張しない両親(とくに母)のコピーをぶち破る闘いにおいて、だったと思える。
あるいは両親のコピーの矛盾を突き、補完し、さらに進化するために。
「心の病」「不登校」「引きこもり」「摂食障害」「虐待」「発達障害」あるいは「うつ」と言葉にしてひとくくりにして、分かったつもりになってはいけない。
何も分かってはいない。一人一人は異なり、一つ一つに意味があり、分かろうと努力することで、こんがらがった糸をときほぐしていくことができるかもしれない。
そんな根気強い心の力仕事。人と人とが向き合い、存在を確認し合うこと。ていねいに心のかけらを拾い集め、今の自分にぴったりな新しい言葉という船をともに作っていくこと。
それがカウンセリングと文学の仕事だと僕は思う。カウンセリングと文学は、僕の心の奥ではつながっています。つながるようになった、と言ってもいいのかもしれない。
最後に、この本のエピローグからの引用です。
カウンセリングとは、その人の生き方とか、悩みを聞くのではなく、「存在」感を聞く、「存在」を確認するものである。その結果として、生き方を変えたり、そのまま安心したりする。しかし、それは単なる結果である。
存在は、この世界に生まれてから、社会的な存在感を身につけて生きるようになっても、それをもてないまま生きていても、あるいは、そこを抜け出してからでも、変わらずにずっと「ある」。人と人とが向かい合って、この「存在」を確認しあう作業、それがカウンセリングの本質である、そう、私は患者さん(クライアント)から教えてもらった。 273ページ10行~274ページ3行
高橋和巳 著/ちくま文庫/2014


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます