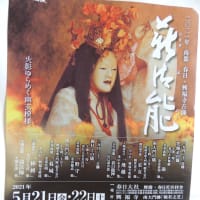かえる石・・・元興寺


日本伝承大鑑から→「現在、奈良の元興寺に安置されているかえる石であるが、この石は、江戸時代に奇石にまつわる話を集めた『雲根志』に“大阪城の蛙石”として載せられるほど有名な石である。その形状が蛙に似ているということで名付けられたことは疑いないところであるが、その数奇な歴史は、名前に似合わず非常に恐ろしいものである。
元々この石は、河内の川べりにあった殺生石であったと言われている。それを豊臣秀吉がたいそう愛でて、大阪城に運び込んだところから因縁が生じる。大阪城落城の際に、亡くなった淀君の遺骸をこの蛙石の下に埋めたとされ、そのために淀君の怨念がこの石に籠もったと言われる。
その後時を経てこの石はいつの間にか大阪城の乾櫓の堀をはさんだ対岸に置かれる。ここからさらに陰惨な言い伝えが広まっていく。この石のあるところから大阪城の堀に身を投げる者が後を絶たない。あるいはこの石の上に履き物を置いて身を投げる者が多く出る。さらには大阪城の堀に身を投げて死んだ者は必ずこの石のそばに流れ着くとも言われるようになる。要するに、大阪城の堀で死ぬ者は必ずこの蛙石に絡んでいくことになり、まさに死の象徴と言うべき都市伝説に発展した、実に不吉な石となったのである。
そのような石がなぜ奈良の元興寺に安置されたのかは詳細はつまびらかではないが、第二次世界大戦の折の混乱で行方不明となったものが、昭和31年(1956年)に元興寺に引き取られたことが記録に残っている。名の通った寺院の境内に置かれるとあって、当然過去の悪因縁やそれにまつわる諸霊の供養をおこなっているとのこと(現在でも毎年7月7日に供養が執り行われている)。それ以降は、災いをもたらす石のイメージのを払拭がなされ、“福かえる”や“無事かえる”の語呂合わせで、元興寺の縁起物として位置付けられている。」
<雲根志うんこんし>
「博物書。木内石亭著。1773年(安永2)から1801年(享和1)にかけて三編一六巻を刊行。岩石や鉱物・化石・石器など約二〇〇〇品を分類して記載したもの」(出典 三省堂大辞林 第三版)
「木内石亭(1724‐1808)の著した石に関する博物誌。前編,後編,および三編があり,それぞれ1773年(安永2),79年,1801年(享和1)に大坂で出版され,その後版を重ねた。鉱物,岩石,化石のほか,石器などが図示され,性状,産地,成因などが記されている。石亭は現在の滋賀県草津市の人で,名は重暁。博物学のうち,とくに石について興味をもち,多くのものを収集した。当時の知識人との交流も深く,日本各地のものを集めることができた。」(出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版)