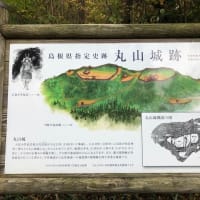7. 弘法大師
弘法大師とは空海の諡で空海の死から86年後の延喜21年(921年)第60代醍醐天皇の御代に贈られたものである。
空海は、遣唐使の留学僧として唐へ留学し、「真言密教」という仏教の教えを持ち帰って「真言宗」という仏教の宗派を開いた。
空海が留学僧として唐に向かう時、嵐にあって漂着している。この時の出来事は非常にドラマチックであった。
7.1. 空海、唐へ出港
空海は延暦23年(804年)7月6日に第一六次遣唐使(大使は藤原葛野麻呂)の長期留学生として、橘逸勢や最澄達と肥前国松浦田浦から四隻で出港した。
遣唐使船の寸法は全長25m、幅8mくらいであったと推定されている。
一隻に凡そ120人が乗り込んだ。船の進路は風まかせで、風向きが逆になると船端から櫓を出して漕がなねればならなかった。
最澄は還学生(遣唐使に同行する学問僧)、空海は留学僧(滞在期間20年間)、として旅立った。
最澄はエリート僧であり桓武天皇から、遣唐使のメンバーとして任命され、公費で通訳付きであった。
一方空海は志願して遣唐使に加えてもらったが、渡航費は自費だったという。
ではなぜ、空海はそこまでして入唐したかったのか?
大日経
空海は修行中に密教の根本教典である「大日経」にであった。
空海は読むことによって大日経の理論は理解できた。しかし空海にも解せない部分があった。
大日経には仏と融合してそこから求めるものを引き出すという方法が書かれているが、その部分は秘密であるので、印を結ぶなどの所作を必要とした。
しかし、こればかりは手を取って伝授されることが必要があったのである。
空海は、この大日経に置ける不明の部分を解くために入唐を決意したのであった。


遣唐使船が大海に出た二日目に嵐にあい、四隻はちりぢりになった。
空海や貴族の橘逸勢は藤原葛野麻呂遣唐大使の第1船に乗り、最澄は第2船に乗船していた。
途中第3船と第4船は遭難し、唐にたどり着いたのは第1船と第2船のみであった。
空海の乗った船は、大きく航路を逸れて貞元20年(804年)8月10日、福州長渓県赤岸鎮巳(現在の福建省霞浦県寧徳赤岸)に漂着した。
最澄が乗船した第2船は9月1日に明州鄮県(現在の浙江省寧波市)に到着している。
7.2. 上陸までの混乱
浜に着くと、藤原葛野麻呂大使はすぐに村の役人(県令)に連絡をとらせた。
当時の中国は、直接海岸から上陸するのは禁止されており、許可をまたなければならなかったのである。
県令は「自分には許可を出す権限がない」と、皇帝と直結した役人がいる福州へ使いを出した。
その間、空海たちは上陸が許されないまま、船の中で二ヶ月過ごすことになった。
密輸船、または海賊船賊船として追い払われてもしかたがない状況に遣唐使船はあった。
結局、赤嶺鎮の役人は「福州へいってくれ」と一行を追い出した。
空海の漂着地が福建省寧徳市霞浦県赤岸村と特定されたのは
長い間、日本の研究者や真言宗関係者たちは空海入唐の足跡を探し求めてきた。
史料に残された漂着の地「赤岸」がどこであるかを特定するため、中国沿海地域を調査した。
しかし、中国の各地に赤岸という地名があり、さらに、時代の変遷と共に地名も変わった可能性があり、漂着地を特定することは極めて困難な作業だった。
1980年代に、ハルビン師範大学歴史学科の游寿教授が空海漂着の地が寧徳市霞浦だという手がかりを発見した。
游教授はもともと霞浦の出身で、歴史と考古学に通じた中国でも著名な歴史学者であり書道家だった。
1981年、游教授は平安時代初期に編纂された勅撰史書『日本後記』に、空海が唐の貞元20(紀元804)年の8月10日、福州長渓県赤岸鎮南の湾に着き、県令の胡延沂らが出迎えたことが記されているのを発見した。
そこで彼女は霞浦に戻り、赤岸で調査を行ってこれをまとめた論文を発表すると、日本で大きな注目を集めた。1984年、高野山大学の静慈圓教授をはじめとする「空海・長安への道」訪中団が、赤岸で調査を行った。湾を調査し、船に乗ったり、文献を照合した後、一行はそのまま西安に向かった。帰国後、静教授は『空海・長安への道』という報告をまとめ、そこで現在の寧徳市霞浦県赤岸村こそが紀元804年に空海が漂着した場所であると断定した。
長渓県赤岸鎮で上陸を拒否され、観察使のいる福州へ回航することを指示された遣唐使船は再び外洋へ出て福州を目指した。
福州は闽江(福建省最大の河川)の河口から約30Km遡ったところにある。
観察使はこの船を密輸船と判断し、着くやいなや船に乗っている百二十人を船からひきずりおろした上、船を封印してしまった。
遣唐使一行は、上陸することも、船にもどることも許されず、砂の上で生活しなければならなかった。
「私は日本国の大使である」と大使の藤原葛野麻呂は主張したが役人はとりあわなかった。
大使ならば、当然持っているはずの国書や印符を持っていなかったからである。
藤原葛野麻呂は観察使の閻济美に何度も手紙を書いた。しかし、それは徹底的に無視された。
文章によってその人を知ろうとする中国人にとって、大使の文章はあまりにもたどたどしすぎたからである。
現在でも、いかに中国語に熟達した人でも、中国の名文豪以上の文章を中国語で書ける日本人はいない。無理もない話である。
困り果てた遣唐大使は空海に代筆を頼んだ。
空海、名文「大使の為に福州の観察使に与うるの書」を書く。
「賀能(葛野麻呂の別名)啓す」からはじまるこの文章を要約すると、
まず大唐の聖帝に会いに来た自分たちの旅がいかに過酷であったかを訴えた。
漂流中に船員が鯨に喰われそうになる危機一髪の場面や漂流中に見たのは「天水」つまり空と海だけの風景だった、と読んでいる人を感動させるように、戯曲形式に書いている。
そして、唐と日本はいまさら印符など必要がないほど心が通じ合っており、唐と日本の天子は友好を結んでいるのに、その天子の使いでやって来た自分たちを信じないのは何事かと責める。
しかし、あなた達官吏からみれば、自分たちを疑うのは役目がら当然のことである、と相手を尊重する。
だが、自分たちを海中におくのは何ごとだと再び責める。
まだ天子の徳酒を飲んでもいないのに、このような仕打ちをうける理由はないと。
そして、自分たちを長安へ導くことが、すべての人々を唐の皇帝になびかせることではないかと書いた。
空海が書いた手紙を読んだ閻济美は、その表現力に驚き、すぐに上陸の許可を出し、待遇を一変させた。
長安へ定った使者が「大使を同賓として待遇せよ」とい皇帝からの命令を伝えると、さらに待遇は激変した。
そして大使一行は、長安からの勅使の迎えを待って出発することになった。
遣唐使船に乗船してきた百二十人の中から、大使と随行員ニ十数人が選ばれ長安へ向かうことが許された。
残りの人々は船を修復し、その後海路北上し、大使らが帰国の途につく明州(現在の浙江省寧波市)で待たなければならなかった。
ところが観察使は長安に行く組のメンバーに空海を選ばなかったのである。
理由は分からないが、空海の文章力に惚れきった閻济美が自分の文章秘書として欲しくなったのではないかと、言われている。
空海は再度書面で一行に加えてくれるように申請しなければならなかった。
空海は再び嘆願書を書く。
「日本国留学の沙門空海、啓す」という文で始まるこの書は、自分は非才ながら国から新しい学問を勉強することを荷わされてきている。いろいろ事情もあるだろうが入京させて欲しいと、間済美の人徳にすがっている。
空海は無事入京組に入り、長安に旅立つ。
11月3日に福州を出発し、長安までの2,400Kmの旅に出た。
長安に着いたのは12月23日であった。
中日交流の場「空海大師記念堂」
1993年4月、福建省霞浦県人民政府は日本の高野山真言宗総本山金剛峰寺と中日両国が共同で空海大師記念堂を建設する協定書を締結した。
これは高野山真言宗総本山宗務総長の新居祐政氏が中日文化交流の場、参拝する場として記念堂の建設を提案したことにより実現した。建設費用は中国側と日本側のそれぞれで負担し、1993年5月に着工、翌94年5月に竣工した。
記念堂は霞浦県を中心に空海研究を行なっている「寧徳市霞浦空海研究会」が管理している。
会長の陳永遷さんは空海について、「霞浦の人々は1200年前と同じように友好的な存在であり、1つの善良で友好的な文化の使者だと考えている」と話す。それを象徴するように現在でも地域住民は真言宗の信者ではないものの、敷地内に建立された空海像に線香を手向け、祈りを捧げている。

「寧徳市霞浦空海研究会」の人たちは次のように空海の手紙を驚きながら評価する。
「この手紙は漢文について深い教養を持っていることを示しながら、読んでいる人を感動させるように、戯曲形式に書いている。
また中国人は誠実で温かい心をもっていると持ち上げる心憎さがある。
わずか30歳の、それも日本人の男性がこれほど教養のある手紙が書けたなんてとても信じられない」

この赤岸に漂着した時の様子が「弘法大師行状絵巻」にも描かれている。
①嵐のなかの船。船の寸法は全長25m、幅8mくらいであったと推定されている。船の左端に座っているのが空海と思われる。

②国家使節である証明書をもっていないため、遣唐大使が福州の長官に嘆願書を書いている図

③図の右半分は、遣唐大使の書いた嘆願書を、福州の長官が投げ捨てる様子。左半分は空海が遣唐大使の代筆をする様子

④空海が書いた嘆願書を長官がみて、その表現力に驚き、感心する。

<続く>