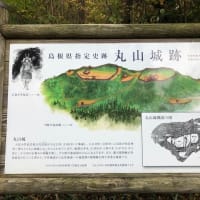7.3. 長安での空海
遣唐使一行が長安へ入ったのは延暦23年(804年)(唐歴貞元20年)12月23日であった。
長安は現在の陝西省西安である。
長安は西周、秦、前漢、新、前趙、前秦、後秦、西魏、北周、隋、唐の11王朝が都した中国第一の古都である。
唐の最盛期には人口は100万以上であったという。運河や鉄道がなかった時代の盆地型城郭都市では生活必需品の供給面からみて人口100万が限界らしい。
世界史上屈指の規模の城郭都市で東西9.7km、南北8.6kmの巨大な壁(この城壁の幅は約6mあったらしい)によって囲まれ、12の城門を持っていた。
その町の真ん中を、北から南へ向かって朱雀大路がまっすぐ走り、皇城を背にして左側(東)五十五坊、右側(西)に五十五坊の、やはり壁によって囲われた坊があった。
左街は主に屋敷や公官庁などがあり、右街には民家や食堂、酒楼、商店などがひしめいていた。
東西に大きな市があり、人々はみなその市で買い物をしていた。
大使一行は宣陽坊にあった公館に落ち着いた。
本来ならば、国立の迎賓館であった鴻臚寺(こうろじ)にその宿舎をかまえるはずであったが、満員だったようである。
2月10日に大使達は長安を去った。
この間、正月の公式儀礼、さらに今上皇帝徳宗の崩御にともなう葬儀に急遽参列している。
大使が帰国の途についたあと、都に残った空海たちは宣陽坊から右街の延康坊にある西明寺に移った。
空海はそこを拠点にして長安の街を歩きまわった。
長安にいる間、空海は北インド出身の般若三蔵と牟尼室利三蔵から、サンスクリット語とインド哲学を学んでいる。
また空海は長安の名士たちと、色々と交流している。
空海が、二本の手と二本の足、そしてもう一つ口で筆をくわえ、五本の筆を一緒に動かして書を書いたという伝説から、「五筆和尚」というニックネームも付けられたという。
空海は、詩と書によって社交界のスターであったという。

密教
釈迦の死後、密教という仏教思想がインドで生まれた。
釈迦はこの世の苦しみは、人々が様々な欲望を持つことから生まれると教え、すべての欲望を自分の力で断つことをことを求めた。しかしこの釈迦の教えは実践の難しいものであった。
多くの人々は、現世利益を求めて神や仏にすがり、欲望を自分の力で断つことはできなかった。商利の追求を貪りとした釈迦の教えは、釈迦の死後しだいに力を失っていった。
こうした中、密教という新しい仏教思想がインドで生まれた。
密教は自然の状態を清らかなものとし、人間の欲望を否定しない、新しい世界観に満ちていた。
密教はその中心に宇宙の真理をあらわす大日如来という仏を置いた。大日如来は無限なる宇宙の全てであると同時に、宇宙に存在している全てに内在していると説いた。つまり、仏も人も本質的には同じであり、ひとつであるというのである。
その宇宙は人間や万物に、釈迦が感じたような、飢餓や老病苦死をのみを与えるのではなく、むしろ限りなく労り深いものであると教え、独自の世界を創りあげた。
その蜜教は、7世紀に入って、大日経と金剛頂経という画期的な経典を生み出す。
大日如来という宇宙の絶対的心理ともいうべき形而上学的な最高仏を教主としたこの二つの経典は、インドのまったく異なった地方で別々に生まれ、中国に伝わり、恵果(中国唐代の密教僧で日本の空海の師)の所で合流した。
空海、恵果から灌頂を受ける
空海が密教の正統なる相承者である青龍寺の恵果を訪問したのは貞元21年(805年)の5月末か、6月の初めだといわれている。長安に着いて半年の月目が流れていた。
空海をひと目見た恵果は、大いに歓迎し、満面に微笑をたたえて、
「われ先きより、汝の来れるを知り、相待つこと久し、今日、相まみゆるは大いに好し大いに好し。報命つきなんとするに、付法する人なし。必ずすべからく速やかに香花を弁じ、灌頂担に入るべし」といった。
一面識もなかった32歳の青年僧に密教の法の全てをすぐに授けるというのである。
恵果は空海の噂を聞いており、その特殊な能力を感じており、会うことを心待ちにしていたのかもしれない。
恵果には当時でも千人を超す弟子がいたと伝えられる。その中でわずか一人にしか伝えなかった金剛界、胎蔵界の両部を一気に授けたいと、師が自ら申し出たのである。
6月上旬に胎蔵界の灌頂を受け、7月上旬には金剛界灌頂を、8月上旬には伝法阿闍梨位の灌頂を受けた。
灌頂とはもともと国王が即位のときに四大海(天下のこと)の水を汲んで帝王の頭上にそそいで四大海の掌握を意味した儀式であるが、密教では如来の五智を象徴する五瓶の水を用いて秘密法門の印可伝綬、師資相承、密教の法灯を伝える儀式であり、阿闍梨とは密教に精通した偉大なる師という意味である。
空海はわずか三ヶ月でその全てを授かった。
師の恵果が1年後に死去(享年61)している、ことを考えれば、空海はぎりぎりのタイミングで、入門する幸運に恵まれたことになる。
密教を伝授され、最新の唐の文化を吸収した空海はその成果を早く日本に伝えたかった。
空海はわずか2年で留学を止め日本に帰る準備を始める。20年分として持参していた留学費用は、密教の経典を写し、諸々の書籍や法具類を購入し使い切った。
空海は806年3月に長安を出発して4月に越州に到着、そこに4ヶ月滞在し、土木技術や薬学など様々な分野の事を学びながら、帰国の機会を待っていた。
運良く徳宗皇帝の崩御にともなう、新帝・順宗への、朝貢礼謁の使者が日本から来た。
空海はその帰り船に便乗し日本に帰国したのである。
<空海が辿った道 (青:帰国)>

7.4. 空海帰国する
空海は、大同元年(806年)10月に博多に帰着した。
留学僧は20年間滞在して修学するという国家の規定を破って帰国したため、空海に対して朝廷は大同4年(809年)まで入京を許可しなかったため、空海は帰国後入京の許しを待つ数年間大宰府に滞在することを余儀なくされた。
大同4年(809年)、許しを得た空海は7月に入京、高雄山寺に入った。
以後空海は嵯峨天皇に重用され、無名の一留学僧から、仏教界の表舞台にたち、大活躍することになる。
日本の密教
日本で密教が公の場において初めて紹介されたのは、延暦24年(805年)唐から帰国した伝教大師最澄によるものであったが、天台教学が主であった最澄は密教を本格的に修学していたわけではなかった。
本格的に日本へ伝来されることになるのは、唐における密教の拠点であった青龍寺において密教を本格的に修学した空海(弘法大師)が延暦25年(806年)に日本に帰国してからである。
ときの桓武天皇は密教を最新の仏教とし、奈良の仏教勢力を抑え込む道具にしようと考え保護した。
日本の密教は、空海、最澄以前から存在した霊山を神聖視する在来の山岳信仰とも結びつき、修験道などの神仏習合の主体ともなった。
<続く>