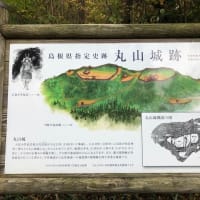7.4. 弘法大師にまつわる石見地方の口碑伝説
日本各地には数多くの弘法大師伝説があり、その数は5000件を上回る。
石見地方、邑智郡、桜江町に残っている弘法大師の伝説を調べてみた。
その一部を以下に記述する。
何れも超常現象の逸話である。
戒めを有名な人を通して伝えるという狙いがあったのかもしれない。
戒めの主人公は天狗様でもいいのだが、実在する人物のほうがまだ真実味があったからと思われる。
7.4.1. 美濃郡豊田村(現益田市横田町)(島根県口碑伝説集より)
弘法大師の衣洗ひ
昔弘法大師、諸国を行脚せられて、美濃郡豊田村大字本俣賀に来られ、汗塵に汚れた衣を脱いで、之を樋の元川で洗はれた。
村人は固よりそれが有名な高徳の大師とは知らないから、其衣の不潔なるを見咎めて洗濯を差止めた。大師は何も云はないで去つて、高津村字須子に行きて、須子の大堤で御洗ひになった。
この因縁によって後世本俣賀村は、夏季に入ると水利潤渇して、旱魃を見ること毎度だけれども、須子村は高僧の恵みによつて、後世此堤で溺死したものが無いと云ふ。
現今夏季殆んど毎年、樋元より用水潤渇し、角井に至つて湧出する。爲めに上流たる本俣賀は、旱魃の患を見るも、下流たる角井は更に此患無きは、不思議な現象である。
7.4.2. 邇摩郡大濱村(現大田市温泉津町)(島根県口碑伝説集より)
弘法 大 師の石
邇摩郡大濱村大字飯原に昔吉田某の老媼が小作人の繁八と云ふものと四國八十八ヶ所を巡禮した時、ある朝荷物の中に石が這入つて居た、何者の仕業だらうかと訝りつゝ投棄てた。
その日も巡禮をして宿を取り 翌朝に至りて出發しやうとすると、前日捨てた石がまた荷物の中にあった。
依つて此事を成寺僧に尋ねると、これはお大師様の思召であらうと云ふので大切に持歸り大師の像と共に岩屋内に祭った。里人は今に 至るまで崇拝して居る。
7.4.3. 桜江町江尾(桜江町誌より)
弘法大師
江尾の糸谷川にドウショウという地名があるが、むかし弘法大師がここまでこられた時、日が暮れかかっていたので「ここ で泊らうか、どうしょうか」といわれたので、以来この地をド ウショウというようになったと伝えている。
その時ドウショウの川のはたで、着物を洗っていたおばあさんがあったので「お婆さんここの水はのまれるかい」と問われ た。
大師はあまりにもきたないなり (身なり)をしておられたので「こんなほいとう坊主」と思ったのか「この水はきたなくてのまれません」といった。
大師「そうか」といって糸谷川にそうて行かれた。そしてその川の水を飲んでみられると、とてもおいしい水だった。
「ははあ婆ァわしのなりをみて馬鹿にして嘘を教えてくれたな、おのれこれからはこの川でせんたくが 出来ぬようにしてやる」といわれて、口の中で何かとなえられた。
すると糸谷川の水がぴたっととまった。以来糸谷川には水 が流れぬようになったという。
それからしばらく行かれると、おいしそうな桃があったので、土地の人に「この桃の持主があるか」ときかれると「その桃はにがくて食べられません」といった。 大師は試みに一つ食べられると、とてもおいしかった。 以来この桃はにがくて食べられなくなったという。
(註) この大師の話には、 都野津弘法坂 (千田) 有福にも類 話がある。
7.4.4. さくらえの民話より
弘法大師の話(水)谷住郷 谷
弘法さんが、昔、通って、錫杖で。水飲ましてごせ言うて。 今度、 木の無いのに水汲んで飲ましてあげたいうてな。
そりゃ、水がたっ ぶりありゃあ飲ませられるだが、 水無いけな、無理して汲んできて 飲ましてあげたいうて。
「それだけ、水不自由しとるんか。」
いうてな。 それから水をなにしちゃろいうて、それから今度錫杖持って、
「ここをちっと掘りんさい、水が出るけ。」
言うて。それから、今もちょうど冷たい水が出よるだ。 坂根の井戸 いうてな。
弘法大師の話(水)谷住郷 長戸路
昔、人が通りんさった言うてな。
「水飲ませんか。」
ちゅっというようなことを。
「水ありません。」
言うてな。それが弘法大師さんだったんだげな。
「川の水を飲ませ。」
言うのを、「そりゃきちゃなあけん飲まれん。」
いうて言うた話やあります。
そうで、「きちゃなあ水なら。」
って、ぼこぼこって弘法大師さんが杖持ってつついとれたげなが。
そいから水が枯れはないたいう話がありますね。
そりゃあっち(住郷)の川がありやすけん。
弘法大師の話 (芋) 川戸 小田
弘法さんがなぁ、あの、この方は芋を作って食べにゃあ、畑ばっかりで田がなぁけえなあ。
だいたいに畑の、田の少なぁとこだけえ弘法さんが回られた時にあの、弘法さんに貸すまぁ思うて、「こりゃぁ今、石だけえ、おまえにゃあ貸されん。」 たら言うて。
けぇ、芋までが石になった。
弘法大師の話 ( 地名由来) 市山 江尾
三田地に出たら、
「ここは見たことがあるようだ。」
と言いんさったけん、三田地だという。
月の夜になったら、
「まだ月の夜だな。」
言う。だけん月の夜。 それから今度、長尾じゃ、 「やれ長いのう。」
言うたで、長尾。 それで、今度、 今田、
「まだかいのう。」
言うたけん、今田になった。 そいから江尾にきて、 「ええ所だのう。」
言うて江尾になった。いう話を弘法大師がした。
弘法大師の話 ( 地名由来) 谷住郷 妙見谷
弘法大師が山からおりてむこうへ、川戸の方へ行く。
そのときに 喉が渇いたので山水を飲んだと。 ところがその山水が非常においし かった。
それで、「この水はおいしい水だ、大事にしとかにゃあいけん。」
言うて、その水を飲んで、それから川を渡って、船を渡って川戸と いうところへ行って、その堤防を通って行くときに、夜、月がこう、 上がって来て、
「あ、いい月だ」
言うて、弘法大師が眺めたのが、堤防のむこう側の「月の夜」という 集落だそうだ......。
弘法大師の像 川戸三田地
弘法大師は、水との縁が深かったようである。
川戸の三田地には、謂れ等は伝わっていないが、五谷川より湧き出る霊泉の守り佛として、薬師如来と弘法大師の小さな像が祀られている。

7.5.5. 江の川の水害防備林
現在江の川沿いに多く見られる竹林は、治水目的で意図的に植えられた水害防備林である。
かつて、江の川中下流域では、田畑と江の川との間には竹林が茂っていたが、現在はそれが堤防に取って代わりつつある。
伝承によるとこれらの竹林は、奈良時代から平安時代に現在の江津市桜江町甘南備寺を訪れた弘法大師の教えで植えていったということである。

これらの伝説が出来たのは、恐らく空海逝去後弘法大師の諡を受けた後、全国的に有名になってから出来たものと思われる。
<続く>