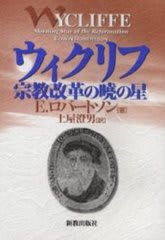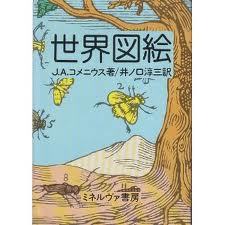コメニウスが所属していた「モラヴィア兄弟教団(チェコ兄弟教団)」について、もう少し触れておきましょう。 宗教改革運動といえば、16世紀のドイツのルターやジュネーヴのカルヴァンが有名ですが、腐敗したカトリックを批判し、キリスト教本来の精神に立ち戻ろうという運動は、14世紀のイングランドにおいてすでに開始されていました。「モラヴィア兄弟教団」の起源は、このイングランドで開始された宗教改革に連なるもの . . . 本文を読む
少し間が開いてしまいましたが、チェコの教育思想家コメニウスの続きです。
日本ではほとんど知られていませんが、コメニウスの著作の中で「18世紀には聖書に次ぐベストセラーになっている」と言われたのが『世界図絵』です。作られたのは17世紀ですが、それから200年余りにわたって版を重ね続け、ドイツ語や英語などヨーロッパの各国の言語に訳され、普及しました。19世紀のドイツの作家ゲーテもこの『世界図絵』 . . . 本文を読む
コメニウスは亡命生活中に数多くの教育書を書き、1657年にはそれらをまとめ上げた書物として『大教授学』を出版しました。そこには「貴族の子どもも身分の低い子どもも、金持ちの子どもも貧乏人の子どもも、男の子も女の子も、あらゆる都市、町、村、農家」にすんでいる子どもも含めたすべての青少年を教育の対象とすると書かれています。
教育がすべての人を対象とするというコメニウスの考えは反発を招きかねないもの . . . 本文を読む
本日7月14日はフランス革命記念日です。この「憲法って、面白っ! 教育編」のシリーズは、フランス革命期に公教育の理念を打ち出したコンドルセから始まり、次にその思想的源流として16世紀フランスの思想家モンテーニュの教育思想の紹介をおこなってきました。今回はその続きとして、17世紀のチェコに登場した「近代教育学の祖」と呼ばれるコメニウスを取り上げていきたいと思います。
コメニウスは「すべての人に . . . 本文を読む
今回は、「猿払(さるふつ)事件」を取り上げて、公務員に政治活動をする権利があるのか、それを規制する法律は憲法に照らし合わせてどうなのかという問題について述べていきたいと思います。
まず、猿払事件とはどんな事件だったのでしょうか。 事の起こりは、1967年の衆議院議員選挙に際し、北海道宗谷郡猿払(さるふつ)村の郵便局に勤務する労働組合の事務長Aさんが、所属する労働組合の決定に従い、B党公認候補 . . . 本文を読む
学問は楽しいものであるとモンテーニュが主張したからと言って、彼は子どもたちを安楽に過ごさせようとしたわけではありません。彼は子どもたちに肉体的な鍛錬をも推奨しました。それは何のためかといえば…。(鈴) . . . 本文を読む
モンテーニュは、学問は本来楽しいものであるという強い信念を抱いています。そして、教育には学ぶ楽しみが不可欠のものであることを随所で述べています。
「子どもたちの利益があるところには、彼らの楽しみもあるのでなければなりません。」
「知恵の最も明白なしるしは不断の喜びです。」
「彼の心の中に、すべてのものを探求しようとする正しい好奇心を植え付けてください。」
彼自身、生涯にわたってあらゆる . . . 本文を読む
モンテーニュの時代に広くおこなわれていた教育といえば、子どもたちを鞭による苦痛と恐怖で締め上げることでした。彼はそのやり方を厳しく批判しています。
「人は子どもたちを学問へ誘う代わりに、事実上は、子どもたちに恐怖と残酷をしか与えていないのです。どうか暴力と強制をやめてください。私の見るところでは、良く生まれついた本性をこれほどはなはだしく堕落させ、萎縮させるものはありません。」
「授業の最中 . . . 本文を読む
著書『エセー』の中で、哲学や歴史、人間の心理、様々な風習など、非常に多岐にわたるテーマを展開したモンテーニュですが、その中でも彼が最も重視したのは、なんだったのでしょうか。(鈴) . . . 本文を読む
モンテーニュの生きた時代から半世紀を遡った頃にヨーロッパ人はアメリカ大陸を「発見」し、新大陸の住民との交流が始まりました。 ヨーロッパ人は、アメリカ大陸に住む住民を“野蛮人”と決めつけて、奴隷にしたり、インカやアステカのように彼らのコミュニティを破壊してしまったりしました。
アメリカ大陸の住民の中でも、「食人」の習慣を持つ人々について、モンテーニュは次のように述べてい . . . 本文を読む
2012年1月1日から9回にわたってこのブログで「憲法って、面白っ! 教育編」を掲載し、そこではコンドルセを中心としたフランス革命期の公教育思想について紹介しました。
今回はさらに時代を遡って、ルネッサンス時代の思想家モンテーニュ(1533~1592)を紹介していきたいと思います。
モンテーニュは、ワインで有名なフランス南西部のボルドー近郊で生まれました。若い頃は裁判所に勤め、37歳でい . . . 本文を読む
これまで、「フランス革命期の公教育論」という本から、コンドルセの「公教育の全般的組織についての報告と草案」(1792年4月20,21日)の内容を紹介してきました。 不幸なことに、この報告をおこなった翌日にオーストリアに対する宣戦布告がなされ、この公教育案は審議されずに終わってしまいました。しかし、これは同年12月にあらためて印刷・配布されました。 これを受けてまた活発な討議が行われるようになりま . . . 本文を読む
これまで紹介してきたコンドルセの報告はその最後でも、公教育の公権力からの独立について再度強調しています。
「われわれは公教育をあらゆる公権力から独立させた」
「あらゆる公権力」というのは、もちろんコンドルセ自身がその一員である革命政府の権力をも含んでいます。せっかく絶対王政を打ち倒しても、その革命の成果が全ての人々のものになることなく、再びそれが後戻りしてしまうことを彼は危惧していました。 . . . 本文を読む
コンドルセは、公教育を宗教から完全に分離させることを求めました。それは、一つには社会的平等のためであり、もう一つは各人の信仰の自由、思想・良心の自由を守るためです。彼は政教分離が徹底されてこそ、特定の人々を排除することなく、各人の信教の自由、思想良心の自由が真に守られると考えていました。
「憲法は各人に自分の信仰を選ぶ権利を認め、フランスの全住民の完全な平等を定めているのだから、公教育において . . . 本文を読む