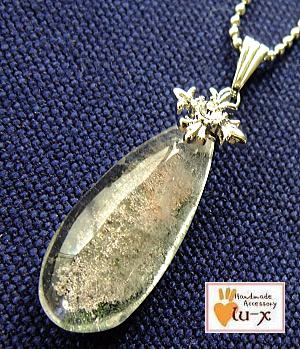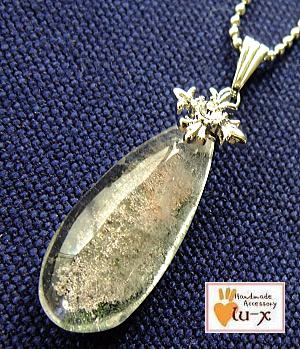こんにちわ~^0^
ああ~~ぁ ホントに引きずってしまっている京都編><
今日で最終回ですので、最後までお付き合いくださいぃぃ~ヽ(^_^;))((^。^;)ノ
三千院を巡りお次は・・・(この日徳島へ戻らなければならないわけですので、あまり悠長に遊んでいられないってのもあり^^;)最後は、ココで〆めましょう♪って事で選んだのは比叡山。
比叡山と言えば、『延暦寺』っしょ( ̄∀ ̄*)
でも、さぶそぅ・・

比叡山にはドライブウェイ(有料)が走っています、ケーブルも有りましたが、車で行きたかったのと少しでも早くと思い、割高でしたが有料使いました。
おおっ! 山の向こうはもう滋賀県です。 琵琶湖が見えます。

比叡山は京都府と滋賀県の県境、京都からは鬼門(東北)にあたるため王城鎮護の山とされた。
古事記では比叡山は日枝山(ひえのやま)と表記され、延暦寺が日枝山に開かれて以降、天台宗の山王信仰の頂点になったのです。
着いた瞬間凍り付きそうでした。

雪降ってるんだもん><(当然でしょうけれど^^;)
だけど、丁度、小降りになり止んでくれました(ホッ)
大講堂

お釈迦様を始めとして桓武天皇、聖徳太子、仏教・天台宗ゆかりの高僧の肖像画がかかっていました。
延暦7年(788)最澄(さいちょう)がこの地に一堂を建てて自刻の薬師如来像を安置し、その後、延暦寺は天台宗の総本山として隆盛を極めました。
法然、親鸞、日蓮、栄西、道元などの各宗派の開祖がこの寺で学び、法華(ほっけ)・密教(みっきょう)・浄土(じょうど)・禅(ぜん)の各信仰が展開され、その後の日本仏教の様々な宗派が生み出されていったことから「母なる山」とも呼ばれました。
やがて、その強大な力を恐れた織田信長が元亀2年(1571)全山を焼き討ち。(まぁ、この焼き討ちには色々なストーリーが有るのですが、興味がありましたら、
こちらへ

延暦寺は根本中堂をはじめ大半の建物を焼き討ちによって失いました。
現在の建物は豊臣秀吉が再興を手がけ、徳川3代将軍・家光の時代にほぼ復興し、現在の根本中堂も江戸時代初期の寛永19年(1642)に9年の歳月をかけて完成したものです。
巨木の森に包まれた根本中堂の長い回廊を靴を脱いで歩いてみましたが、昔の僧侶は裸足で歩いたであろう回廊は氷の様に冷たくて、お堂の中の一部に引かれたホットカーペットがオアシスの様でした(〃∇〃)
この根本中堂には1200年間ずっと消されずに燃えている火があるのだそうで、『不滅の法灯』と呼ばれています。
本尊厨子前の釣灯篭に灯るのが、最澄の時代から続く「不滅の法灯」なのだそうですが、信長の焼き討ちで一時途絶えたんだって。
山形県の立石寺に分灯されていたもの(保険?^^;)を移して現在でも燃え続けているそうです。
鐘楼(しょうろう)がありました。

開運の鐘と呼ばれ、一山に重大な事件が起きると、この鐘が山中に響き渡り、これを合図に僧や山下にいる公人が大挙して大講堂前に集まり衆議をしたといわれ、また除夜の鐘としても有名です。
除夜の鐘は108の煩悩を取り払うんですよね^^
ホイミの煩悩まみれの脳にも効くかしら♪
かなり気合い入れて全力で突きました。

我ながらあっぱれ

鐘の音が山々に響き渡りました♪
一突き50円です。 108回なら5400円也((((((≧∇≦))))))
不思議なのですが、一突きだけで、何かスカッとしました。
(今までには無かった不思議な経験です)
ひとつ煩悩が落っこちたにちがいありません!!
同じく煩悩まみれの助さんに、だまされたと思って突いてごらんと、
無理矢理薦めてみまして、助さんのこん身の一発!
・・・・・どうかな???
あ・・・ホンマになんか落ちた。うわっ!!なんで?なんで??スッキリしてる。。(驚)
だそうですっ!!!!ほぅらね♪\(*⌒▽⌒*)/
あと107回突いてみたら? 悟りがひらけるかもしれんよ( ̄w ̄)ウヒヒ
皆様も要らないモノを落っことしに行ってみてくださいね( ̄∀ ̄*)w
さて、長々と綴って参りましたが、京都編はこれでおしまいデス。
最後に、淡路SAで見つけた・・・
今日のソフト~(臨時復活版)
淡路の藻塩ソフト(粒あん添え)

金時芋ソフト

PS.売店横のベンチに大きなお財布の落とし物発見!
売店のおねぃさんに預けました。
お札(?)とカードでずっしり重い黒い皮の財布、落とした方が見つかってれば良いけど。。