最近手に入れた地図があります。欲しくて欲しくて古いビルの3階の一室にあるオフィスまでもらいに行きました。
それがこれ。
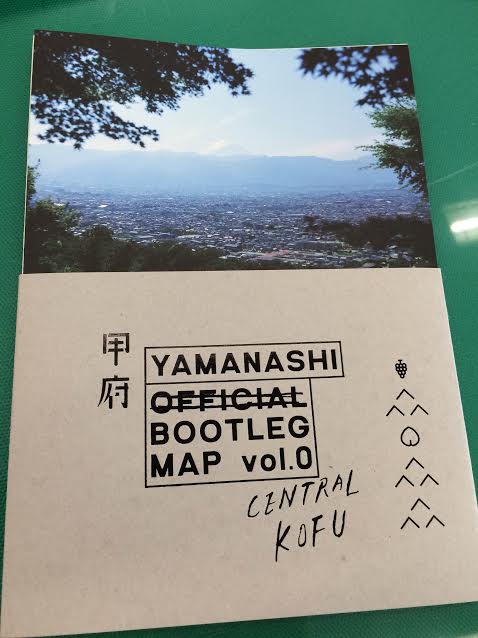
オフィシャルではなくて、ブートレグ。ようはアンオフィシャルというか、実に私的目線満載の甲府の地図です。
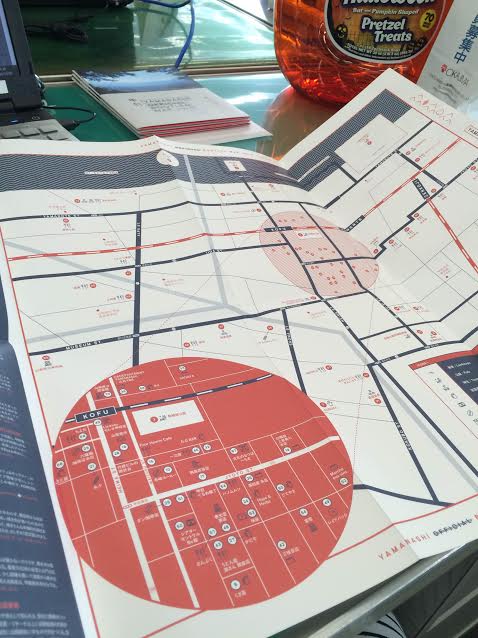
甲府に移住して、
甲府にオフィスを構えて
いろんなお仕事をしている人たちが作ったもの。
冊子版とweb版があります。
http://yamanashi-map.net/
見ていて面白い。
非常に私的なコメントが書いてあります。
ブートレグ。
案外まちって、それぞれの目線でそれぞれの感覚でみたものの積み重ね。そのまちのつまらなさだったり楽しさだったり。
何を発見するか、どう思うかなんだよなーって思っているので、そんな感じの感覚が詰まっている気がする地図です。
どんな地図を広げるか。
それで見える景色が違う。
地図に何を記していくか。それによって生活も違う。
自分だけの甲府地図作りたくなってきました。
それがこれ。
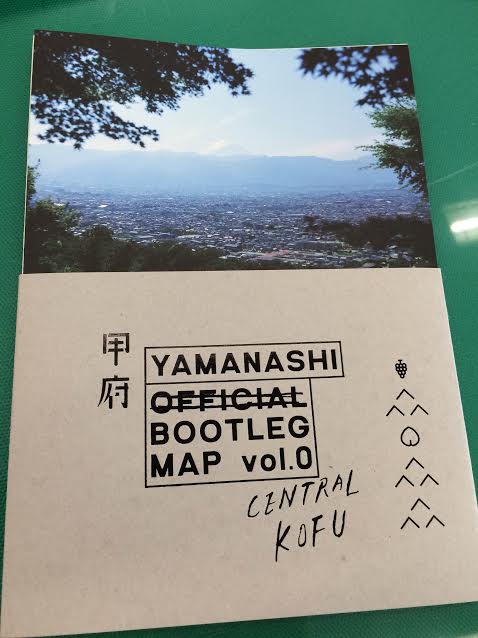
オフィシャルではなくて、ブートレグ。ようはアンオフィシャルというか、実に私的目線満載の甲府の地図です。
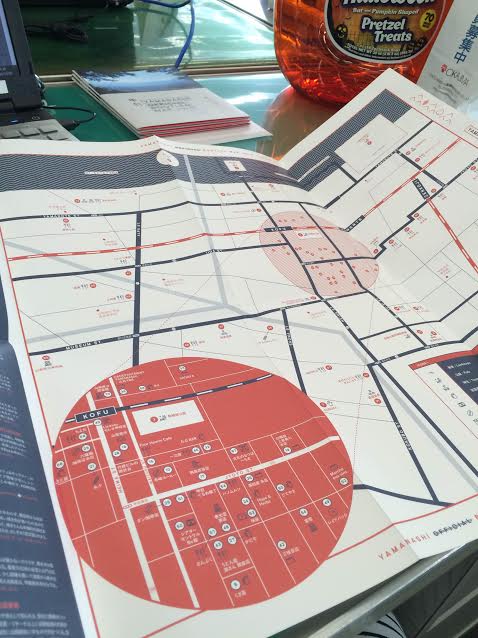
甲府に移住して、
甲府にオフィスを構えて
いろんなお仕事をしている人たちが作ったもの。
冊子版とweb版があります。
http://yamanashi-map.net/
見ていて面白い。
非常に私的なコメントが書いてあります。
ブートレグ。
案外まちって、それぞれの目線でそれぞれの感覚でみたものの積み重ね。そのまちのつまらなさだったり楽しさだったり。
何を発見するか、どう思うかなんだよなーって思っているので、そんな感じの感覚が詰まっている気がする地図です。
どんな地図を広げるか。
それで見える景色が違う。
地図に何を記していくか。それによって生活も違う。
自分だけの甲府地図作りたくなってきました。












 驚きました!「こんなに景色、よかった???」って。これまでわざわざ県外のいいところへいってロープウェイ乗っていましたけれど、昇仙峡、まさかのこの眺望。こんなに近いところに、あった!再発見です!
驚きました!「こんなに景色、よかった???」って。これまでわざわざ県外のいいところへいってロープウェイ乗っていましたけれど、昇仙峡、まさかのこの眺望。こんなに近いところに、あった!再発見です! こんな場所を越え、
こんな場所を越え、 こんな道を越え
こんな道を越え こんな道なき道をすすむという・・・
こんな道なき道をすすむという・・・
 履いててよかった。
履いててよかった。
 こんな階段も
こんな階段も こんなはしごもおかげで登れました。
こんなはしごもおかげで登れました。 あの林の向こうに見える岩肌のところ。
あの林の向こうに見える岩肌のところ。


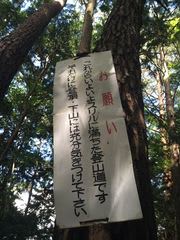 こんなおちゃめな看板は私に帰れといっているかのよう・・・
こんなおちゃめな看板は私に帰れといっているかのよう・・・
 なんで怖いかって?それは饅頭のようにまん丸の岩。その先つるりといったら・・・ひょえーーー!!!!って想像するだけで怖いです。
なんで怖いかって?それは饅頭のようにまん丸の岩。その先つるりといったら・・・ひょえーーー!!!!って想像するだけで怖いです。







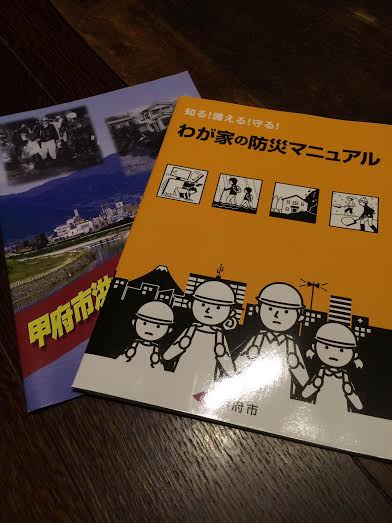
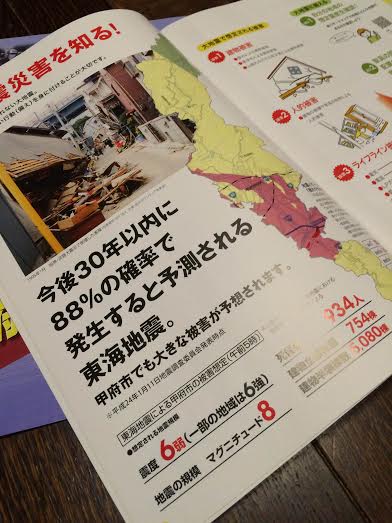
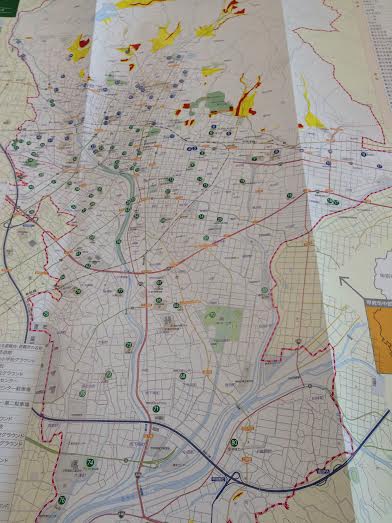
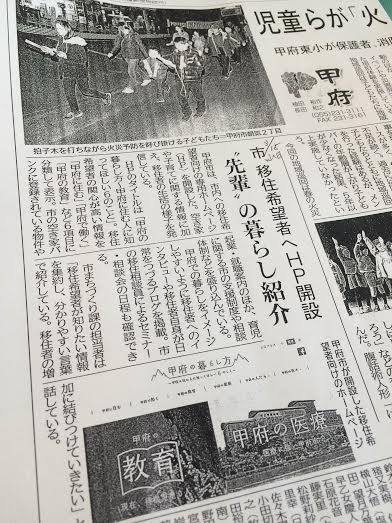
 小学校とその地元の消防団がともに初めて企画したそうで、子どもたちが拍子木を打ちながら「火の用心、マッチ一本火事のもと」と声を張り上げながら地域を回ったそうです。
小学校とその地元の消防団がともに初めて企画したそうで、子どもたちが拍子木を打ちながら「火の用心、マッチ一本火事のもと」と声を張り上げながら地域を回ったそうです。 これは、私の幼馴染が消防訓練をしている時の写真です。このブログに載せるためにもらいました。
これは、私の幼馴染が消防訓練をしている時の写真です。このブログに載せるためにもらいました。










