(高田博厚 芸術論)
著作集 III、313-317頁 「モーツァルトの親密」
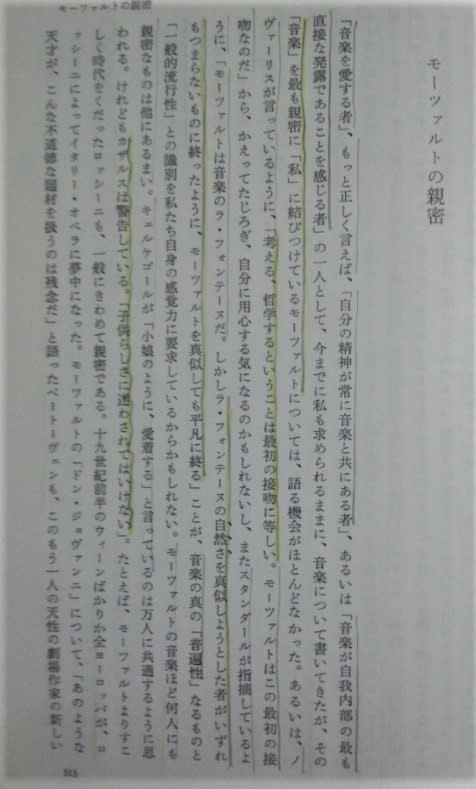
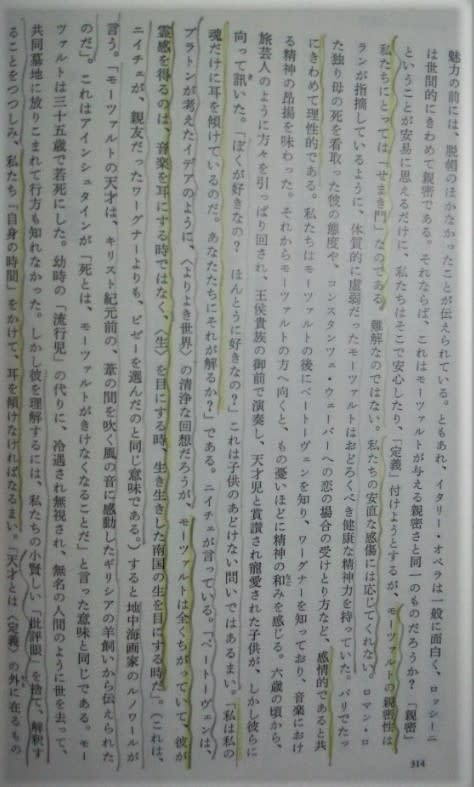
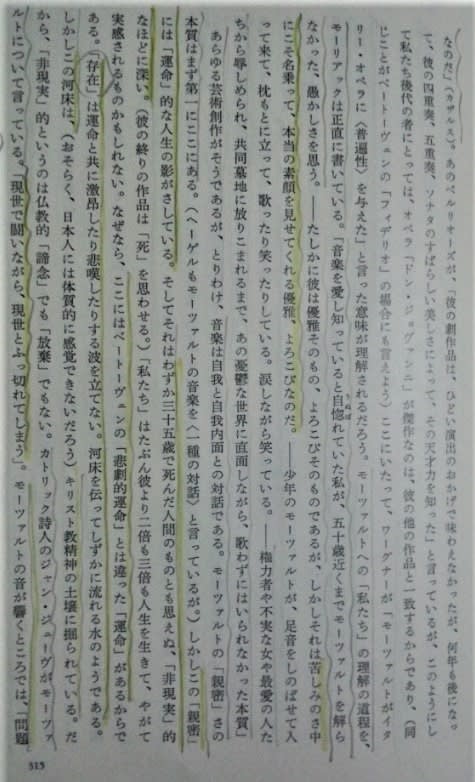
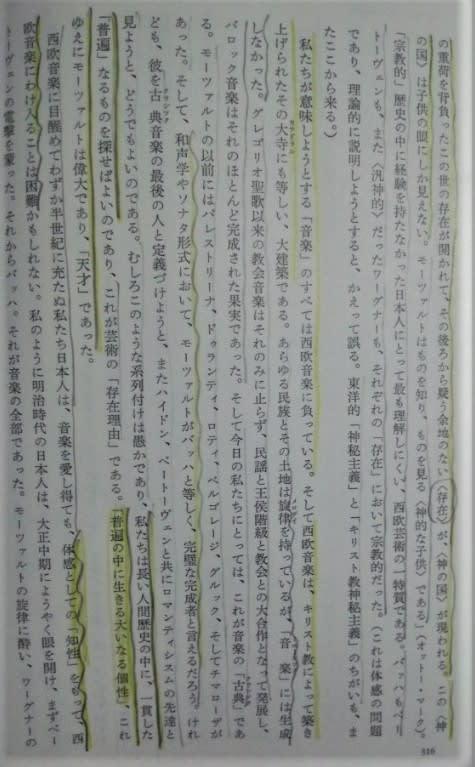
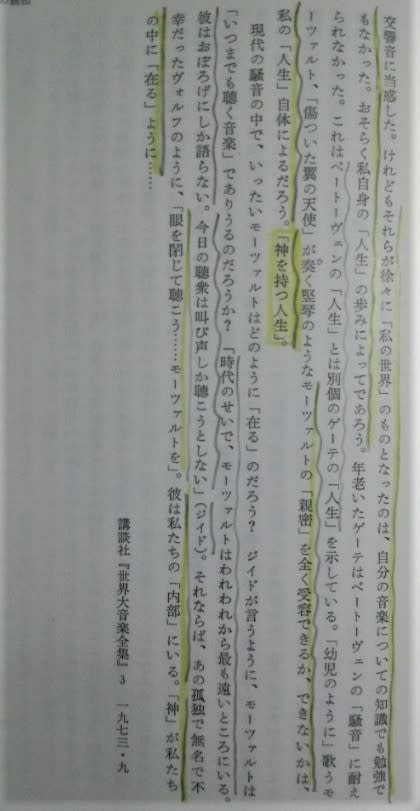
このような文章は全体がかけがえのない価値をもち、そののなかから特に選べるものではないが …
《モーツァルトの親密性は私たちにとっては「せまき門」なのである。難解なのではない。私たちの安直な感傷には応じてくれない。》
《彼を理解するには、私たちの小賢しい「批評眼」を捨て、解釈することをつつしみ、私たち「自身の時間」をかけて、耳を傾けなければなるまい。「天才とは〈定義〉の外(そと)に在るものなのだ」(カザルス)。》
《ここにはベートーヴェンの「悲劇的運命」とは違った「運命」がある・・・ 「存在」は運命と共に激昂したり悲嘆したりする波を立てない。河床を伝ってしずかに流れる水のようである。》
《「現世で闘いながら、現世とふっ切れてしまう」。モーツァルトの音が響くところでは、「問題の重荷を背負ったこの世の存在が開かれて、その後ろから疑う余地のない〈存在〉が、〈神の国〉が現われる。この〈神の国〉は子供の眼にしか見えない。》
《私たちは長い人間歴史の中に、一貫した「普遍」なるものを探せばよいのであり、これが芸術の「存在理由」である。「普遍の中に生きる大いなる個性」、これゆえにモーツァルトは偉大であり、「天才」であった。》
《それらが徐々に「私の世界」のものとなったのは、自分の音楽についての知識でも勉強でもなかった。おそらく私自身の「人生」の歩みによってであろう。・・・ モーツァルトの「親密」を全く受容できるか、できないかは、私の「人生」自体によるだろう。「神を持つ人生」。》
《「眼を閉じて聴こう……モーツァルトを」。彼は私たちの「内部」にいる。「神」が私たちの中に「在る」ように……》









