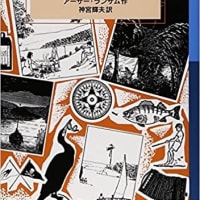↑『海に出るつもりじゃなかった』のなかの挿絵。子猫のシンバッド。アーサー・ランサム自身が描いている。

 アーサー・ランサムはご存知のように、20世紀前半に、子どもたち向けに休暇と冒険の物語群、別称ランサム・サーガを世に送り出した作家だ。
アーサー・ランサムはご存知のように、20世紀前半に、子どもたち向けに休暇と冒険の物語群、別称ランサム・サーガを世に送り出した作家だ。ランサムはこの物語群を書くのに、17年の歳月を費やしている。
作家自身が作品の子どもたちを上回るような冒険
──ともいえそうな波乱に満ちた人生を送ったわけだけれど、そんなランサムも猫とのふれあいに心を温めた時期があった。
それは物語にも反映している。
 『海へ出るつもりじゃなかった』はランサム・サーガ7番目の物語だが、そこに猫が登場する。
『海へ出るつもりじゃなかった』はランサム・サーガ7番目の物語だが、そこに猫が登場する。
嵐で波がうねる夜の海。
母親から決して海には出ちゃいけないと釘を刺されいたにもかかわらず、
思いもよらない成り行きで、ゴブリン号は外海に流れ出てしまった。
乗船しているのは子どもたち4人だけ。
これまでに操縦したことのない規模のヨットを必死で繰りながら、危機を乗り切ろうとしていた真っ最中に、子猫が海に流されてくる。
ジョンが言うには、材木運搬船の甲板の積荷が流され、その中に子猫がしがみついていた鶏小屋も含まれていたのだ。
(たぶんノルウェーの船と思われる材木運搬船は)
「まず一方に傾いて、つぎに反対側に移ったところへ、大波が一つきて、さっとすくうと、材木がぜんぶ海に浮かんじゃうのね。」(by スーザン)
〝海に流された鶏小屋の板にぺったりとへばりついた、びしょぬれの毛皮の切れっぱし〟
それは子猫だった。
 子どもたちは、危険にひるむこともなく、
子どもたちは、危険にひるむこともなく、子猫を助けることを唯一の選択肢として迷うこともなく、
子猫を救い上げる。
まさかのタイミングで、子どもたちに救われた子猫。
「おぼれかけた人には、ふつうなにをするのかしら。」(ティティ)
「かわいた布とブランデーよ」(スーザン)
ほら、ランサムは何もかも心得ているのだ。
長年培ってきた湖や川や海での経験。
何気ないけどこんなリアルな知識が物語に練りこまれるから、
本当にあったことのように、読者の心を強く惹きつける。
なにしろそんなわけで、難破水夫である子猫はシンバッドと名づけられ、
8番めの物語『ひみつの海』にも登場することになる。

 さて、実生活でもランサムは猫を飼っていた。
さて、実生活でもランサムは猫を飼っていた。そりゃ、当然だ。
猫を飼ったことがなければ、あんなリアルに溺れかけた猫を蘇生させるシーンを描けないだろう。
ラム酒をつけた指を子猫の小さな口の中にそっと差し入れて含ませる様。
水で薄めたミルクをなめておなかがぷっくりふくれる様、ピンク色の小さな舌、よろよろ歩く様…。
猫を飼って日々見つめた人でなければ描けない、イキイキした猫の姿。
 ヒュー・ブローガンの評伝によると、ランサム夫妻は、ランサムが50歳のときに2匹の子猫を手に入れた。
ヒュー・ブローガンの評伝によると、ランサム夫妻は、ランサムが50歳のときに2匹の子猫を手に入れた。ランサム夫人の子猫はポリー。
ランサムの子猫はポッジ。メスの猫だ。
賢くて人懐こい猫。
2人に子どもはいなかったから、愛情は十分に注がれた。
本に登場させるくらいだもの。
母親への手紙にもこんなことを書いている。
★ネコたちは元気です。ポッジは今空襲監視員といわれています。(第二次世界大戦中、1940年の話)彼女は、サイレンがなるとすぐなかけこんできます。ポリーのほうはよばなくてはなりません。ポッジは、避難所でも、不安げに、ポリーがくるまで目をくばっています。はじめから、ポッジのほうは、飛行機を真剣に考えていて、頭上になにかがいるかぎり、不安そうに天井を見上げながら伏せているのです。
こうして8年間可愛がったネコのポッジだったけれど、
疎開のためにコニストンに引っ越した2年後に、なんと、キツネに食い殺されてしまう。
58歳のランサムはしばらくしょんぼりしていたそうだ。
「頭がよくて心のやさしい小さな生きものの死を、彼は心から嘆き悲しんだ。」(評伝より)
突然に可愛がっているネコが亡くなってしまった場合、
とくに「キツネにやられた」なんてときには、
けっこうひどいペットロスに襲われるにちがいない。
シンバッドが…と思うと、
(もちろん物語のなかのネコと現実のネコは違うけれど)猫好きとしては胸が詰まる。
 そんなアーサー・ランサムと猫の話でした。
そんなアーサー・ランサムと猫の話でした。  今夜は雨が降り出すらしい。 よいウィークエンドを!!
今夜は雨が降り出すらしい。 よいウィークエンドを!!