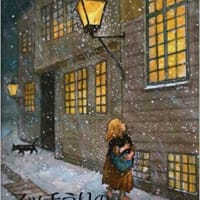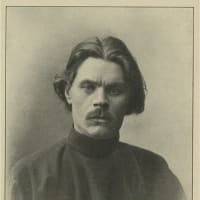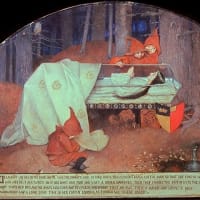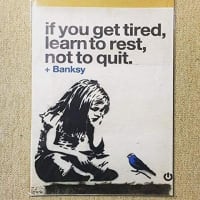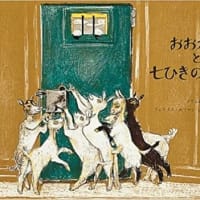ずっと前に、「児童文学とファンタジー」というテーマの、ある公共機関の図書館のセミナーに参加したことがあります。
ずっと前に、「児童文学とファンタジー」というテーマの、ある公共機関の図書館のセミナーに参加したことがあります。
講師は児童向けの書店を経営し、児童文学に造詣が深い女性でした。
残念ながら、お名前は忘れたけど、OL時代に『指輪物語』に出会い、人生に転記が訪れたという方でした。
読み始めた『指輪物語』を途中で中断するのが惜しくて会社に電話して年休を取り、寝るのも惜しんで読了したそうです。
 この方のファンタジーの定義によると、「ファンタジーは『普通の子』がさまざまな体験を通して成長していくという要素がなくてはならない」ということでした。
この方のファンタジーの定義によると、「ファンタジーは『普通の子』がさまざまな体験を通して成長していくという要素がなくてはならない」ということでした。
ちょうどハリー・ポッターが登場し、世界中に旋風を巻き起こしていた時期でしたが、「ハリー・ポッターはファンタジーではない」というのが、講師の方の持論でした。
サラは質問の時間に、このことについて質問してみました。
「ハリー・ポッターはファンタジーだと思うのですか…!?」
講師の方の答えはこうでしたよ。
「ハリー・ポッターは前述の定義に当てはまりません。
ハリー・ポッターは生まれながらに特別の存在であり、強い能力を与えられています。
『普通の子』ではありませんよね。
だから、ハリー・ポッターはファンタジーとはいえないのです。
あの本は、学園もののジャンルに入ります」
彼女にとっては、『指輪物語』こそがファンタジーそのものだったのでしよう。
しかし、ずっと納得できなかったこの定義。
どんな人たちが、そのような定義・お約束を決めたのかはしりませんが、ちょっと狭すぎませんか?
 さて、ここのところ『探求するファンタジー』(風間書房)という本を読んでいます。
さて、ここのところ『探求するファンタジー』(風間書房)という本を読んでいます。
その中で多ヶ谷有子さんという人が「聖杯探求におけるファンタジー」という章で、トールキンのファンタジー論を次のように紹介しているのに出会いました。
 「トールキンは、ファンタジーは想像力の思い描くものを直ちに現実化する力だと主張している。
「トールキンは、ファンタジーは想像力の思い描くものを直ちに現実化する力だと主張している。
ファンタジーの魔法によって、物事をイメージとして、目に見えるように捉えることで、その結果、想像力によって思い描くものが現実化できるのだと説明している。
ファンタジーによって、目に見えるように、文字として現実化された世界が、ファンタジー文学といえるだろう。
お伽噺の世界、小説の世界、これらはみな、想像力が思い描いたものが作り上げた世界である。
この世界をトールキンは『第二の世界』と名づけた。
我々が生きる人間世界を『第一の世界』と呼ぶならば、人間が想像力によって作り上げる世界は『第二の世界』というわけである」
「現実世界では決してかなえることのできない根源的願望をファンタジーの世界でかなえることによって、人は「幸福の結末」という慰めを得ることができ、精神の飢えから回復することができるというのである」とも。
 トールキンといえば、まさに『指輪物語』の著者です。
トールキンといえば、まさに『指輪物語』の著者です。
そのトールキンも、ファンタジーとは、このように広義な世界と定義しているのです。
だから、ハリー・ポッターももちろんファンタジーです。
この本を読んで、「なんだよーっ」という鬱憤が晴れ、すっきりしたのでした。
(長年の鬱憤…ううっ、しつこいかも)
 ちなみに、バーネットの『消えた王子』は、妖精も出てこないし、現実的世界から離れることはないのですが、やはりファンタジーだといっていいと思います。
ちなみに、バーネットの『消えた王子』は、妖精も出てこないし、現実的世界から離れることはないのですが、やはりファンタジーだといっていいと思います。
最近の「物語とは?──物語論」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- ジブリノート(2)
- ハル文庫(100)
- 三津田さん(42)
- ロビンソン・クルーソー新聞(28)
- ミステリー(49)
- 物語の缶詰め(88)
- 鈴木ショウの物語眼鏡(21)
- 『赤毛のアン』のキーワードBOOK(10)
- 上橋菜穂子の世界(16)
- 森について(5)
- よかったら暇つぶしに(5)
- 星の王子さま&サン=テグジュペリ(8)
- 物語とは?──物語論(20)
- キャロル・オコンネル(8)
- MOSHIMO(5)
- 『秘密の花園』&バーネット(9)
- サラモード(189)
- メアリー・ポピンズの神話(12)
- ムーミン(8)
- クリスマス・ブック(13)
- 芝居は楽しい(27)
- 最近みた映画・ドラマ(27)
- 宝島(6)
- 猫の話(31)
- 赤毛のアンへの誘い(48)
- 年中行事 by井垣利英年中行事学(27)
- アーサー・ランサム(21)
- 小澤俊夫 昔話へのご招待(3)
- 若草物語☆オルコット(8)
バックナンバー
人気記事