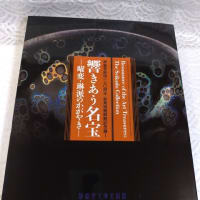<初出:2015年の再掲です>
巻四の六 信長、命からがら逃げ落ちること
永禄八年(一五六五)九月二十八日、堂洞取手
攻めの最中、丹羽五郎左衛門長秀は本陣を吹き
すぎた生ぬるい風を頬に受けて、強烈な身震いに
襲われた。今までの経験から「この身震いが起きる
と何か良くないことが起きる。」と思ったが、戦況
は信長方にとって悪くないため陣中で誰にも伝え
ないでいた。ただ信長には伝えておく必要がある。
「のう、三郎」
「なんじゃ、五郎左衛門?」
「何か知らぬが今日猛烈な身震いがした。」
「うむ」
「ただそれだけじゃ」
信長はちらっとこちらに首を傾けただけで、堂洞
取手に攻め込む味方を大声で鼓舞している。五郎
左衛門にも「そちも攻めてこい!」と人差し指で
天主を指し示す。
河尻与兵衛秀隆に続き丹羽五郎左衛門長秀が
天主に攻め入るが、敵もさる者、岸勘解由左衛門・
多治見一党が頑強に応戦してなかなか攻め落とす
ことが出来ない。その日は引き退き、先日信長方
に忠誠を誓った加治田城へと向かう。事前に佐藤
父子(佐藤紀伊守・佐藤右近右衛門)と会う約束
はしていたが、信長を目の当たりにすると「かた
じけない」と父子感涙を流し、信長は子息のところ
へ泊まることとなったのであった。翌日の行動予定
は限られた加治田城勢にしか伝えていなかった
はずなのだが・・
翌九月二十九日、信長方は山下の町で頸実検を
行い、その後尾張に帰陣しようとする予定であった
が、加治田城勢の誰かが美濃勢と通じていたのか
もしれない、関の口から長井隼人正が、井口から
斎藤竜興が、計ったように挟み討ちをかけてきた。
信長は昨日の五郎左衛門からの『身震い』の一言
と悪い前例を瞬時に思い出してつぶやく。
「これでは天文十六年(一五四七)九月、わが父
織田信秀が美濃攻めの帰りに斎藤山城守(道三)
殿に追討ちをかけられて五千名以上討ち死にした
悪例の二の舞ではないか!」
「殿、はやく、はやく」
信長のつぶやきを無視するように五郎左衛門が
河を越えての撤退を促す。ここで命をなくしては
元も子もない。
味方は七百~八百の軍勢しかないところへ、
三千を超える敵勢が挟み打ちで攻めかかったから
たまらない。ただ、父信秀の代から渡河戦に慣れ
ている信長方では、河を背にして一度『亀の甲の
型の陣形』を組んで防戦を図る。一列に河を渡っ
て逃げようとすると美濃勢の思うつぼとなるから
である。両側から攻めかかってきた美濃勢もこの
『亀の甲』を見るといったん矢合わせして十段
(108m)ほど引き退く。美濃勢も実は「本気で
信長を倒す!」と気合が入っている者と「今度
来られた時には是非お味方で!」と寝返りを狙っ
ている者が入り混じっており、斎藤竜興の鬨の声
には従うがうまく信長勢が逃げるのを願っている
者もいる。
信長方は一度広野に移動して軍勢を立て直し、
『亀の甲』の内側から馬喰・手負い・雑人を先に
河を越させ、降り注ぐ矢を楯で防御しながら撤退
する算段である。手負い・死人がそれでも多数
発生した。通常殿軍(しんがり)はその軍の最強
の部隊がつとめるが、この時は手勢が少ないこと
もあり、自動的に一番危険な渡河の差配を五郎
左衛門が受け持ち、次に危険な殿軍には信長
自身と最強の兵数名が残り、最後の仕舞いを行う
ことになった。
あらかた軍勢の渡河が終わり、取巻きのものと
残る信長が馬の鼻を敵軍に向けると、一瞬敵の
矢が止まる。殿軍としてしっかり撤退を成し遂げ
た敵将への尊敬の念からである。信長一行が河
を渡りきると再び矢の雨が降り注ぐ。河を渡った
あとは信長も足軽の動きのように馬を乗り回し、
全軍撤退したのであった。
巻四の六 信長、命からがら逃げ落ちること
永禄八年(一五六五)九月二十八日、堂洞取手
攻めの最中、丹羽五郎左衛門長秀は本陣を吹き
すぎた生ぬるい風を頬に受けて、強烈な身震いに
襲われた。今までの経験から「この身震いが起きる
と何か良くないことが起きる。」と思ったが、戦況
は信長方にとって悪くないため陣中で誰にも伝え
ないでいた。ただ信長には伝えておく必要がある。
「のう、三郎」
「なんじゃ、五郎左衛門?」
「何か知らぬが今日猛烈な身震いがした。」
「うむ」
「ただそれだけじゃ」
信長はちらっとこちらに首を傾けただけで、堂洞
取手に攻め込む味方を大声で鼓舞している。五郎
左衛門にも「そちも攻めてこい!」と人差し指で
天主を指し示す。
河尻与兵衛秀隆に続き丹羽五郎左衛門長秀が
天主に攻め入るが、敵もさる者、岸勘解由左衛門・
多治見一党が頑強に応戦してなかなか攻め落とす
ことが出来ない。その日は引き退き、先日信長方
に忠誠を誓った加治田城へと向かう。事前に佐藤
父子(佐藤紀伊守・佐藤右近右衛門)と会う約束
はしていたが、信長を目の当たりにすると「かた
じけない」と父子感涙を流し、信長は子息のところ
へ泊まることとなったのであった。翌日の行動予定
は限られた加治田城勢にしか伝えていなかった
はずなのだが・・
翌九月二十九日、信長方は山下の町で頸実検を
行い、その後尾張に帰陣しようとする予定であった
が、加治田城勢の誰かが美濃勢と通じていたのか
もしれない、関の口から長井隼人正が、井口から
斎藤竜興が、計ったように挟み討ちをかけてきた。
信長は昨日の五郎左衛門からの『身震い』の一言
と悪い前例を瞬時に思い出してつぶやく。
「これでは天文十六年(一五四七)九月、わが父
織田信秀が美濃攻めの帰りに斎藤山城守(道三)
殿に追討ちをかけられて五千名以上討ち死にした
悪例の二の舞ではないか!」
「殿、はやく、はやく」
信長のつぶやきを無視するように五郎左衛門が
河を越えての撤退を促す。ここで命をなくしては
元も子もない。
味方は七百~八百の軍勢しかないところへ、
三千を超える敵勢が挟み打ちで攻めかかったから
たまらない。ただ、父信秀の代から渡河戦に慣れ
ている信長方では、河を背にして一度『亀の甲の
型の陣形』を組んで防戦を図る。一列に河を渡っ
て逃げようとすると美濃勢の思うつぼとなるから
である。両側から攻めかかってきた美濃勢もこの
『亀の甲』を見るといったん矢合わせして十段
(108m)ほど引き退く。美濃勢も実は「本気で
信長を倒す!」と気合が入っている者と「今度
来られた時には是非お味方で!」と寝返りを狙っ
ている者が入り混じっており、斎藤竜興の鬨の声
には従うがうまく信長勢が逃げるのを願っている
者もいる。
信長方は一度広野に移動して軍勢を立て直し、
『亀の甲』の内側から馬喰・手負い・雑人を先に
河を越させ、降り注ぐ矢を楯で防御しながら撤退
する算段である。手負い・死人がそれでも多数
発生した。通常殿軍(しんがり)はその軍の最強
の部隊がつとめるが、この時は手勢が少ないこと
もあり、自動的に一番危険な渡河の差配を五郎
左衛門が受け持ち、次に危険な殿軍には信長
自身と最強の兵数名が残り、最後の仕舞いを行う
ことになった。
あらかた軍勢の渡河が終わり、取巻きのものと
残る信長が馬の鼻を敵軍に向けると、一瞬敵の
矢が止まる。殿軍としてしっかり撤退を成し遂げ
た敵将への尊敬の念からである。信長一行が河
を渡りきると再び矢の雨が降り注ぐ。河を渡った
あとは信長も足軽の動きのように馬を乗り回し、
全軍撤退したのであった。