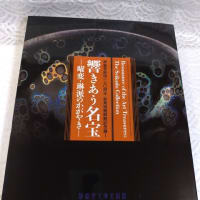<初出:2015年の再掲です>
巻四の七 信長、美濃を放置すること、付けたり、
一乗院覚慶『義秋』を名乗ること
永禄八年(一五六五)九月下旬、信長の軍は
這う這う(ほうほう)の体で美濃攻略戦から
引き退いた。堂洞取手攻めの陣中の信長・長秀
のところへ、「細川兵部大輔藤孝殿の差配に
より興福寺を逃れた一乗院覚慶(のちの足利
将軍義昭)が、八月に和田伊賀守惟政の和田城
に入った」との知らせが、惟政の弟である黒田
城主和田定利から寄せられてはいたが、今は
それどころではない。信長もよほど懲りたのか、
間近の小牧山の城へ戻ればよいものを、防御に
必要な軍勢だけを小牧山に残しすでに清洲の城
に落ち着いた。五郎左衛門は粛々と信長について
清洲まで来たが、愛馬『二寸(にき)殿』が怪訝
そうな目つきで信長のことを見るので、膝で首の
横を小突いて「じろじろ見るな」と無言で伝える。
お城の本丸北矢倉の御座所で信長は、丹羽
五郎左衛門長秀・柴田権六勝家を呼び寄せ三者
会談を始める。開かれたふすまの外では、渡り
廊下に松井友閑・木下藤吉郎が着座している。
「まずは無事で尾張に戻れたことに感謝して
『にっ!』」
これは三人が集まる時に必ず笑顔で話を始める
約束なので仕方ない。丹羽五郎左衛門長秀・
柴田権六勝家も『にっ!』と笑顔で返す。
「武士(もののふ)は莞爾として死すべし!
(武士は恐怖に引きつった顔で死んではなら
ない。敵が腰を抜かすような満面の笑顔で死ぬ
べきだ!)」という父信秀の教えを守っている
だけである。
「五郎左衛門よ、軍場に残してきた我が軍の兵
の亡骸の引き受けと、論功行賞と、協力してくれ
た尾張と美濃のすべての者(民・百姓・商家・
僧侶)に礼金を頼む。」
「御意。有閑よ、できるか?」
五郎左衛門が普通の口調で有閑に問いかけ、
有閑も藤吉郎と目を合わせて一度『うん』と
頷いてから「何とかいたします。」とこたえる。
これまで同様、松井有閑の「何とか」は「確実
に」を意味している。
「まあ、それは有閑・藤吉郎に任すとして、今後
美濃攻略の軍はどうする?」
権六勝家もいつも通り直接的な聞き方をしてくる。
「どうしたものか・・・今回も事前情報では
堂洞取手は容易に攻陥できるような気がしたが、
まだまだ斎藤山城守(道三)の時代からの古参
が張りきって攻めてくるからの~」
「力攻め・我攻めは三郎らしくないと思うが?」
勝家と長秀が、ほぼ同時に同じことを言う。
「う~む、よし。任せた、よきに計らえ!」
三人はしばらく美濃方面は様子見ということで
意見が一致した。
「それと藤吉郎よ、美濃勢を内側から切り崩す
方法があれば何か考えておけ!」
「ははっ」
と答えたはいいものの、当分藤吉郎はこの宿題
で頭を悩ますことになる。
一方、近江国和田城に入り和田伊賀守惟政の
庇護で命をつないだ一乗院覚慶は、この年の
十一月に近江矢島に移動し、翌永禄九年(一五
六六)二月僧籍から還俗し、名を『義秋』と
名乗ることとなった。またひそかに朝廷へ働き
かけ「従五位下左馬頭」の位官を獲得していた。
「従五位下」の位は、源頼朝がこの位を経由
して征夷大将軍になったことから「源氏にとって
由緒ある位」と考えられている。足利将軍家の
流れをくみ、一度僧籍に入った自分が還俗した今、
「自分が将軍の地位について、舎兄義輝が暗殺
された後の世を統べて見せる!」という『義秋』
の強い意志であろう。朝家への依頼は、和田
伊賀守惟政と細川兵部大輔藤孝の陰の働きで
実現したことは言うまでもない。
巻四の七 信長、美濃を放置すること、付けたり、
一乗院覚慶『義秋』を名乗ること
永禄八年(一五六五)九月下旬、信長の軍は
這う這う(ほうほう)の体で美濃攻略戦から
引き退いた。堂洞取手攻めの陣中の信長・長秀
のところへ、「細川兵部大輔藤孝殿の差配に
より興福寺を逃れた一乗院覚慶(のちの足利
将軍義昭)が、八月に和田伊賀守惟政の和田城
に入った」との知らせが、惟政の弟である黒田
城主和田定利から寄せられてはいたが、今は
それどころではない。信長もよほど懲りたのか、
間近の小牧山の城へ戻ればよいものを、防御に
必要な軍勢だけを小牧山に残しすでに清洲の城
に落ち着いた。五郎左衛門は粛々と信長について
清洲まで来たが、愛馬『二寸(にき)殿』が怪訝
そうな目つきで信長のことを見るので、膝で首の
横を小突いて「じろじろ見るな」と無言で伝える。
お城の本丸北矢倉の御座所で信長は、丹羽
五郎左衛門長秀・柴田権六勝家を呼び寄せ三者
会談を始める。開かれたふすまの外では、渡り
廊下に松井友閑・木下藤吉郎が着座している。
「まずは無事で尾張に戻れたことに感謝して
『にっ!』」
これは三人が集まる時に必ず笑顔で話を始める
約束なので仕方ない。丹羽五郎左衛門長秀・
柴田権六勝家も『にっ!』と笑顔で返す。
「武士(もののふ)は莞爾として死すべし!
(武士は恐怖に引きつった顔で死んではなら
ない。敵が腰を抜かすような満面の笑顔で死ぬ
べきだ!)」という父信秀の教えを守っている
だけである。
「五郎左衛門よ、軍場に残してきた我が軍の兵
の亡骸の引き受けと、論功行賞と、協力してくれ
た尾張と美濃のすべての者(民・百姓・商家・
僧侶)に礼金を頼む。」
「御意。有閑よ、できるか?」
五郎左衛門が普通の口調で有閑に問いかけ、
有閑も藤吉郎と目を合わせて一度『うん』と
頷いてから「何とかいたします。」とこたえる。
これまで同様、松井有閑の「何とか」は「確実
に」を意味している。
「まあ、それは有閑・藤吉郎に任すとして、今後
美濃攻略の軍はどうする?」
権六勝家もいつも通り直接的な聞き方をしてくる。
「どうしたものか・・・今回も事前情報では
堂洞取手は容易に攻陥できるような気がしたが、
まだまだ斎藤山城守(道三)の時代からの古参
が張りきって攻めてくるからの~」
「力攻め・我攻めは三郎らしくないと思うが?」
勝家と長秀が、ほぼ同時に同じことを言う。
「う~む、よし。任せた、よきに計らえ!」
三人はしばらく美濃方面は様子見ということで
意見が一致した。
「それと藤吉郎よ、美濃勢を内側から切り崩す
方法があれば何か考えておけ!」
「ははっ」
と答えたはいいものの、当分藤吉郎はこの宿題
で頭を悩ますことになる。
一方、近江国和田城に入り和田伊賀守惟政の
庇護で命をつないだ一乗院覚慶は、この年の
十一月に近江矢島に移動し、翌永禄九年(一五
六六)二月僧籍から還俗し、名を『義秋』と
名乗ることとなった。またひそかに朝廷へ働き
かけ「従五位下左馬頭」の位官を獲得していた。
「従五位下」の位は、源頼朝がこの位を経由
して征夷大将軍になったことから「源氏にとって
由緒ある位」と考えられている。足利将軍家の
流れをくみ、一度僧籍に入った自分が還俗した今、
「自分が将軍の地位について、舎兄義輝が暗殺
された後の世を統べて見せる!」という『義秋』
の強い意志であろう。朝家への依頼は、和田
伊賀守惟政と細川兵部大輔藤孝の陰の働きで
実現したことは言うまでもない。