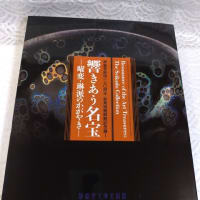<初出:2007年の再掲です。>
巻一の三 五郎左、つらつら考えること
黒田城を出発して半時(一時間)ほどたったころ、
愛馬『二寸殿(にきどの)』にのった丹羽五郎左衛
門長秀は丁度尾張一宮のそばを通りかかる。ここで
ひとまず休憩することにして、和田定利が「上総介
信長殿へ」と手渡したみやげ物の中身をあらためる
と、はたして信長の大好物の『真桑瓜の塩漬け』が
入っている。美濃名産の手土産である。「こういう
心配りが一流と二流の差であろう」と感じ入り、
「自分が尊敬する他国の武将と会うときも、和田の
ようにみやげ物選びには力を入れよう」と自戒する。
二日酔いを治すため内緒で少しだけ『真桑瓜の塩漬
け』を頂いたが・・・
さらに境内の湧き水を「ゴクリ」と飲み、頭をす
っきりさせて、これまでの尾張を取り巻く状況をつ
らつらと思い起こして見る。
*八年前の織田備後守信秀(信長の父)の死去と七
年前の平手中務丞政秀(信長の教育係)の死は痛
い!正直言って早すぎた!信長は父信秀から一国
の経営の仕方を勉強中であったし、自分も他国と
の取次ぎの仕方を政秀から勉強中であった。その
ため、二人で話し合い「我流でもなんとか前に進
まねば」と励ましあいながらやってきた。その意
味では三年前に柴田権六勝家が織田信行(信長の
舎弟)に愛想をつかして我が陣へ参加してくれた
のは渡りに舟であった。何もわからない中で、人
からは笑われたようだが軍(いくさ)の先例を学
ぶために『源平盛衰記』を三人で必死に読み込ん
だ。
*まず一番先に手がけたのは、周辺諸国の動向をい
ち早く知るため、『草・鳥・風』の仕組みの確立
であった。『草』というのは各地に定住する織田
家の支援者のことである。信秀の時代から織田家
信奉者は少なくなく、安祥・岡崎のあたりまでは
『草』が植えてある。『鳥』というのは移動する
織田家の支援者、例えば商人・僧侶などである。
『風』というのは情報操作のことであり、嘘であ
ろうが真実であろうが『鳥』を指定地域へ飛ばし
『草』に広めてもらう。
*次に手がけたのは、我流では合ったが三人で考え
出した『飛び馬(とびうま)』の仕組みである。
『飛び馬』というのは、本城から最前線まで半時
(一時間)の間に三回早馬を走らせる仕組みのこ
とであり、こうしておけば、もし進軍中に本城と
の補給路を断とうとした敵が出てきた場合に、即
座に知らせが入り対応することができる。三人の
中の誰がかけても国内の反乱分子を抑えることは
できないきわどい情勢であったので、「とにかく
自分たちの死ぬ可能性を低くする」必要があった。
顔を洗いもう一度「ゴクリ」と水を飲むと、おお
よそ頭の痛さはどこかに飛んでしまっている。
*まず美濃国の動向は、今回の和田定利との面談で
見当がついた。現在の主君は斎藤義龍であるが、
四年前の父斎藤道三殺害はさすがにやりすぎで、
家内でもかなりの不協和音が響いているとのこと。
尾張まで攻め込めるだけの余裕はない。
*信濃国の動向は、五年前武田晴信(のちの信玄)
の軍が東美濃に侵攻してきたときは肝を冷したが、
よくよく使いの者を遣り確かめたところ、「木材
の供給だけでなく河川運輸の通行税も欲しい」と
いうのが本音であった。ただ以前から国同士の関
係は悪くないので、信長の子息御坊丸を養子にお
くるところまで段取りを組んでおり急な動きは無
いはず。
*駿河国の動向は、六年前の武田・北条・今川の同
盟(善徳寺の会盟)が基本となっている。北条家
はもともと今川家の家宰として忠誠を尽くした伊
勢宗瑞(後の北条早雲)が初代であるところから、
多少のいざこざがあっても今川・北条の関係が悪
くなることはない。現在は北条家の関東での動き
が活発なので、今川家も興味の中心は関東方面で
ある。また家内の事情としては、『智謀神の如し』
と国内外で評価の高かった太原雪斎が五年前に死
に、中途半端な武将が我を張り自論を主張してい
る状態なので、統一が取れていない。今川家とし
ては余計な込み入った軍には巻きこまれたくない
というのが本音らしい。
*尾張国内では、どうも武衛公(斯波義銀)が三河
の吉良殿(義昭)・石橋殿と組んで、今川義元進
軍の援護射撃をしようとしているらしいが、これ
はわざと放置してある。今川軍と軍を構えるとき
にどうしても守護としての武衛公からの指示とい
う形が欲しいためである。
ここまで頭を整理してみたが、やはり苦々しく思
われるのは三河の松平次郎三郎元康(のちの徳川家
康)の動きである。「あの男のせいで織田も今川も
要らぬ軍をせねばならぬ」と思うと、二日酔いのせ
いではない、精神的な吐き気がしてくるのであった。
↓ランキングに参加中。ぽちっとお願いします
 にほんブログ村
にほんブログ村
<JR岐阜駅前の黄金の信長公像>
巻一の三 五郎左、つらつら考えること
黒田城を出発して半時(一時間)ほどたったころ、
愛馬『二寸殿(にきどの)』にのった丹羽五郎左衛
門長秀は丁度尾張一宮のそばを通りかかる。ここで
ひとまず休憩することにして、和田定利が「上総介
信長殿へ」と手渡したみやげ物の中身をあらためる
と、はたして信長の大好物の『真桑瓜の塩漬け』が
入っている。美濃名産の手土産である。「こういう
心配りが一流と二流の差であろう」と感じ入り、
「自分が尊敬する他国の武将と会うときも、和田の
ようにみやげ物選びには力を入れよう」と自戒する。
二日酔いを治すため内緒で少しだけ『真桑瓜の塩漬
け』を頂いたが・・・
さらに境内の湧き水を「ゴクリ」と飲み、頭をす
っきりさせて、これまでの尾張を取り巻く状況をつ
らつらと思い起こして見る。
*八年前の織田備後守信秀(信長の父)の死去と七
年前の平手中務丞政秀(信長の教育係)の死は痛
い!正直言って早すぎた!信長は父信秀から一国
の経営の仕方を勉強中であったし、自分も他国と
の取次ぎの仕方を政秀から勉強中であった。その
ため、二人で話し合い「我流でもなんとか前に進
まねば」と励ましあいながらやってきた。その意
味では三年前に柴田権六勝家が織田信行(信長の
舎弟)に愛想をつかして我が陣へ参加してくれた
のは渡りに舟であった。何もわからない中で、人
からは笑われたようだが軍(いくさ)の先例を学
ぶために『源平盛衰記』を三人で必死に読み込ん
だ。
*まず一番先に手がけたのは、周辺諸国の動向をい
ち早く知るため、『草・鳥・風』の仕組みの確立
であった。『草』というのは各地に定住する織田
家の支援者のことである。信秀の時代から織田家
信奉者は少なくなく、安祥・岡崎のあたりまでは
『草』が植えてある。『鳥』というのは移動する
織田家の支援者、例えば商人・僧侶などである。
『風』というのは情報操作のことであり、嘘であ
ろうが真実であろうが『鳥』を指定地域へ飛ばし
『草』に広めてもらう。
*次に手がけたのは、我流では合ったが三人で考え
出した『飛び馬(とびうま)』の仕組みである。
『飛び馬』というのは、本城から最前線まで半時
(一時間)の間に三回早馬を走らせる仕組みのこ
とであり、こうしておけば、もし進軍中に本城と
の補給路を断とうとした敵が出てきた場合に、即
座に知らせが入り対応することができる。三人の
中の誰がかけても国内の反乱分子を抑えることは
できないきわどい情勢であったので、「とにかく
自分たちの死ぬ可能性を低くする」必要があった。
顔を洗いもう一度「ゴクリ」と水を飲むと、おお
よそ頭の痛さはどこかに飛んでしまっている。
*まず美濃国の動向は、今回の和田定利との面談で
見当がついた。現在の主君は斎藤義龍であるが、
四年前の父斎藤道三殺害はさすがにやりすぎで、
家内でもかなりの不協和音が響いているとのこと。
尾張まで攻め込めるだけの余裕はない。
*信濃国の動向は、五年前武田晴信(のちの信玄)
の軍が東美濃に侵攻してきたときは肝を冷したが、
よくよく使いの者を遣り確かめたところ、「木材
の供給だけでなく河川運輸の通行税も欲しい」と
いうのが本音であった。ただ以前から国同士の関
係は悪くないので、信長の子息御坊丸を養子にお
くるところまで段取りを組んでおり急な動きは無
いはず。
*駿河国の動向は、六年前の武田・北条・今川の同
盟(善徳寺の会盟)が基本となっている。北条家
はもともと今川家の家宰として忠誠を尽くした伊
勢宗瑞(後の北条早雲)が初代であるところから、
多少のいざこざがあっても今川・北条の関係が悪
くなることはない。現在は北条家の関東での動き
が活発なので、今川家も興味の中心は関東方面で
ある。また家内の事情としては、『智謀神の如し』
と国内外で評価の高かった太原雪斎が五年前に死
に、中途半端な武将が我を張り自論を主張してい
る状態なので、統一が取れていない。今川家とし
ては余計な込み入った軍には巻きこまれたくない
というのが本音らしい。
*尾張国内では、どうも武衛公(斯波義銀)が三河
の吉良殿(義昭)・石橋殿と組んで、今川義元進
軍の援護射撃をしようとしているらしいが、これ
はわざと放置してある。今川軍と軍を構えるとき
にどうしても守護としての武衛公からの指示とい
う形が欲しいためである。
ここまで頭を整理してみたが、やはり苦々しく思
われるのは三河の松平次郎三郎元康(のちの徳川家
康)の動きである。「あの男のせいで織田も今川も
要らぬ軍をせねばならぬ」と思うと、二日酔いのせ
いではない、精神的な吐き気がしてくるのであった。
↓ランキングに参加中。ぽちっとお願いします
<JR岐阜駅前の黄金の信長公像>