昨日は一日家でおとなしくしていました
ようやく、大腿骨頸部骨折の患者様(人工骨頭置換術後7日目)の看護展開を仕上げて…
次は、心不全の患者様にしようと決めたところで勉強はおしまい
読んだ本はこれ。

内田先生の漫画論です。
この本の中で紹介されていて、前から読んでみたいと思っていたので、読みましたよ。

とても長い作品なんですよねぇ。歴史物は小説も読んだことがなかったのですが。
面白いです
内田先生の本によると、(養老孟司先生の説を紹介して)「日本人が文字を読むとき脳内の二か所を同時に使っている」
のだそうです。漢字は表意文字で図表として認識して、ひらがな、カタカナは表音文字なので音声として認識されるのだと。
なので、日本でマンガが生まれたっていうこと。
このあたりの話しが、自分が関わる「手話」ってことばにちょっと置き換えていたんです。
聞こえない人が手話を話す時には「映像が見えている」というのを書いているのは、長谷川さん

長谷川さんに、「幹さんは見える人」って言われるのにいつも抵抗を感じていたのですが。
見えやすいようになるのは…ってことに、内田先生の本を読んで…「 」
」
手話を観る時も、両方の頭使っているんだ!ちょうど、本を読むときの「漢字」と「かな」の部分みたいにして
読み分けているのかも…
もうちょっと考えてみようっと
今日は北陸放送で、広報番組の手話収録です

ようやく、大腿骨頸部骨折の患者様(人工骨頭置換術後7日目)の看護展開を仕上げて…

次は、心不全の患者様にしようと決めたところで勉強はおしまい

読んだ本はこれ。

内田先生の漫画論です。
この本の中で紹介されていて、前から読んでみたいと思っていたので、読みましたよ。

とても長い作品なんですよねぇ。歴史物は小説も読んだことがなかったのですが。
面白いです

内田先生の本によると、(養老孟司先生の説を紹介して)「日本人が文字を読むとき脳内の二か所を同時に使っている」
のだそうです。漢字は表意文字で図表として認識して、ひらがな、カタカナは表音文字なので音声として認識されるのだと。
なので、日本でマンガが生まれたっていうこと。
このあたりの話しが、自分が関わる「手話」ってことばにちょっと置き換えていたんです。
聞こえない人が手話を話す時には「映像が見えている」というのを書いているのは、長谷川さん


長谷川さんに、「幹さんは見える人」って言われるのにいつも抵抗を感じていたのですが。
見えやすいようになるのは…ってことに、内田先生の本を読んで…「
 」
」手話を観る時も、両方の頭使っているんだ!ちょうど、本を読むときの「漢字」と「かな」の部分みたいにして
読み分けているのかも…

もうちょっと考えてみようっと

今日は北陸放送で、広報番組の手話収録です













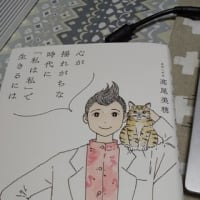





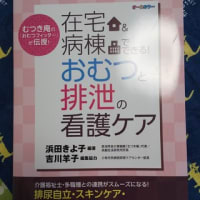

「幹さんは見える人」とおっしゃっているのだろうと考えます。
逆に、耳が聞こえない人は、幹さんの手の動きから映像化して「見て」いるので
「耳が聞こえない人は見る人」と言われるのだろうと推察します。
心の動きを表現しているのであって、聞こえない人が映像で「見える」ことを手話で、幹さんに「見せる」時は、主体が聞こえない人で、客体が幹さんです。
大きなちがいは、公演中は聞こえない人の耳に幹さんがなっているので、手話をしている幹さんが音声を映像化する主体で、客体が聞こえない人という事だと思います。
つまり、幹さんは音声を映像化して、聞こえない人に見せているから、長谷川さんは、
「幹さんは見える人」という役割分担という意味でおっしゃっているのだろうと考えます。
日本で漫画が発達したのは音声言語を映像化する機会が中国人より多いので、映像化する脳機能が中国人より発達しているということかもしれませんね。