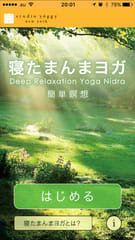定期連絡のように伯父とは電話連絡を行っていたのですが、その日は様子が違いました。
朝一番に電話したところ「伯母さんが左半身に力が入らず床に這いつくばっている!どうすればよいか?」と慌てており、携帯電話を直接伯母の耳に当ててもらって私が直に確認しました。
・左手左足に力が入らない状態が前日夜から続いていた。
・発語がうまくいかずろれつが回らない。
・唾液が少なく口が乾く。
・血圧が上がっているようで頭がボーっとする。
・だけど軽傷だから救急車は呼ばなくてよい。
と本人は言っています。
その時私は東京葛飾に居たので、まずは緊急通報を行う方法を確認すべく #7119 に電話しますが、大阪吹田での救急車は東京からは呼べないとのこと。
何とか伯父から 119番通報 をするしかないことが分かりました。
本人の抵抗を振り切りながら91歳の伯父が頑張って通報し、救急病院に搬送されたのは最初の電話から1時間半後でした。
私も取るものとりあえず、新幹線で大阪に向かい、入院先の救急病院へ直行しました。
脳疾患用のICU(集中治療室)にて処置中であり、直接会話はできる状況でした。
伯父と一緒に入院や治療方針の説明を受け、必要な部分にサインを代筆したのですが、なんと91歳の伯父では入院時の保証人になり得ないということが判明します。
老人ホーム入居契約の連帯保証人もそうですが、老夫婦は若い世代に助けを求めないと、入院も入居もできないんですかね。
実際問題、保証人が不在でスタックするケースはないのでしょうか?
何とも言えない消化不良な感覚のまま、その日は急遽吹田市内に宿を取り、翌日の病院対応に備えました。
・ ・ ・
伯母 退院までの20日間、伯父の老人ホームではコロナ感染者急増による外出・面会禁止の措置が取られており治療方針合意などの手続きの為、私は追加2回ほど日帰りで吹田往復しました。
そして伯母も観念し、退院とともに老人ホーム入居を承諾してくれました。
退院時の介護タクシーサポートなどもコロナ感染予防対策の観点から、老人ホームの介護スタッフの力を借りることはできず、私がレンタカーを借りてサポートしました。
残るは叔母の住んでいた住居の整理・退去、銀行口座の整理と手続きです。