
小学1年生でエレクトーンから始めた音楽キャリア。確か「固定ド」で習ってた筈なんだけど、途中でほっぽり出したため絶対音感も付かず、学校の音楽の授業では固定ドなもんだから、それが当たり前だと思っていた。でも、大学の軽音楽部でそうではない奴らがちらほらいて、バークリーに行ってみたら、完全に全てが「移動ド」で授業が展開される。え?こんな世界が有ったの?って感じ。まぁ、絶対音感が無いので、「今はこれがドだよ~ん。」と言われれば、あ~そうですかぁ的にやってたので、日本の音大卒で完全なる絶対音感の有る人ほどは苦しむ事も無く、適当ぉ~にテストに合格したりしてきたんだけど、なんかそのまま適当ってのも居心地悪く、また、耳がそれほど良くないってのも音楽家として常にコンプレックスで何とかしたいと漠然と思っていた。
日本に帰って来て、歌の伴奏の仕事をやるようになって(NYでも勿論やってたんだけど)、スタンダードをとんでもないキーでやるボーカリストが居て、それに対応できず、これに対応するには移動ドしかないと思った。ずっと固定ドだったし、絶対音感が無いにしろ、好きな音楽とかはテープ・スピードが異なると(アナログのカセット・テープは再生機材によって、微妙なテープの回転速度の誤差が有る)吐き気がするほど気持ち悪くなり、ボーカリストが曲のキーを変えると全く違う曲に聴こえていた。(だから、曲のキーを変えるのなんて、作曲者の意図を無視した作曲家に対する冒涜だと思い、かつてはその行為自体を軽蔑していた。) でも、仕事でそんなワガママは言ってられない。DbMaj7を弾きはじめた弾き語りの御姐さんに、「イパネマのサビなんて、どれもミーファミレミレドーレーよ。」と言われた時は衝撃だった。(笑) それから「コールユーブンゲン」を勧められ、写真にある本を買って改めて移動ドで歌う練習を始めたのだ。
バークリーである程度やってたものの、ちゃんと身についていないのは分かってたので、有る時を境に一念発起して「全てを移動ドで歌いきる」をやり始めた。中々上手く行かないものの努力を重ね、まずは、ごく当たり前なバップのメロディーラインあたりは移動ドで歌って他のキーに移調ってのも出来るようになった。(その昔は固定でひたすらこういう練習していたので・・) ディミニッシュ・スケールやホールトーン・スケール、またヘキサトニック・スケールなど、他のキーと共通の構成音を持つスケールで構成されたラインも、それぞれのキーで歌い(つまり、同じシェラブルで指は違うという意味)、決して他キー同士で共有する事なく別々に歌い切る事によって、そういう複雑なラインでもドミナント・モーションやトーナリティーを深く感じる事が可能となった。ここまで来ると、例え出音が間違ってなくても、自分の歌い方が間違ってれば自分の心の中でNGを出す様な作業で、聴き手とは全く関係のない「趣味の世界」となってしまう。(笑)
ここで本題。
問題はマイナースケールなのである。バークリーでは「do re me fa sol le te do」と歌わされてた記憶がある。そのせいか、Ⅴ7-Ⅰmの場合、ルート・モーションがどうしても「sol do」と聴こえてしまう。今もそれが相変わらずあまり直っていない。しかしながら、スタンダードではリラティブ・メジャー ←→ リラティブ・マイナーの移行はごく当たり前だ。例えば「オール・ザ・シングス・ユー・アー」とか「枯葉」とか。じゃあ、あの枯葉の簡単なAメロを最初はメジャーキーの「la ti do fa」と歌ってるのに、途中でわざわざマイナーキーに転調して「sol la ti me」と歌うのかというと、それって凄く非合理的に感じる。それを転調と感じず同調だと思えばこんな機能的な事は無い。つまり「mi fi si do」と歌っちゃえば、転調とみなして歌い直す必要が無くなる。ただしその場合、Ⅴ7-ⅠmはⅢ7(正式にはⅤ7ofⅥ)-Ⅵmであり、そのルートモーションは「mi la」と聴こえなくてはならないのだ。この辺りが実は合点が行かず苦しむ事が多いのだが、徐々に慣れつつある。スタンダードでは当たり前の#Ⅳm7(b5)―Ⅶ7(b9)とかⅢm7(b5)―Ⅵ7(b9)はどう歌うんだ・・とか、色々問題点は有るものの、なるべく転調しないように歌う事を心がけていると、トーナリティーが見えて来て、演奏が無機質にならず楽しいものになる。
しかし同時に、モード曲で、例えばドリアンを「re mi fa sol la ti do」と歌う事で、まるでバップみたいに演奏する様になってしまい、学生時代にやってたコルトレーンもどきのペンタトニックでゴリゴリ・プレーってのが中々出て来なくて困っている。あぁ、昔って「コードが一発!」っての楽しかったよなぁ。(苦笑)
で、今回、この「コールユーブンゲン移動ド唱」のCDを購入した大きな理由は、クラシックの移動ドってどういう歌われ方をされてるのか?という事だ。まず気になったのが、前述のマイナー・キーである。弾き語りの御姐さんは「la ti do..」で歌ってたけど果たして??そして、本日その待ちに待ったCDが届き、本では終盤にあたる第14章から聴き始めた。やはり「la ti do」である。残念ながらメロディック・マイナーで「mi fi si la」等のクロマティック唱法でないのと、嬰は短調の章では、C#マイナーから明らかにAメジャーに転調している所をC#マイナー=Eメジャーで歌い切ってるのが違和感が有るけれど、これを聴くだけでも自分の「耳グセ」がかなり改善されるのでは・・との期待が持てる。膨大な量の音源なので、まだ全て聴いたわけではないのだが・・。
長年、固定ドでやって来たので、いまだに誤作動が脳内で起こるのだけど、こういう人体実験をやるのが好きだし、大学時代、バブル期で一流企業から引く手数多(あまた)だった頃に会社員への道をかなぐり捨てて、こんなリスキーな世界に飛び込んだのも、こういう研究がトコトンやりたかったからだ。実験材料である自分自身が、これまた全てにおいて中途半端で良い実験になる。(笑) そして、レッスンやライブに於いて、これらの実験結果を発表/活用出来る環境にある事は大変喜ばしい事である。
しかし、練習用としては優れていても、タイトルも歌詞も、また音楽的イメージも何も無いメロディーの数々を情感たっぷりに、オペラの名手の先生方が「ソ~、ミファソラソ~」と歌い上げるのを聴いてると、素晴らしいけど笑ってしまう。すいません。でも、これがこれから私のヘヴィー・ローテーション。歌ももうちとばかし上手くなりたい。(笑)
日本に帰って来て、歌の伴奏の仕事をやるようになって(NYでも勿論やってたんだけど)、スタンダードをとんでもないキーでやるボーカリストが居て、それに対応できず、これに対応するには移動ドしかないと思った。ずっと固定ドだったし、絶対音感が無いにしろ、好きな音楽とかはテープ・スピードが異なると(アナログのカセット・テープは再生機材によって、微妙なテープの回転速度の誤差が有る)吐き気がするほど気持ち悪くなり、ボーカリストが曲のキーを変えると全く違う曲に聴こえていた。(だから、曲のキーを変えるのなんて、作曲者の意図を無視した作曲家に対する冒涜だと思い、かつてはその行為自体を軽蔑していた。) でも、仕事でそんなワガママは言ってられない。DbMaj7を弾きはじめた弾き語りの御姐さんに、「イパネマのサビなんて、どれもミーファミレミレドーレーよ。」と言われた時は衝撃だった。(笑) それから「コールユーブンゲン」を勧められ、写真にある本を買って改めて移動ドで歌う練習を始めたのだ。
バークリーである程度やってたものの、ちゃんと身についていないのは分かってたので、有る時を境に一念発起して「全てを移動ドで歌いきる」をやり始めた。中々上手く行かないものの努力を重ね、まずは、ごく当たり前なバップのメロディーラインあたりは移動ドで歌って他のキーに移調ってのも出来るようになった。(その昔は固定でひたすらこういう練習していたので・・) ディミニッシュ・スケールやホールトーン・スケール、またヘキサトニック・スケールなど、他のキーと共通の構成音を持つスケールで構成されたラインも、それぞれのキーで歌い(つまり、同じシェラブルで指は違うという意味)、決して他キー同士で共有する事なく別々に歌い切る事によって、そういう複雑なラインでもドミナント・モーションやトーナリティーを深く感じる事が可能となった。ここまで来ると、例え出音が間違ってなくても、自分の歌い方が間違ってれば自分の心の中でNGを出す様な作業で、聴き手とは全く関係のない「趣味の世界」となってしまう。(笑)
ここで本題。
問題はマイナースケールなのである。バークリーでは「do re me fa sol le te do」と歌わされてた記憶がある。そのせいか、Ⅴ7-Ⅰmの場合、ルート・モーションがどうしても「sol do」と聴こえてしまう。今もそれが相変わらずあまり直っていない。しかしながら、スタンダードではリラティブ・メジャー ←→ リラティブ・マイナーの移行はごく当たり前だ。例えば「オール・ザ・シングス・ユー・アー」とか「枯葉」とか。じゃあ、あの枯葉の簡単なAメロを最初はメジャーキーの「la ti do fa」と歌ってるのに、途中でわざわざマイナーキーに転調して「sol la ti me」と歌うのかというと、それって凄く非合理的に感じる。それを転調と感じず同調だと思えばこんな機能的な事は無い。つまり「mi fi si do」と歌っちゃえば、転調とみなして歌い直す必要が無くなる。ただしその場合、Ⅴ7-ⅠmはⅢ7(正式にはⅤ7ofⅥ)-Ⅵmであり、そのルートモーションは「mi la」と聴こえなくてはならないのだ。この辺りが実は合点が行かず苦しむ事が多いのだが、徐々に慣れつつある。スタンダードでは当たり前の#Ⅳm7(b5)―Ⅶ7(b9)とかⅢm7(b5)―Ⅵ7(b9)はどう歌うんだ・・とか、色々問題点は有るものの、なるべく転調しないように歌う事を心がけていると、トーナリティーが見えて来て、演奏が無機質にならず楽しいものになる。
しかし同時に、モード曲で、例えばドリアンを「re mi fa sol la ti do」と歌う事で、まるでバップみたいに演奏する様になってしまい、学生時代にやってたコルトレーンもどきのペンタトニックでゴリゴリ・プレーってのが中々出て来なくて困っている。あぁ、昔って「コードが一発!」っての楽しかったよなぁ。(苦笑)
で、今回、この「コールユーブンゲン移動ド唱」のCDを購入した大きな理由は、クラシックの移動ドってどういう歌われ方をされてるのか?という事だ。まず気になったのが、前述のマイナー・キーである。弾き語りの御姐さんは「la ti do..」で歌ってたけど果たして??そして、本日その待ちに待ったCDが届き、本では終盤にあたる第14章から聴き始めた。やはり「la ti do」である。残念ながらメロディック・マイナーで「mi fi si la」等のクロマティック唱法でないのと、嬰は短調の章では、C#マイナーから明らかにAメジャーに転調している所をC#マイナー=Eメジャーで歌い切ってるのが違和感が有るけれど、これを聴くだけでも自分の「耳グセ」がかなり改善されるのでは・・との期待が持てる。膨大な量の音源なので、まだ全て聴いたわけではないのだが・・。
長年、固定ドでやって来たので、いまだに誤作動が脳内で起こるのだけど、こういう人体実験をやるのが好きだし、大学時代、バブル期で一流企業から引く手数多(あまた)だった頃に会社員への道をかなぐり捨てて、こんなリスキーな世界に飛び込んだのも、こういう研究がトコトンやりたかったからだ。実験材料である自分自身が、これまた全てにおいて中途半端で良い実験になる。(笑) そして、レッスンやライブに於いて、これらの実験結果を発表/活用出来る環境にある事は大変喜ばしい事である。
しかし、練習用としては優れていても、タイトルも歌詞も、また音楽的イメージも何も無いメロディーの数々を情感たっぷりに、オペラの名手の先生方が「ソ~、ミファソラソ~」と歌い上げるのを聴いてると、素晴らしいけど笑ってしまう。すいません。でも、これがこれから私のヘヴィー・ローテーション。歌ももうちとばかし上手くなりたい。(笑)












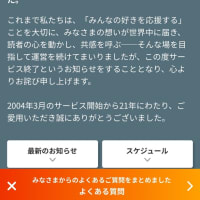







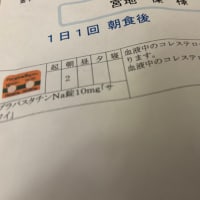







高音・中音・低音
とあったと思います。
合唱の時、パートが分かれているように各パートの人が歌いやすいように書かれてあったのでは…
一般的には、中音用を高校や音大では使っているようですが、男性の場合は低音用を使われると楽と思いますよ!
なんか、ケイタイで見ると、コードネームが全部文字化けしてますね~。すいません。
夕べ、荻と話してて、「ひょっとして、相対音感の事を言ってはるのかな?」と思いました。
「移動『ド』」って相対音感の事ですか?違ってたらごめんなさいm(__)m
しかし、何をもって絶対か相対かを判別するのって難しいよね。自分も、ソロしてる時に基本は相対音感の筈なのに、直感的に音を選ぶ時は絶対音感的なものを使ってるし。絶対音感の持ち主で相対的な感じ方をする人も友人には居るし。
ドがキーごとに移動しますよって言い方、結構分かりやすくて好き。
だって、カラオケ歌う人は全員相対音で歌ってますよ!だから、キー上げ下げしてもスムーズに歌える・・・。
管楽器の人ってメロディーも絶対音で感じてるんですか?
Ⅰ、Ⅳ、Ⅴのコードの座標をあまり意識してないのですか?
確かに、複雑な進行、ファンクションが斬新なコード進行の曲は、相対音感だと歌い方に困る事があるね。ただ、使えるスケールから音をチョイスして吹く演奏方だと、極めて理論的でメロディアスにならない事が多い。学生時代にこういうジレンマに陥り、固定ドから移動ドに無理矢理変えたっていう経緯が有る。
因みにⅠ、Ⅳ、Ⅴは極めてダイアトニックなコード群なので、それぞれのルートをKEYと捉える事はしないので、一括りにする事が出来る。座標が変わる事ばかり意識すると逆に不自然になる。例えばGのブルースで、それぞれのコード(G7、C7、D7)を意識し過ぎて演奏するより、Gマイナー・ペンタ1発で演奏した方が自然だし簡単でしょ?ただ、ジャズの場合は、それぞれのコードで使えるテンションが違う事を利用して一時的な転調をわざと脳内で想定してより複雑なサウンドを導き出す傾向が有る。ビ・バップ的な発想だけど。マイケル・ブレッカーは両方のやり方を絶妙なバランスで演奏出来た最初のサックス・プレーヤーだと思う。
ま、やり方は人それぞれって事です。(笑)
ポップスとかロックやらSOULやらで、譜面を立てる管楽器の人に軽い嫌悪感を感じてたんですが(フルバンやらオーケストラやら)、さんざん練習した曲の構成もコード進行も意識でけへんのかえ!って・・。思ってましたが、もし、相対音で対峙してないなら、譜面要りますよね・・・。
認識不足でした・・・。
ま、これらは言い訳っちゃ言い訳になるけど、世の中には、譜面一発で覚えられる人もいるし、出来る人は出来るし出来ない人も多いってこと。ただ譜面を覚える事だけが重要ではなく、それ以外の才能を認められて、そのバンドに呼ばれてステージに上がってる人も居るわけ。