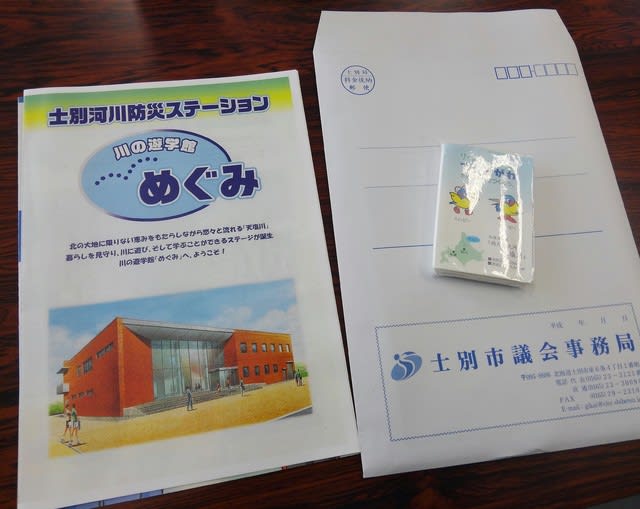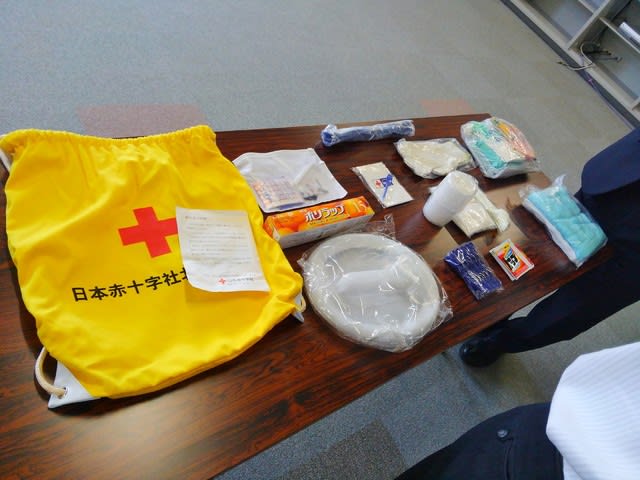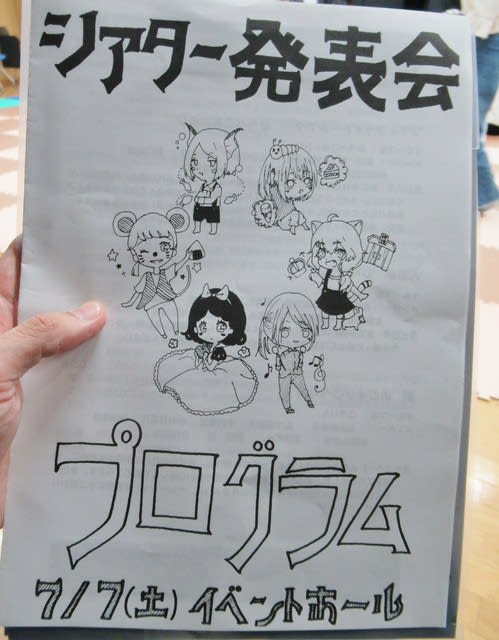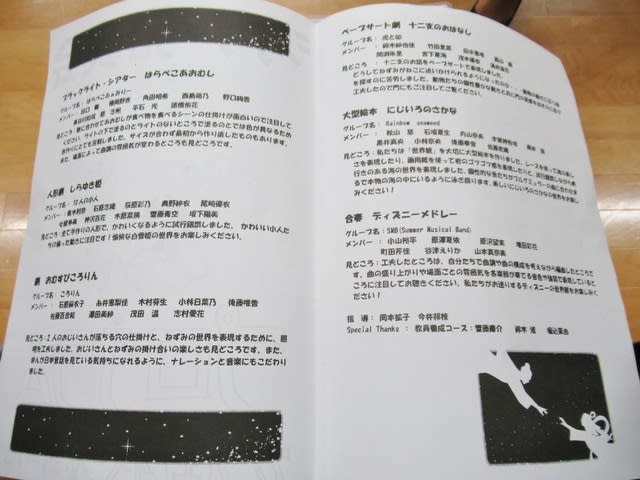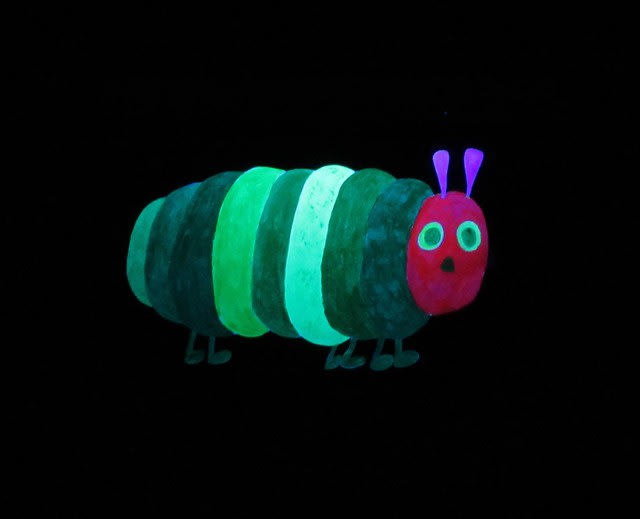九州初上陸!
毎年恒例の自治体学校が、今年は九州を会場に7月21日~23日の3日間の日程で開催されました。
22日は諫早湾に行ってきました。
大自然を破壊し、漁民と農民を対立させてしまった干拓事業について学ぶためです。
公共事業によって住民同士が対立する構図は、実際に高崎市でも見られること。
改めて、公共事業のあり方について考えさせられました。
諫早湾を見渡せる白木峰高原から。

左側が諫早湾、白いラインが潮受け堤防、その右側が調整池で、その更に右側が干拓した農地「中央干拓地」です。
向こうに見える山は、27年前に大噴火した雲仙岳。
諫早市ゆうゆうランド干拓の里にある、むつごろう水族館へ。

諫早湾の干潟に生息していたムツゴロウとシオマネキです。

流木にたたずむトビハゼ。水面を忍者のように飛び跳ねる、なんとも不思議な魚です。

潮受け堤防で諫早湾が閉め切られたことによって、ムツゴロウやトビハゼだけでなく多くの生命が姿を消しました。
その影響は有明海にも。
漁民が被った被害は甚大で、多くの漁民は潮受け堤防の開門を切望しています。
堤防を閉門する様子が「ギロチン」と形容されているゆえんなのかもしれません。

干拓が行われる以前、諫早湾は「ムツカケ漁」という伝統漁法が盛んでした。
子どもの頃、釣りキチ三平がムツカケをする姿に憧れたものです。

潮受け堤防から見た調整池。腐敗性の有機物を含む水質です。

調整池の水を諫早湾に排水するエリアでは、たくさんの鵜が汚染した水質にも適応できるボラの幼魚を狙っていました。

中央干拓地にて。

国や県が推奨して干拓した農地ですが、調整池の水が様々な問題が浮上して撤退した農家も多数。
農地の土の室は固い粘土質で、作物を栽培に適しているとはとても言えません。

調整池で越冬するカモが農作物を食い荒らしてしまう問題も。
漁民が潮受け堤防開門を望む一方、農民は開門に反対していましたが、国や県にそそのかされて農業を始めてしまったと気づいた一部の農民は、漁民と共に堤防開門を訴え始めています。
毎年恒例の自治体学校が、今年は九州を会場に7月21日~23日の3日間の日程で開催されました。
22日は諫早湾に行ってきました。
大自然を破壊し、漁民と農民を対立させてしまった干拓事業について学ぶためです。
公共事業によって住民同士が対立する構図は、実際に高崎市でも見られること。
改めて、公共事業のあり方について考えさせられました。
諫早湾を見渡せる白木峰高原から。

左側が諫早湾、白いラインが潮受け堤防、その右側が調整池で、その更に右側が干拓した農地「中央干拓地」です。
向こうに見える山は、27年前に大噴火した雲仙岳。
諫早市ゆうゆうランド干拓の里にある、むつごろう水族館へ。

諫早湾の干潟に生息していたムツゴロウとシオマネキです。

流木にたたずむトビハゼ。水面を忍者のように飛び跳ねる、なんとも不思議な魚です。

潮受け堤防で諫早湾が閉め切られたことによって、ムツゴロウやトビハゼだけでなく多くの生命が姿を消しました。
その影響は有明海にも。
漁民が被った被害は甚大で、多くの漁民は潮受け堤防の開門を切望しています。
堤防を閉門する様子が「ギロチン」と形容されているゆえんなのかもしれません。

干拓が行われる以前、諫早湾は「ムツカケ漁」という伝統漁法が盛んでした。
子どもの頃、釣りキチ三平がムツカケをする姿に憧れたものです。

潮受け堤防から見た調整池。腐敗性の有機物を含む水質です。

調整池の水を諫早湾に排水するエリアでは、たくさんの鵜が汚染した水質にも適応できるボラの幼魚を狙っていました。

中央干拓地にて。

国や県が推奨して干拓した農地ですが、調整池の水が様々な問題が浮上して撤退した農家も多数。
農地の土の室は固い粘土質で、作物を栽培に適しているとはとても言えません。

調整池で越冬するカモが農作物を食い荒らしてしまう問題も。
漁民が潮受け堤防開門を望む一方、農民は開門に反対していましたが、国や県にそそのかされて農業を始めてしまったと気づいた一部の農民は、漁民と共に堤防開門を訴え始めています。