法制審の答申案の中に,刑事裁判手続に犯罪被害者も参加できるような制度を導入する旨含まれていることが報じられており,「犯罪被害者の権利拡大を図る」などとコメントされています。
一方で,裁判員制度については,約8割の国民が参加に消極的である旨の世論調査結果も報じられています。
さらに,連日のように,刑事裁判に関するニュースにおいて「今日の法廷で,**被告は**をした」等と報じられています。
一方で,「そもそも刑事裁判ってどういう仕組みなんだろう」「どういう流れで進んでいくんだろう」「何で検察官の求刑がそのまま判決にならないんだろう」などという疑問をお持ちの方も多いかと思います。
そこで,今回は刑事裁判の仕組みや流れについて説明したいと思います。
なお,刑事裁判制度の大前提にあるのは,「えん罪防止」という観点です。したがって,被告人の権利が厚く保障されている背景については,私の過去のシリーズ(「被疑者,被告人の権利について」と 「逮捕勾留について」)をご覧ください。
第1 そもそも論
1 刑事裁判って何?
刑事裁判とは,犯罪者を刑務所送りにするための裁判です。刑事裁判では,犯罪を犯した容疑者のことを「被告人」と呼びます。
そして,「こんな犯罪をしたんだ。けしからん奴だ」と追求するのが,「検察官」です。
刑事裁判では,検察官vs被告人の対決,ということになります。
2 被告人に弁護士が付くのはなぜ?
ところで,被告人には弁護士(刑事裁判では「弁護人」と呼びます)がつきますが,それはなぜでしょうか。
それは,「検察官は法律のプロである。ところが被告人は法律の素人であるため,まともに戦えない。そこで,検察官とまともに戦えるために,法律のプロである弁護士を付ける」というものです。
また,被告人は警察に逮捕されているため,自由に活動ができません。証拠集めや証人の用意,さらには被害者との示談交渉なども必要となります。そのための代理人として弁護人は必須なのです。
いわば「朝青龍と戦うためには,自分じゃ勝てないから千代大海を雇って戦ってもらう」ようなものなのです(かなり強引な例えかな?)。
3 国選弁護人って何?
お金がない被告人に対し,国が弁護人を付ける制度です。刑事裁判の多くは,この国選弁護人になります。
これは,お金のあるなしで刑事裁判の結果が変わってしまうということを防ぐためのもので,憲法上認められた権利です。いわば,格差社会対策とも言えるでしょう。
ただし,判決の際に,被告人にこの費用の負担を命じることができますので,全部が全部タダで済むとは限りません。
4 誰が裁判をやるの?
裁判官です。じゃなくて,どこの裁判所がやるのか,ということです。
多くの事件は,地方裁判所が第1審となります。そして,通常は裁判官1人で裁判をしますが,重大事件(殺人など)の場合は,裁判官3人で審理します(これを「合議事件」といいます。)。
一方,軽微な事件(窃盗など)については,簡易裁判所が第1審となり,裁判官1人で裁判をします。
第1審の判決で不服があった場合は,地裁簡裁問わず,第2審は高等裁判所になり,裁判官3人で裁判をします。高裁の判決に不服があれば,最後の砦の最高裁で裁判をします。ここでは,5人の裁判官で審理しますが,場合によっては15人の大法廷で審理する場合もあります(ただし,刑事裁判ではほとんど大法廷は開かない。)。
長くなるので,次回に続きます。
よく分かる(?)シリーズ 刑事裁判の仕組み(その2)
よく分かる(?)シリーズ 刑事裁判の仕組み(その3)
よく分かる(?)シリーズ 刑事裁判の仕組み(その4)
よろしければ1クリックお願いしますm(__)m→人気blogランキングへ

TB先一覧
http://cgi.members.interq.or.jp/enka/svkoya/blog/enka/archives/2007_2_2_526.html
http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/17473f2d8408b80ba975d7ccdc29a3c9
http://blog.livedoor.jp/nob11/archives/50877424.html
http://imprezza-inada-1973.seesaa.net/article/32675456.html
http://onojo-kawakubo.seesaa.net/article/32511147.html
一方で,裁判員制度については,約8割の国民が参加に消極的である旨の世論調査結果も報じられています。
さらに,連日のように,刑事裁判に関するニュースにおいて「今日の法廷で,**被告は**をした」等と報じられています。
一方で,「そもそも刑事裁判ってどういう仕組みなんだろう」「どういう流れで進んでいくんだろう」「何で検察官の求刑がそのまま判決にならないんだろう」などという疑問をお持ちの方も多いかと思います。
そこで,今回は刑事裁判の仕組みや流れについて説明したいと思います。
なお,刑事裁判制度の大前提にあるのは,「えん罪防止」という観点です。したがって,被告人の権利が厚く保障されている背景については,私の過去のシリーズ(「被疑者,被告人の権利について」と 「逮捕勾留について」)をご覧ください。
第1 そもそも論
1 刑事裁判って何?
刑事裁判とは,犯罪者を刑務所送りにするための裁判です。刑事裁判では,犯罪を犯した容疑者のことを「被告人」と呼びます。
そして,「こんな犯罪をしたんだ。けしからん奴だ」と追求するのが,「検察官」です。
刑事裁判では,検察官vs被告人の対決,ということになります。
2 被告人に弁護士が付くのはなぜ?
ところで,被告人には弁護士(刑事裁判では「弁護人」と呼びます)がつきますが,それはなぜでしょうか。
それは,「検察官は法律のプロである。ところが被告人は法律の素人であるため,まともに戦えない。そこで,検察官とまともに戦えるために,法律のプロである弁護士を付ける」というものです。
また,被告人は警察に逮捕されているため,自由に活動ができません。証拠集めや証人の用意,さらには被害者との示談交渉なども必要となります。そのための代理人として弁護人は必須なのです。
いわば「朝青龍と戦うためには,自分じゃ勝てないから千代大海を雇って戦ってもらう」ようなものなのです(かなり強引な例えかな?)。
3 国選弁護人って何?
お金がない被告人に対し,国が弁護人を付ける制度です。刑事裁判の多くは,この国選弁護人になります。
これは,お金のあるなしで刑事裁判の結果が変わってしまうということを防ぐためのもので,憲法上認められた権利です。いわば,格差社会対策とも言えるでしょう。
ただし,判決の際に,被告人にこの費用の負担を命じることができますので,全部が全部タダで済むとは限りません。
4 誰が裁判をやるの?
裁判官です。じゃなくて,どこの裁判所がやるのか,ということです。
多くの事件は,地方裁判所が第1審となります。そして,通常は裁判官1人で裁判をしますが,重大事件(殺人など)の場合は,裁判官3人で審理します(これを「合議事件」といいます。)。
一方,軽微な事件(窃盗など)については,簡易裁判所が第1審となり,裁判官1人で裁判をします。
第1審の判決で不服があった場合は,地裁簡裁問わず,第2審は高等裁判所になり,裁判官3人で裁判をします。高裁の判決に不服があれば,最後の砦の最高裁で裁判をします。ここでは,5人の裁判官で審理しますが,場合によっては15人の大法廷で審理する場合もあります(ただし,刑事裁判ではほとんど大法廷は開かない。)。
長くなるので,次回に続きます。
よく分かる(?)シリーズ 刑事裁判の仕組み(その2)
よく分かる(?)シリーズ 刑事裁判の仕組み(その3)
よく分かる(?)シリーズ 刑事裁判の仕組み(その4)
よろしければ1クリックお願いしますm(__)m→人気blogランキングへ
TB先一覧
http://cgi.members.interq.or.jp/enka/svkoya/blog/enka/archives/2007_2_2_526.html
http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/17473f2d8408b80ba975d7ccdc29a3c9
http://blog.livedoor.jp/nob11/archives/50877424.html
http://imprezza-inada-1973.seesaa.net/article/32675456.html
http://onojo-kawakubo.seesaa.net/article/32511147.html










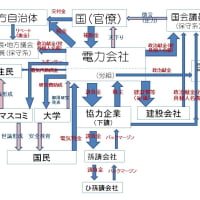




分かりやすく説明され、しかもTBまで…ありがとさんです。
おいらのような感情論で記事をかくシロートさんには分かりにくいことなので、
大助かりです。
少々長くなりすぎてしまいました。もう少しきれいにまとめられれば良かったなあ,とちょっとばかり反省しております。
しかし,手前味噌ですが,こうしておけば,「何が問題か」が分かりやすくなるかなあ,って思います。