
20日の金曜日から彼岸入り
お彼岸の供物といえば「おはぎ」
今では年中食することができますが、小豆の収穫に合わせた秋が旬といえます。
春のお彼岸では、牡丹餅と名前が変わります。
季節の感性を大切にする日本人らしい変化です。
さらに夏と冬にも「おはぎ」の別の呼び方があります。
夏は夜船
冬は北窓
おはぎは、お餅のように杵でぺったん、ぺったんと音を出して作りません。
いつついたのかわからないので「つき知らず」
夜の闇にまぎれて着く船は、いつ着いたのかわかりません。
夏の夜のイメージの夜船と名前がなったようです。
北窓も、北窓から月が見えないことから「月知らず」となり
冬のイメージと重なっておはぎの冬の呼び名だそうです。
(言葉遊びとしても、ちょっと強引すぎるような気もしますが・・・・)
おはぎは、表面を覆う小豆が萩の花に似ていることから「萩の花」と呼ばれ、転じておはぎとなったようです。

この言葉は室町時代の女官たちの間で使われた隠語のひとつで女房詞(にょうぼうことば)と呼ばれます。
頭に「お」がつく言葉はその代表的なものです。
「おかず」「おなか」「おにぎり」「おでん」と他にも随分あります。
なんとなく上品ですよね。
日本語も変化をしてきました。
こうした古い言葉も残り、外国語も柔軟に取り入れ、新語も続々出てきています。
これからの時代、外国人も多く住むようになってくるでしょうから、どんなふうに変わっていくのでしょうか。










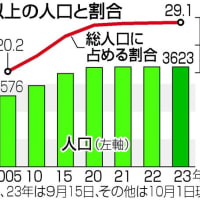















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます