
神奈川県大磯で左義長が12日におこなれます。
⇒イソタビ
大磯北浜海岸で燃えさかる火は、神業のような光景でしょうね。
住民の子どもたちから大人まで参加しますので、こうした体験は、大人になって懐かしくどこか心に残っているので、いい思い出になります。
また地域の伝統行事も先々守られていきますね。
左義長は平安時代に清涼殿(今でいう天皇の御所にあたるでしょうか)の東庭で行われた宮中行事に由来します。
毯杖(ぎっちょう)を三脚にし、束ねた竹を結んで立てます。
そこへ、短冊や扇子などを載せて陰陽師が謡い踊りながら燃やしていきます。
厄払いやその年の占いも兼ねていました。
左義長の様子
⇒goo辞書
毯杖は木製の杖(ホッケーのスティックのような形ですね)のことで、これで球を打ち相手のゴールへ入れる平安時代の遊びです。
⇒広島県教育委員会
三本の毯杖を使うことから三毯杖(さんぎっちょう)となり、それが転じて左義長と呼ばれるようになったようです。
(左義長へと言葉が転じたのには、”仏教の書を左に、道教の書を右に置き、焼いて優劣を試みたところ、仏教の書が残り、左の義長ぜり(優れている)という「訳経図記」にある故事からという俗説〔徒然草寿命院抄〕”(⇒コトバンク)があるようですが、真偽のほどはわかりません。
この左義長の行事が一般庶民や農民にも普及し、今のどんど焼きという形になっていきます。
現在でも、左義長の名前のまま行事が行われています。
一年の始まりに、厄払いを行い、いい年でありますようにと、様々な行事が行われます。
正月も三が日、鏡開きと過ぎ、そろそろ終わりの時ですね。










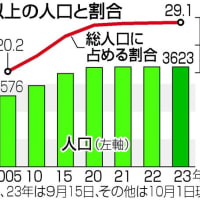















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます