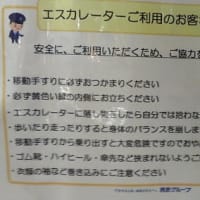2014年4月7日(月)東京春祭ワーグナー・シリーズvol.5
東京文化会館
【演目】
ワーグナー/『ニーベルングの指環』序夜「ラインの黄金」(演奏会形式)
【出演】
ヴォータン:エギルス・シリンス/ドンナー:ボアズ・ダニエル/フロー:マリウス・ヴラド・ブドイウ/ローゲ:アーノルド・ベズイエン/アルベリヒ:トマス・コニエチュニー/ミーメ:ヴォルフガング・アブリンガー=シュペルハッケ/ファーゾルト:フランク・ヴァン・ホーヴ/ファーフナー:シム・インスン/フリッカ:クラウディア・マーンケ/フライア:藤谷佳奈枝/エルダ:エリーザベト・クールマン/ヴォークリンデ:小川里美/ヴェルグンデ:秋本悠希/フロースヒルデ:金子美香
【演奏】
マレク・ヤノフスキ指揮 NHK交響楽団
毎回オーケストラにN響を起用して行われるワーグナー・シリーズは「東京・春・音楽祭」の目玉公演とも言える。去年は聴かなかったが、今回はいよいよリング4部作の最初を飾る「ラインの黄金」が上演されるので、これはまず聴いておきたい!ということで2年ぶりに東京文化会館へ。
僕にとっての「ラインの黄金」と言えば、5年前にウィーンで観たウェルザー=メスト指揮の公演。「なんじゃこれは!?」と言うほどのとてつもない体験を味わったが、我らがN響だって過去にすごいワーグナーを聴かせてくれたことがあるし、もしかしたらあのウィーンの公演の感動を追体験させてくれるかも、そんな期待を抱いて出掛けたが…
今夜の公演を聴いて思い知ったのは、このリングという作品が、あまたの大規模な作品を世に送り出したワーグナーの作品の中でも、いかにとてつもなくでかい存在で、これに立ち向かうことがいかに困難か、ということ。「でかい」とは、オケ編成の規模や作品の長さという数値で測れるものだけではなく、作品に詰め込まれたエネルギーというか濃度というか、更にこの「ラインの黄金」に関して言えば、「神々の黄昏」にまで至る壮大な絵巻物のプロローグとしての、物語全体を包み込む力とか予見する力とか、とにかく知性や感性やテクニックだけでは太刀打ちできないパワーやしつこさが必須だということを思い知った。
N響はよく健闘していたとは思うが、そこには地響きするほどの重量感や、一旦食らいついたらなにがなんでも放さないという執念や、会場の空気を熱し、上気させ、その空気を会場内にぐわんぐわんと対流させるようなエネルギー、そういった過度で貪欲なほどの能動性という点ではいかにも力不足。最後のヴァルハラ城への入場だけでも陶酔感に浸りたかった。大きな音で吠えればいいというわけではもちろんないが、最後は巨大な音圧に圧倒されたかった。指揮のヤノフスキもN響から底力を引き出すことはできなかった。
逆に、お手本のようなアグレッシブな姿を見せつけたのが、アルベリヒを歌ったコニエチュニー。この歌手の歌は最初の場面の黄金を奪う時から、一種異様な凄みがあった。腹のそこから涌き出て噴き出す露わな感情が、リアルに物語の核心を捉え、聴き手を引き込んでいった。ラインの黄金から造られた「指輪」への執着、そこにかけられた呪いが、これからの神々の運命を表現していたと言ってもいい。こういう気概をオケにも持ってほしかった。対する神々の長であるヴォータンを歌ったシリンスは、味わい深い貫禄は出ていたが、終幕前のクライマックスとしてクローズアップされるヴァルハラ城の主としての威厳には少々物足りなさを感じた。
そうした烈しさとは一線を画したところで異彩を放ったのはクールマンが歌ったエルダ。客席側のバルコニーから発せられたその歌声はまさしく神々しい彩光に覆われ、「啓示」として会場に響き渡って息を呑んだ。
フリッカを歌ったマーンケは奥行きを感じる貫禄を聴かせたが、女声ではむしろ藤谷のフライアを挙げたい。助けを切に求める切迫感がリアルに伝わってきて、出番を待ちわびるほど。ラインの乙女たちを歌った小川、秋本、金子の3人も立体感のある生き生きとした描写が印象に残った。
演奏会形式で行われたが、例によってステージ後方のスクリーンではいくつかのシーンが映し出された。ラインの川底の画像、ニーベルハイムの洞窟の描写、そしてヴァルハラ城が聳えるシーン。ただこれはどうにも中途半端で、最後のヴァルハラ城への入場には過度な期待をしていただけに、何も起こらずにがっかり。これならむしろ映像はいらないのでは、と思った。
ウィーン国立歌劇場公演「ラインの黄金」2009.5.16 ウィーン・シュターツオーパー
このウィーン国立歌劇場の公演の感想を読み返していて、アルベリヒが今夜と同じコニエチュニーだったことが判明した!
東京文化会館
【演目】
ワーグナー/『ニーベルングの指環』序夜「ラインの黄金」(演奏会形式)

【出演】
ヴォータン:エギルス・シリンス/ドンナー:ボアズ・ダニエル/フロー:マリウス・ヴラド・ブドイウ/ローゲ:アーノルド・ベズイエン/アルベリヒ:トマス・コニエチュニー/ミーメ:ヴォルフガング・アブリンガー=シュペルハッケ/ファーゾルト:フランク・ヴァン・ホーヴ/ファーフナー:シム・インスン/フリッカ:クラウディア・マーンケ/フライア:藤谷佳奈枝/エルダ:エリーザベト・クールマン/ヴォークリンデ:小川里美/ヴェルグンデ:秋本悠希/フロースヒルデ:金子美香
【演奏】
マレク・ヤノフスキ指揮 NHK交響楽団
毎回オーケストラにN響を起用して行われるワーグナー・シリーズは「東京・春・音楽祭」の目玉公演とも言える。去年は聴かなかったが、今回はいよいよリング4部作の最初を飾る「ラインの黄金」が上演されるので、これはまず聴いておきたい!ということで2年ぶりに東京文化会館へ。
僕にとっての「ラインの黄金」と言えば、5年前にウィーンで観たウェルザー=メスト指揮の公演。「なんじゃこれは!?」と言うほどのとてつもない体験を味わったが、我らがN響だって過去にすごいワーグナーを聴かせてくれたことがあるし、もしかしたらあのウィーンの公演の感動を追体験させてくれるかも、そんな期待を抱いて出掛けたが…
今夜の公演を聴いて思い知ったのは、このリングという作品が、あまたの大規模な作品を世に送り出したワーグナーの作品の中でも、いかにとてつもなくでかい存在で、これに立ち向かうことがいかに困難か、ということ。「でかい」とは、オケ編成の規模や作品の長さという数値で測れるものだけではなく、作品に詰め込まれたエネルギーというか濃度というか、更にこの「ラインの黄金」に関して言えば、「神々の黄昏」にまで至る壮大な絵巻物のプロローグとしての、物語全体を包み込む力とか予見する力とか、とにかく知性や感性やテクニックだけでは太刀打ちできないパワーやしつこさが必須だということを思い知った。
N響はよく健闘していたとは思うが、そこには地響きするほどの重量感や、一旦食らいついたらなにがなんでも放さないという執念や、会場の空気を熱し、上気させ、その空気を会場内にぐわんぐわんと対流させるようなエネルギー、そういった過度で貪欲なほどの能動性という点ではいかにも力不足。最後のヴァルハラ城への入場だけでも陶酔感に浸りたかった。大きな音で吠えればいいというわけではもちろんないが、最後は巨大な音圧に圧倒されたかった。指揮のヤノフスキもN響から底力を引き出すことはできなかった。
逆に、お手本のようなアグレッシブな姿を見せつけたのが、アルベリヒを歌ったコニエチュニー。この歌手の歌は最初の場面の黄金を奪う時から、一種異様な凄みがあった。腹のそこから涌き出て噴き出す露わな感情が、リアルに物語の核心を捉え、聴き手を引き込んでいった。ラインの黄金から造られた「指輪」への執着、そこにかけられた呪いが、これからの神々の運命を表現していたと言ってもいい。こういう気概をオケにも持ってほしかった。対する神々の長であるヴォータンを歌ったシリンスは、味わい深い貫禄は出ていたが、終幕前のクライマックスとしてクローズアップされるヴァルハラ城の主としての威厳には少々物足りなさを感じた。
そうした烈しさとは一線を画したところで異彩を放ったのはクールマンが歌ったエルダ。客席側のバルコニーから発せられたその歌声はまさしく神々しい彩光に覆われ、「啓示」として会場に響き渡って息を呑んだ。
フリッカを歌ったマーンケは奥行きを感じる貫禄を聴かせたが、女声ではむしろ藤谷のフライアを挙げたい。助けを切に求める切迫感がリアルに伝わってきて、出番を待ちわびるほど。ラインの乙女たちを歌った小川、秋本、金子の3人も立体感のある生き生きとした描写が印象に残った。
演奏会形式で行われたが、例によってステージ後方のスクリーンではいくつかのシーンが映し出された。ラインの川底の画像、ニーベルハイムの洞窟の描写、そしてヴァルハラ城が聳えるシーン。ただこれはどうにも中途半端で、最後のヴァルハラ城への入場には過度な期待をしていただけに、何も起こらずにがっかり。これならむしろ映像はいらないのでは、と思った。
ウィーン国立歌劇場公演「ラインの黄金」2009.5.16 ウィーン・シュターツオーパー
このウィーン国立歌劇場の公演の感想を読み返していて、アルベリヒが今夜と同じコニエチュニーだったことが判明した!