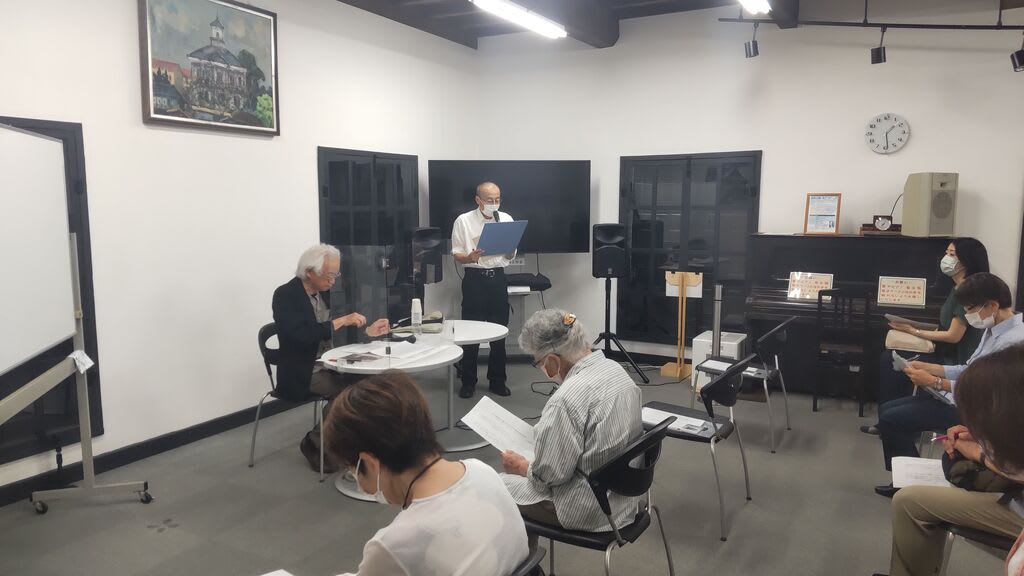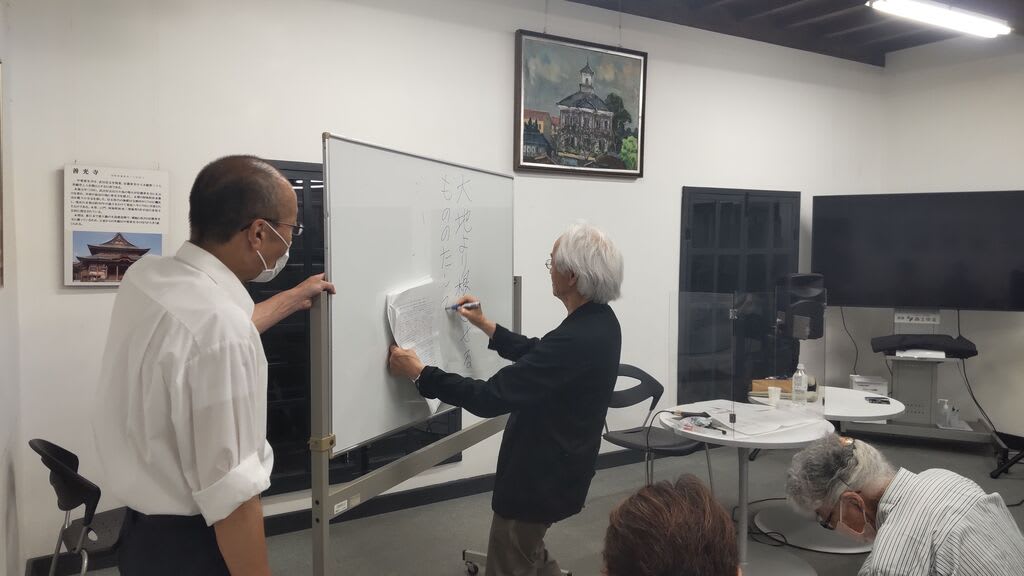7年ぶりに行われた、善光寺御開帳。
多くの皆さまが、この間、六善光寺を訪れていると聞いています。
甲斐善光寺にも、朝から大型バスが入れ替わり立ち替わり。
信玄ミュージアム企画展をご覧になって、「せっかくだから寄って行こう」と、いう声も
この展示期間中何度も耳にし、
「車で何分くらいですか?」と、いうお問い合わせも「ほうとうはどこで食べられますか?」
の質問と同じくらい受けたような気がします。
少しでも地域貢献できたかな?と思うところですが、そんな御開帳も6月29日まで。
いよいよ10日を切りました。
7年に1度ですので、興味のある方はお近くの善光寺へどうぞ。
さて、善光寺は、ご本尊が日本最古で絶対秘仏だったり、宗派も問わなければ、
早い時期から女人救済もうたうなど、とても特徴のあるお寺です。
御開帳されている前立てご本尊は、善光寺ならではの「一光三尊形式」で、
中央に阿弥陀如来、脇には、向かって右に観音菩薩、左に勢至菩薩が。
そして、三尊の印相、つまり手の形も、他ではあまり見られない珍しいものだとか。
阿弥陀如来の基本の印相といえば、親指と人差指で輪を作った「(禅)定印」や、
臨終におよび、西方浄土から迎えにいらっしゃる時の印相、指で輪を作った形が特徴の「来迎印」。
極楽往生の段階を示す「九品往生(くぼんおうじょう)」に基づく印相も。
一方、善光寺式の阿弥陀如来の印相は、
衆生の畏れを取り除くという意味が込められた「施無畏印(せむいいん)」と
チョキを閉じたような形の「刀印」。
阿弥陀如来の脇侍をつとめる、
あらゆる人を慈悲の心で救う観音菩薩は、多くの場合、蓮華を捧げ持ち、
知恵によって、人を苦しみから救い、仏道に引き入れることで正しい行いへ導く勢至菩薩は合掌されて。
けれども善光寺の観音菩薩と勢至菩薩は、
共に、胸の前で、左の掌に右の掌を水平に重ねる「梵篋印(ぼんきょういん)」という印相。
そして、掌に包むようにされているのは、真珠の薬箱・・だとか。
三尊仏の出現のきっかけとなった、印度・毘舎離国の悪疫を癒やし、
まん延をおさめた霊験譚を表しているのでしょうか。
それとも別の意味が込められているのでしょうか。
本当のことは、あまり広く知らされていないのかもしれませんが・・
いずれにしても、「善光寺式」の特徴、一光三尊方式や印相などは、
彫像であろうと、画像であろうと、大切な要素として踏襲されていることは確かなよう。
「善光寺縁起」によれば、信州善光寺のご本尊は、
552年、百済の聖明王より日本に贈られたとありますが、
6〜7世紀頃、朝鮮半島で制作された「如来および両脇侍像」(東京国立博物館像)が、
ご本尊とかなり近い特徴を示しているのも、なかなかどうして興味深い!
【1089ブログ】本館3室と11室で善光寺本尊について考える
長野・善光寺の本尊は絶対の秘仏で写真さえありません。 7年に一度御開帳があるのは、実はお前立ち(本尊の身代わり)で、本尊の厨子が開くことはありません。 お前立ちは...
↑13世紀、鎌倉時代に制作された像(2つ)と、6〜7世紀、朝鮮半島で制作された像の比較はこちらで♪
・・・
当館特別展示室にて開催中の企画展、「甲斐国領主と善光寺」第3段では、
甲斐善光寺所蔵の「一光三尊阿弥陀如来画像」を展示中✨
普段はお目にかかれない画像と、間近で対面できます。
小ぶりで、かわいらしささえも感じる画像で、
善光寺の阿弥陀如来さまとご縁を結んでみませんか。