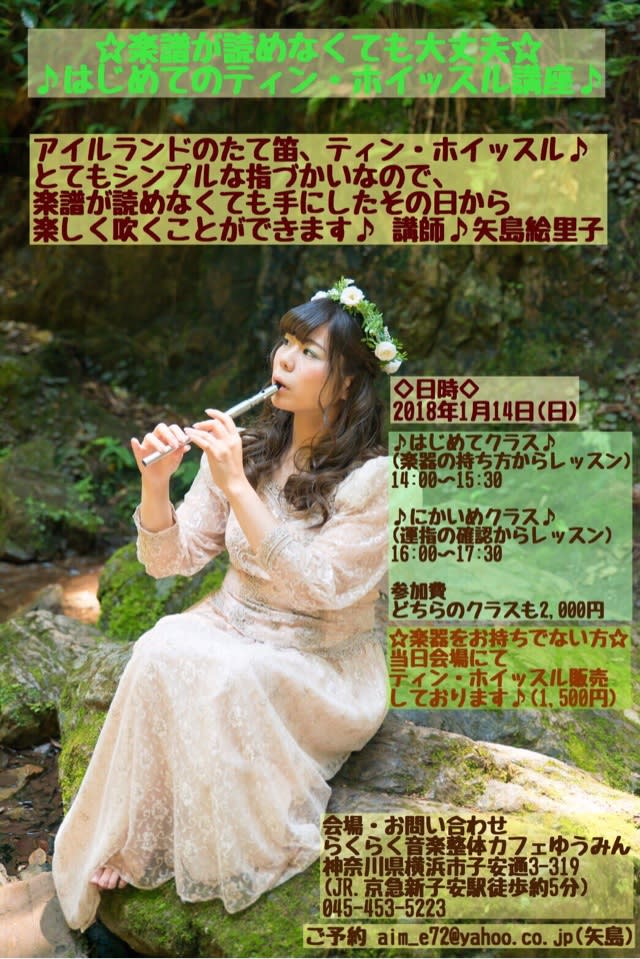【2018.1.16 購入音源】
何ヶ月ぶりだろう。プログレの未聴音源を漁ってきた。

◯Gordon Giltrap『Peacock Party』(1979年8作目)
イギリスの名ギタリストのソロ名義作。木管楽器や弦楽器やクルムホルン奏者などがサポートしている。
少し変わったバンド編成が特徴。
◯Flook『Flatfish』(1999年作)
アイルランド出身のフルーティスト、ギター、バウロン奏者の4人組による、オール・インスト・アルバム。
◯Procol Harum『Grand Hotel』(1973年6作目)
デビュー当時から、鍵盤のテクニックに関しては、プログレを代表するものがあった。オリジナルメンバーとは異なる顔ぶれだが、2人の鍵盤奏者(ピアノとオルガン)が在籍。
◯Spock's Beard『The light』(1995年1作目)
イギリスのシンフォ・プログレによる、1995年デビュー作。
メロトロンが2台使われている。
◯Aria Palea『Zoicekardi'a』(1996年1作目)
イタリアのフォーク・プログレ。
フルーティスト在籍。
◯Nuova Era『L'ultimo Viaggio』(1988作1作目)
イタリアのプログレッシヴ・ロック。オルガンとシンセサイザー入り。
◯Lesiem『Mystic Spirit』(2002年2作目)
ドイツのニューエイジ。
◯Fabrizio De André『Le nuvole』(1990年12作目)
イタリアのシンガー・ソングライター。幼少期にバイオリンを習い、後にジャズ・ギターに転向している。
◯Mosaic『Miniatures』(1995年作)
イタリアのプログレ。よく分からないが、40曲入り。
◯Procol Harum『Novum』(2017年13作目)
デビュー50周年を記念したアルバムの邦題は『乙女は新たな夢に』。ジャケットの絵には、過去のアルバムに描かれたモチーフが使用されている。
◯Popol Vuh『Hosianna Mantra』
ドイツのエレクトロ系プログレで、名盤と評価されている。ピアノやハープシーコードが使われている。
◯Emmanuel Booz『Le Jour Ou Les Vaches』(1974年作)
フランスのプログレ。あまり情報は得ていないが、古きよき味わいが感じられそうなバンドだと思える。
◯Monarch Trail『Sand』(2017年2作目)
カナダの新鋭プログレ。
◯Triana『El Patio』
スペインのシンフォニック・プログレ。メンバーの中に、フラメンコ・ギターを弾いているギタリスト在籍。
つまりクラシックからの影響もかなりありそうな感じ。
◯Sithonia『Spettacolo Annullato』(1992年2作目)
イタリアのプログレ。まずは猫のジャケットに気を惹かれた。
2人のキーボーディスト在籍。
所感は後日、時間があるときに、聴いてから、書きたいと思う。